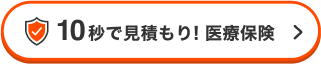5. 【ケース別】妊娠時期別の医療保険選び
出産時のトラブルには、民間の医療保険で備えることができます。ここからは、医療保険の選び方についてケース別にご紹介していきます。
5.1 妊娠前の検討
妊娠前であれば医療保険の選択肢は豊富です。異常分娩に手厚く備えたい場合は、女性疾病特約付きの女性医療保険がおすすめです。ただし、不妊治療中の場合は特別条件が付く可能性があります。
5.2 妊娠中の加入
妊娠中の医療保険加入では、多くの保険会社で妊娠・出産関連の異常について1年程度の不担保期間が設定されます。
今回の出産には適用されませんが、将来の出産に備える意味で検討する価値があります。
5.3 出産後の見直し
正常分娩での出産後は比較的スムーズに加入できますが、異常分娩の場合は1〜5年程度の特別条件が付く可能性があります。年齢上昇による保険料増加を避けるためにも、早期の検討をおすすめします。
6. 出産育児一時金、育児休業給付金…出産時に利用できる公的制度
まずは出産時に利用できる公的制度を確認したうえで、足りない分を民間の医療保険でカバーするように心がけましょう。ここからは、出産時に利用できる公的制度とその申請方法について詳しく解説します。
6.1 出産育児一時金
妊娠4カ月(85日)以上での出産に対し、1児につき50万円が支給されます。会社員だけでなく、扶養者や国民健康保険加入者も対象となり、直接支払制度の利用も可能です。
6.2 出産手当金
産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までの期間で、給与支払いがない場合に支給されます。1日当たりの金額は従前給与の約2/3となります。
6.3 育児休業給付金
1歳未満の子どもを養育するための育児休業期間中に支給され、開始から180日までは給与の67%、それ以降は50%が支給されます。夫婦ともに対象となり、出生時育児休業給付金制度も利用可能です。
6.4 高額療養費制度と医療費控除
異常分娩で公的保険適用時に利用でき、月額上限を超えた医療費が還付されます。また、年間医療費が10万円を超えた場合は医療費控除の対象となり、確定申告による税額軽減が可能です。
7. まとめ
今回は、吸引分娩が保険適用になるのか、出産費用や公的制度の活用について解説しました。
吸引分娩は一般的に異常分娩とされ、公的医療保険や民間の医療保険が適用となる可能性が高いです。特に女性向け医療保険に加入していれば、上乗せの給付金で経済的な安心感につながるでしょう。
今後妊娠・出産を検討している方は、加入できる今のうちに、保険の検討を進めておくことをおすすめします。
参考資料
- 日本産婦人科医会「産婦人科社会保険診療報酬点数早見表 令和4年4月」
- 日本産科婦人科学会 日本産婦人科医会「産婦人科診療ガイドラインー産科編2023」
- 厚生労働省「出産費用の見える化等について」
- 厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
- 厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」
- 全国健康保険協会 協会けんぽ「子どもが生まれたとき」
- 全国健康保険協会 協会けんぽ「出産手当金について」
- 全国健康保険協会 協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」
ほけんのコスパ編集部