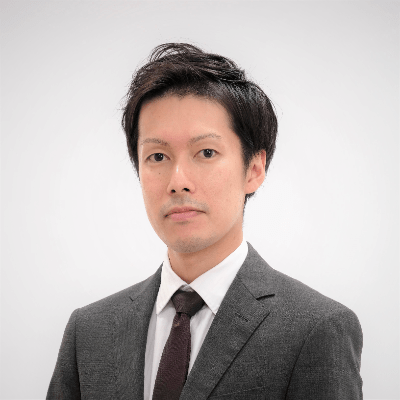3.3 配偶者の扶養に入る場合
配偶者が会社員や公務員で社会保険に加入している場合、所得要件を満たせばその扶養に入ることができます。
この場合、自分の保険料負担はありません。
とくに退職後の収入が年金中心で一定額以下であれば、もっとも負担の少ない選択肢となります。
ただし、アルバイト収入などが基準を超えると扶養から外れるため、収入見込みを事前に確認する必要があります。
4. 定年退職に向けて「シミュレーション」することも大切です
定年退職後は、まとまった退職金の受け取りやiDeCoの引き出し、健康保険の切り替えなど、大きなお金に関わる手続きが一度にやってきます。
これらの選択を誤ると、税金や保険料の負担が膨らみ、思わぬ「損」につながることも。
退職金とiDeCoは、一時金と年金形式の選び方、受け取る年度をずらす工夫によって、控除を最大限に活かせます。
健康保険も、任意継続・国保・扶養の3つから世帯にとってもっとも有利なものを選ぶことが大切です。
老後資金を効率よく守るには、事前にシミュレーションを行い、手取り額がどう変わるかを確認しておくことが重要です。
早めの準備と正しい知識で、安心してセカンドライフを迎えましょう。
参考資料
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 財務省「令和7年度税制改正の大綱」
- 全国健康保険協会「退職後の健康保険について」
- 厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」
加藤 聖人