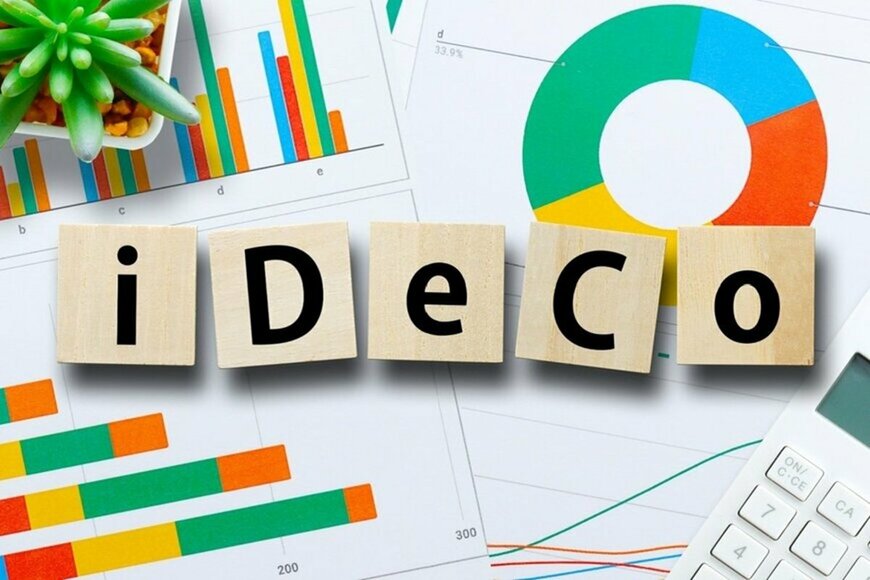2. 【お金の手続き②】iDeCoの受け取り方で損しないために
定年退職後に受け取る資産として、退職金のほかに大きな位置を占める可能性があるのが、個人型確定拠出年金(iDeCo)です。
iDeCoは「一時金形式」「年金形式」「一時金と年金の併用」のいずれかを選べますが、退職金との兼ね合いによって税負担が大きく変わります。
2.1 一時金で受け取る場合
iDeCoを一括で受け取ると、退職金と同様に「退職所得」として扱われます。
この場合、退職所得控除が適用されますが、退職金の受け取り後19年以内にiDeCoを一時金で受け取ると、控除枠が重複してしまうため、非課税メリットを十分に活かせなくなる恐れがあります。
例えば、勤続40年の場合の退職所得控除は2200万円ですから、退職金が2200万円以上であれば控除額を使い切ってしまうことになります。
その後19年以内にiDeCoを一時金形式で受け取る場合は課税対象額が増え、想定以上の税負担になる可能性があるため注意が必要です。
一方、iDeCoを先に受け取り、5年以上(2026年1月以降は10年以上)あけて退職金を受け取る場合はそれぞれに退職所得控除が適用されるため、税制面では有利といえます。
ただし、iDeCoは原則として60歳にならないと受け取れないため、退職金の受け取り時期を65歳以降(2026年1月以降は70歳以降)に遅らせる必要があります。
60歳以降も長く働く、もしくは会社の退職金の受け取りを繰り下げられることが前提となるでしょう。
2.2 年金形式で受け取る場合
iDeCoを分割で受け取ると「雑所得」に区分され、公的年金等控除の対象になります。
年金収入全体の中で一定額が非課税となるため、毎年少しずつ受け取ることで課税を分散できるメリットがあります。
特に退職金を同時期に受け取る予定がある場合は、iDeCoを年金形式にすることで税負担のバランスをとることができます。
2.3 受け取り方の組み合わせ
退職所得控除を十分に活用できる場合は、退職金を一時金で受け取り、iDeCoを年金形式で分割する方法が有効です。
こうすることで退職所得控除を最大限に活用しつつ、公的年金等控除も利用できます。
また、iDeCoは一時金と年金形式を併用できるため、退職所得控除の範囲内は一時金、残りは年金形式で受け取るといった方法も選択可能です。
退職金とiDeCoは、それぞれ大きな資産であると同時に、税制上の扱いが異なるため、受け取り方や時期の調整によって手取り額が大きく変わります。
受給開始前にシミュレーションを行い、最も有利な方法を検討することが大切です。