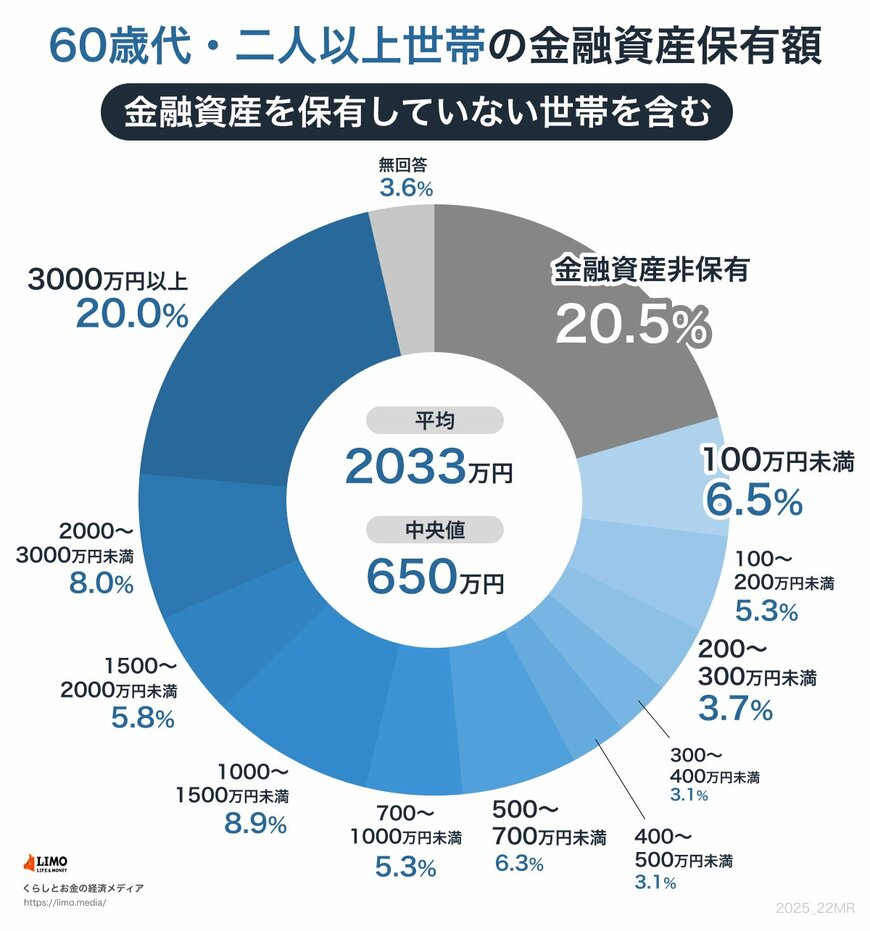お盆真っ只中とあり、親戚でゆっくり集まっているという家庭も多いでしょう。
お正月のようにお年玉などの支出はありませんが、やはり孫へのお小遣いや食費などで、普段より支出が高まるというシニア世帯は多いです。
転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリア株式会社によると、例年と比べた今夏の出費は「増える派」が86.0%となっています(2025年 夏の出費実態調査/2025年6月30日公表)。
出費が多い時期は、貯蓄を取り崩すこともあるでしょう。
では、一定の年金額でやりくりする「年金生活」に入っている世帯も多いと考えられる60歳代~70歳代世帯は、どれほどの貯蓄を備えているのでしょうか。
60歳代→70歳代世帯における貯蓄額の違いを見ていきましょう。
1. 60歳代の貯蓄額(平均や金額のボリュームゾーン)
J-FREC 金融経済教育推進機構が公表する「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」より、60歳代・二人以上世帯の貯蓄(金融資産を保有していない世帯を含む)を見ていきましょう。
※貯蓄額には、日常的な出し入れ・引落しに備えている普通預金残高は含まれません。
1.1 60歳代の二人以上世帯の貯蓄額
60歳代の貯蓄額をみると、平均は2033万円、中央値は650万円となりました。
- 金融資産非保有:20.5%
- 100万円未満:6.5%
- 100~200万円未満: 5.3%
- 200~300万円未満: 3.7%
- 300~400万円未満:3.1%
- 400~500万円未満:3.1%
- 500~700万円未満:6.3%
- 700~1000万円未満:5.3%
- 1000~1500万円未満:8.9%
- 1500~2000万円未満:5.8%
- 2000~3000万円未満:8.0%
- 3000万円以上:20.0%
金額帯で区切るとボリュームゾーンになるのは「貯蓄3000万円以上」が20.0%、「貯蓄ゼロ」が20.5%でほぼ同率です。
60歳代から70歳代になるにつれ、貯蓄を取り崩す世帯も増えると予想されますが、実際にはどうなのでしょうか。