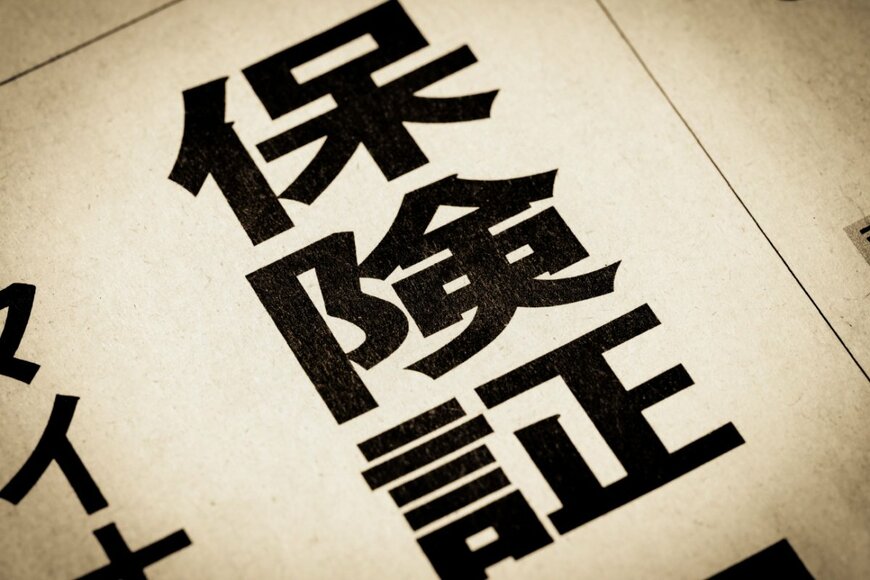2024年12月2日より、マイナンバーカードと健康保険証の一本化が開始され、従来の紙の健康保険証の新規発行は終了しました。その後はマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)が基本になり、医療手続きがスムーズになる見込みです。
しかし、75歳以上の後期高齢者に該当する方のなかには、マイナ保険証を所持していない方がいるのではないでしょうか。そこで本記事では、従来の保険証の有効期限が迫るなかでどのような対応が実施されるのかについて解説していきます。
従来の保険証が廃止される背景やマイナ保険証のメリットなどについても併せて紹介するため、ぜひチェックにしてみてください。
1. 従来の紙の保険証は7月末で終了
2024年12月2日から新規発行・再発行がされなくなった従来の紙の保険証ですが、有効期限が2025年7月31日に迫っています。特に、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方の保険証の多くは、2025年7月31日を有効期限としています。お手持ちの保険証の有効期限をご確認ください。
有効期限以降に医療機関を受診するには、マイナ保険証または資格確認書が必要になるため注意が必要です。
資格確認書については後ほど詳しく解説していきますので、その前になぜ従来の保険証が廃止されるのか簡単におさらいしていきましょう。
1.1 従来の保険証が廃止される背景とは?
従来の保険証が廃止される背景として、政府がデジタル社会における質の高い医療実現を推進していることが挙げられます。従来の紙の保険証を廃止し、マイナンバーカードと健康保険証を一体化することで、業務の効率化や安全性の向上などが期待されています。
例えば、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されたマイナ保険証を活用することで、薬局で受け取った薬の情報などをスムーズに共有できるため、初めて利用する薬局でも詳細を口頭で説明する手間を省くことが可能です。
医療機関や薬局などのデジタル化が進むことにより、医療機関側と利用者側の双方にメリットが生じる可能性があるでしょう。
1.2 「マイナ保険証」に一本化されるメリット
ほかにもマイナ保険証に一本化されることによって、以下のメリットが挙げられます。
- 医療機関窓口での事務作業といった負担を軽減できる
- 薬の情報を医療機関や薬局などと共有できる
- 救急隊への診療情報や薬剤情報などを正確に共有しやすい
- 引越しや、就職・転職の後もそのまま健康保険証として活用できる
- プライバシー保護やマイナンバーカードのセキュリティ対策を講じられている
マイナ保険証を活用することでさまざまな恩恵を期待できるものの、実際にまだマイナ保険証を持っていない高齢者の方も多いのではないでしょうか。
そのため、次章では8月以降の対応について解説していきます。