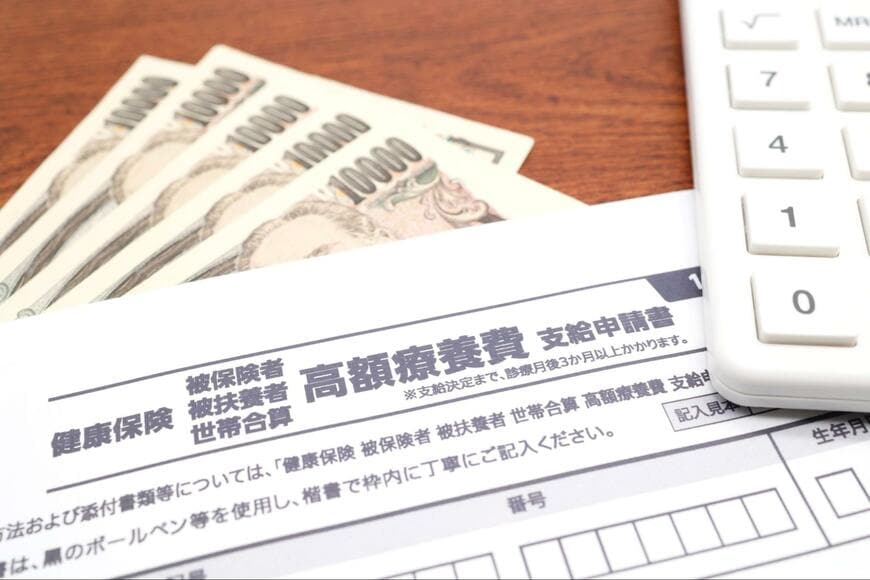75歳以上の医療費負担では、所得に応じて1~3割の区分があります。このうち「2割負担」の人への特例的な軽減措置が2025年9月末で終了し、10月からは自己負担が増えたと感じる方もいるかもしれません。
医療費の負担が増えると、支出額も大きくなります。しかし、医療費は月あたりに支払える限度額が決まっており、それを超えた分については高額療養費制度によって払い戻されます。
高額療養費制度は複雑な仕組みですが、安心して医療を受けるための大切な制度です。
この記事では、高額療養費制度のなかでも重要な「多数回該当」と「自己負担限度額」について解説します。
1. 高額療養費制度、「すべての医療費」に適用されるわけではない
高額療養費制度とは、1ヵ月間に医療機関や窓口で支払った医療費が、所定の上限額を超えた際に、超えた金額を払い戻す制度です。負担した医療費のうち、入院時の食費や差額ベッド代などは除きます。
高額療養費を受け取る際は、加入する健康保険の運営団体(会社の健康保険・市区町村など)で申請書を入手し、必要事項を記載して提出します。そのため、窓口では一度医療費を立て替えなければなりません。
ただし、事前に限度額適用認定証を加入する健康保険に申請して受け取っている場合や、マイナ保険証を活用している場合は、窓口で負担する医療費が自己負担限度額までに制限されます。
高齢になると、健康面での不安から医療機関を受診する機会が増え、定期的な通院や入院などをすることもあるでしょう。とくに入院すると、医療費の負担は高額になります。
しかし、高額療養費があれば、自己負担限度額を超えた分はすべて返ってくるため、安心して医療を受けられるのです。
次章では、高額療養費制度のポイントである自己負担限度額について解説します。