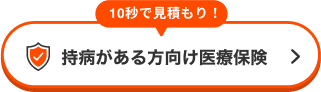5. 保険選びのポイント
持病を抱えていると、「いざというときのために保険に備えておきたい」と考える人も多いでしょう。ここからは、心療内科への通院歴がある方が保険を選ぶ際に、特に押さえておくべきポイントについて、プロの視点から詳しく解説していきます。
5.1 必要な保障の優先順位を決める
限られた予算の中で効果的な保障を確保するため、以下の優先順位で検討することをおすすめします:
- 医療保障:入院・手術費用への備え
- 収入保障:働けなくなった際の生活費
- 死亡保障:家族への経済的支援
精神疾患は平均在院日数が290日と長期化しやすいため、医療保障を優先的に検討することが重要です。
5.2 複数社での比較検討
同じ引受基準緩和型保険でも、保険会社によって保険料や加入条件は異なります。複数の保険会社の商品を比較し、最適な保険を選択しましょう。
5.3 治療経緯の整理
保険検討前に以下の情報を整理しておくことが大切です。
- 正確な診断名
- 初回診断日
- 治療内容と投薬状況
- 入院歴の有無と期間
- 現在の症状と治療方針
緩和型を検討する場合は、告知項目に該当しないか事前にしっかり確認しておきましょう。通常の保険を検討する場合は、診断から現在までの治療経過を分かりやすく告知することがポイントです。
6. 活用できる公的制度
民間の保険は、公的保険でまかないきれない部分をカバーするものです。保険選びをする前に、公的制度について知っておきましょう。
6.1 自立支援医療制度
精神疾患の継続的な通院治療について、医療費負担を1割に軽減する制度です。所得に応じて月額負担上限も設定されており、経済的負担を大幅に軽減できます。
自立支援医療制度の対象には、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害が含まれます。手続きには診断書や申出書などの書類が必要です。お住まいの地域の自治体のホームページ等を確認しましょう。
6.2 高額療養費制度
月額の医療費負担が限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。入院や手術が必要になり、医療費が高額になった際は高額療養費制度を利用して自己負担額を抑えることができます。
年収約370万円の場合、月額負担上限は約8万円となります。限度額は、年齢や収入によって異なります。入院時に備えて、あらかじめ自身の自己負担額の目安を確認しておくと良いでしょう。
6.3 傷病手当金
会社員・公務員が精神疾患で働けなくなった場合、休業4日目から給与の約2/3を通算1年6カ月間受給できます。ただし満額保障ではないため、不足分は民間保険で補完することが重要です。
また、自営業やフリーランスで働く人は傷病手当金を受け取ることができません。長期間働けなくなった時の経済的なリスクについてしっかり考えておく必要があるでしょう。
6.4 精神障害者保健福祉手帳
日常生活に支障をきたす精神疾患と認定された場合、各種支援制度を受けられます。医療費助成や公共交通機関の割引など、経済的負担軽減につながります。
自治体によって支援策の内容は異なるため、詳細についてはお住まいの地域の自治体に問い合わせてみましょう。
7. まとめ
心療内科への通院歴があっても、適切な告知を行い、自分の状況に合った保険商品を選ぶことで、必要な保障を確保することは可能です。告知義務違反は必ず発覚し、深刻なトラブルを招くため、正直な申告を心がけましょう。
引受基準緩和型保険や特定疾病保険など、選択肢は複数存在します。公的制度も併せて活用しながら、総合的なリスク対策を構築していくことが重要です。
8. 参考記事
- 厚生労働省「令和5年 患者調査 退院患者の平均在院日数等」
- 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
- 厚生労働省「障害者手帳」
- 全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」
- 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
ほけんのコスパ編集部