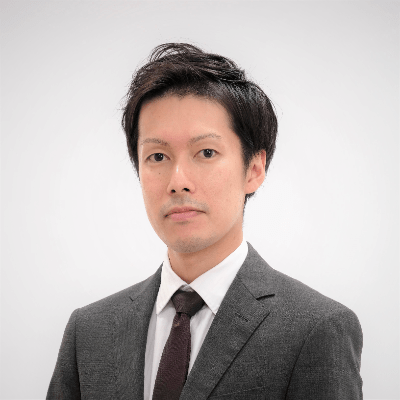4. シニア世代が知っておきたい2つのポイント
金融所得が社会保険料に影響するようになると、収入状況によっては「知らない間に保険料が増えていた」というケースが増えるおそれがあります。
以下の2つの視点から、自分に合った対策を考えましょう。
4.1 保険料対策で「源泉徴収あり」「なし」を正しく選ぶ
現在、証券口座(特定口座)の開設時に、「源泉徴収あり」か「なし」かを選択します。この選択が、将来の社会保険料負担に直結する可能性があります。
【保険料を抑えたい場合】
源泉徴収ありを選択 → 確定申告しない → 保険料に反映されない(現行制度)
【他の控除で税負担を軽くできる場合】
確定申告で配当控除や繰越控除を適用 → トータルで得になる可能性も
ただし、今後制度改正によって「源泉徴収ありでも保険料に反映される」ようになると、この判断基準も変わります。
制度の動向に注意しましょう。
4.2 NISA口座なら非課税だから安心して活用できる
2024年から新NISA制度が始まり、年間360万円までの投資が「非課税枠」で運用できるようになりました。
非課税枠で得た配当金や売却益は、税金も保険料も一切かかりません。
もちろん、NISAについては金融所得として保険料賦課の対象に含める議論の対象外となるので、安心して活用できます。
ただし、NISA枠を超える投資は通常通り課税対象となり、場合によっては確定申告が必要となります。
5. まとめにかえて
これまで社会保険料は、年金や給与など限られた所得に対して課されてきました。
しかし、金融所得も反映される流れになれば、投資の利益に応じて保険料が増えるケースが出てきます。
とくにシニア世代は、保険料だけでなく医療費・介護費用の自己負担割合まで変わる可能性があるため、制度改正の影響を無視できません。
特定口座の源泉徴収の有無やNISAの活用など、自分に合った対策を早めに検討し、賢く資産運用を続けていきましょう。
参考資料
加藤 聖人