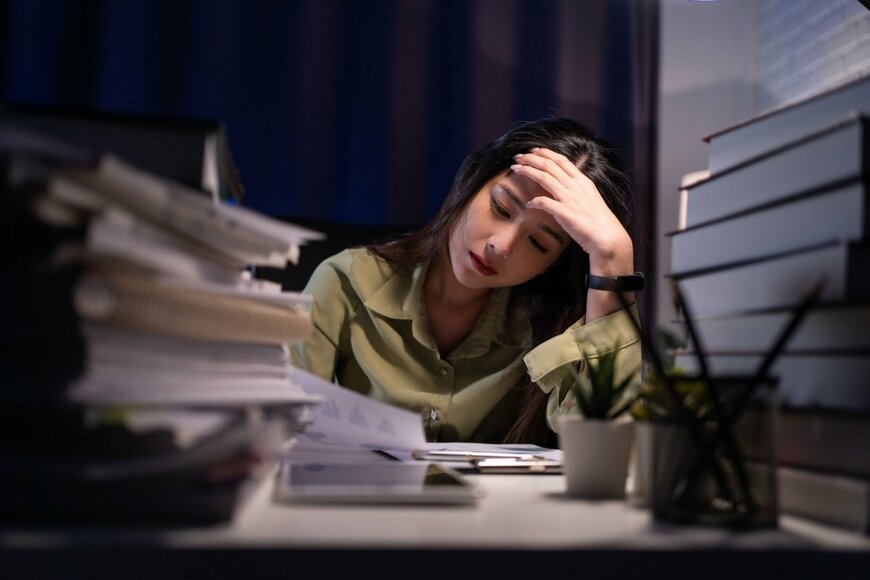年度初めは体制や担当業務の変更などがあり、忙しいと感じる人も多いでしょう。タスクの引き継ぎや業務方針の共有などを丁寧に行い、忙しい時期を乗り越えたいところです。
「4〜6月は残業しないほうがよい」といわれています。これは、9月頃から手取りが減少するためです。なぜ4〜6月の期間に残業しないほうがよいのでしょうか。この記事では「4〜6月の残業」が望ましくないとされる理由やその仕組みを解説します。
1. なぜ「4月・5月・6月」は残業しないほうがよいの?
4・5月・6月に残業しないほうがよいといわれるのは、私たちが納める社会保険料の算定基準となる「標準報酬月額」が上がってしまうためです。標準報酬月額とは、給与を一定の区分に分けて表したものです。
社会保険料の算定基準のひとつである「標準報酬月額」は、毎年7月1日に、直近3ヵ月の報酬をもとに見直されます。標準報酬月額が高いほど、保険料負担は増えます。
見直しの流れは、以下のとおりです。
- 事業主が直近3ヵ月の標準報酬月額を国に届け出る
- 国が届出をもとに標準報酬月額を見直す
見直された標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用されます。
4〜6月に残業すると、直近3ヵ月の報酬が通常の給料額よりも多くなってしまいます。そのため、例年よりも多くの報酬額が届出に記載され、標準報酬月額が上がってしまうのです。
標準報酬月額が上がり社会保険料が増えれば、その分手元に残る給料は減ってしまいます。よって、4〜6月の残業は手取り減につながるといわれているのです。
次章では、標準報酬月額に関連して、会社員が納める社会保険料について解説します。