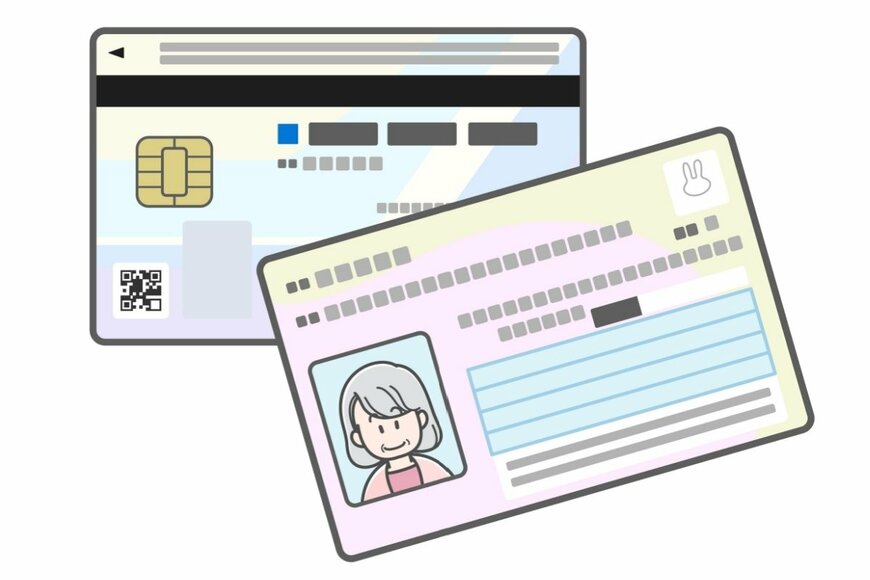協会けんぽが公表している「事業年報概要(令和4年度)」によると、令和4年度末の全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)の被保険者数は2480万人。
被用者保険には他に組合健保や各種共済がありますが、協会けんぽの被保険者数は約1650万人にのぼり、公的医療保険を運営する公法人として国内最大規模です。
それだけ多くの方が加入している協会けんぽですから、被保険者が負担する保険料が変動すると、当然ながら多くの方の給与の手取り額にも影響することになります。
そこで本記事では、協会けんぽの保険料算定に関わる来年度の保険料率について、地域ごとに上がる県、下がる県についてみていきます。一緒に確認してみましょう。
1. はたらき世代が加入する「医療保険制度」とは
日本国民はすべて、公的医療保険制度に加入することが義務付けられています。「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」のいずれかに加入することで、どこでも自由に医療を受けることができます。
なかでも、企業に雇用されている会社員が加入する「被用者保険」には、協会けんぽ、組合健保、共済組合などがあり、はたらき世代の方は、勤め先によっていずれかの制度に加入することになります。
おもに中小企業の会社員が加入する協会けんぽは、被保険者数が2480万人で最も多く、被扶養者も含めると加入者数は約4000万人にのぼります。
他方、大企業が独自に組合を設立する「組合健保」は、被保険者数は約1650万人。協会けんぽより800万人ほど少ないですが、独自の給付サービスがあり、手厚い給付が受けられるのがメリットです。