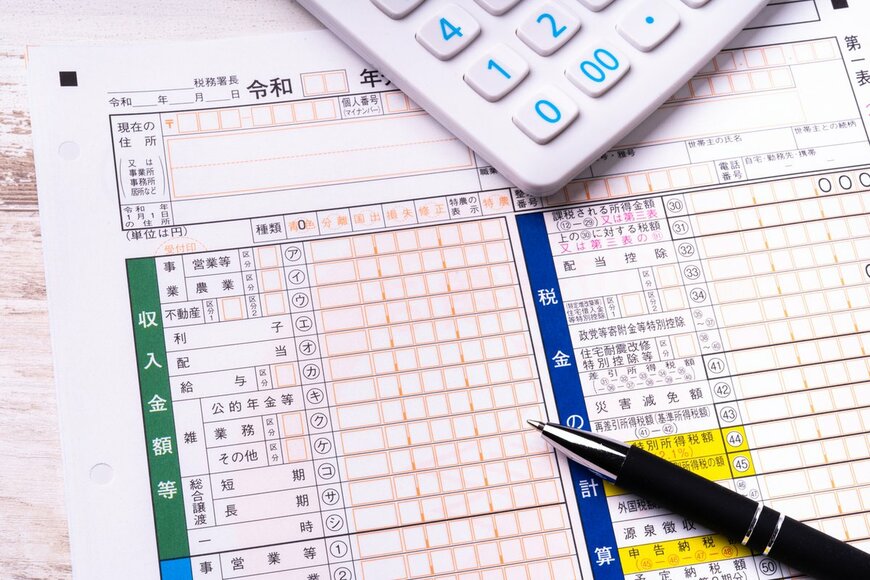5. 確定申告が不要でも申告した方がいいケースとは
確定申告不要制度により、申告が必要ないケースでも、次にあてはまる場合は確定申告をすることで税金の還付が受けられる可能性があります。
1.一定額以上の医療費を支払った
2.生命保険料や地震保険料を支払った
3.ふるさと納税をした
4.災害や盗難にあった
ただし、65歳未満は108万円以上、65歳以上は158万円以上の年金を受け取っている場合に限ります。この金額未満の場合は所得税が源泉徴収されないので、戻ってくる税金もありません。
5.1 一定額以上の医療費を支払った
自身や家族のために支払った年間の医療費が10万円(総所得が200万円未満の人は、総所得の5%)を超える場合に、その超えた部分について医療費控除が受けられます。
また、所定の健康診断を受けている人が市販の対象医薬品を購入した場合に、年間の購入額が1万2000円を超えると、超えた部分が控除の対象となるセルフメディケーション税制も利用できます。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないのでどちらかを選択する必要があります。
5.2 生命保険料や地震保険料を支払った
生命保険や個人年金保険、介護保険などの保険料を支払った場合に生命保険料控除が受けられます。また、保有している住居や家財に対して地震保険料を支払った場合には地震保険料控除が受けられます。確定申告時には、保険会社が発行する控除証明書を提出する必要があります。
5.3 ふるさと納税をした
ふるさと納税は、寄付したい自治体を選んで寄付を行った場合に、寄付金控除として、寄付額のうち2000円を超える部分について、税金の還付・控除が受けられる制度です。控除を受けるには確定申告が必要ですが、寄付した自治体が5つ以内であればワンストップ特例制度を利用して、確定申告をせずに寄付金控除が受けられます。ただし、他の控除を受けるために確定申告をした場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。
5.4 災害や盗難にあった
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。控除を受けるには、被害状況を証明する書類や保険金の支払い通知書などを用意して、確定申告を行う必要があります。
6. まとめ
年金受給者の確定申告不要制度は、公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ他の所得が20万円以下である場合に、確定申告を不要とする制度です。これにより、多くの高齢者の申告手続きの負担を減らすことができます。
ただし、医療費控除や生命保険料控除などで還付を受けられる場合は申告をした方が有利です。ご自身の年金収入や各種控除を把握して、必要に応じて申告を行うといいでしょう。
参考資料
- 国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 日本年金機構「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について
- 国税庁「高齢者と税(年金と税)」
- 国税庁「確定申告が必要な方」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」
- 国税庁「No.1145 地震保険料控除」
石倉 博子