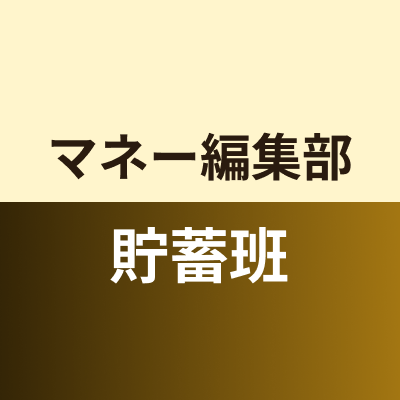3. 働き方で年金額は激変!あなたの将来を左右する厚生年金のリアル
厚生労働省は、2025年度(令和7年度)の年金額の目安として、「多様なライフコースに応じた年金額例」を5つのパターンで提示しました。
この年金額例は、令和6年の財政検証で作成された将来の年金予測(年金額の分布推計)を基にしています。
具体的には「令和6(2024)年度に65歳になる人」の加入期間や収入をモデルとし、働き方のタイプ(経歴類型)ごと・男女別に概算したものです。
3.1 多様なライフコースに応じた年金額
5つのパターンのうち、今回は「厚生年金期間中心」で働いた場合の年金額例を、男女別に見てみましょう。
3.2 厚生年金期間中心の男性
年金月額:17万3457円(+3234円)
- 平均厚生年金期間:39.8年
- 平均収入:50万9000円(平均年収は賞与含む月額換算)
- 基礎年金:6万8671円
- 厚生年金:10万4786円
3.3 厚生年金期間中心の女性
年金月額:13万2117円(+2463円)
- 平均厚生年金期間:33.4年
- 平均収入:35万6000円(平均年収は賞与含む月額換算)
- 基礎年金:7万566円
- 厚生年金:6万1551円
年金月額を男女のモデルケースで比較すると、約4万1000円の差が生じます。
この差の背景には、現役時代の平均収入の違い(月額で約15万円)と、厚生年金加入期間の差(約6.4年)が影響していることが考えられます。
厚生年金は、収入が高く、加入期間が長いほど受給額が増える仕組みのため、これらの要素が年金額に大きく反映されているのです。
また、国民年金のみに加入していた場合の平均年金月額は、男性が6万2344円、女性が6万636円です。
このことからも、厚生年金が上乗せされることによる年金額の増加分が大きいことがわかります。
これらの例からもわかるように、現役時代の働き方や収入によって、将来受け取る年金額は大きく変わります。
4. 世代別「食費」の平均はいくら?家計管理のヒント
家計管理の中でも、日常的に意識しやすく、工夫次第で節約しやすい支出のひとつが「食費」かもしれません。
ここで総務省統計局「家計調査 家計収支編(2024年)」をもとに、二人以上世帯のひと月の食費の平均を見てみましょう。
4.1 50歳代が食費のピーク!年代別平均額
全体平均 7万5258円
- ~29歳 5万2413円
- 30~39歳 6万9433円
- 40~49歳 7万9900円
- 50~59歳 8万1051円
- 60~64歳 7万9831円
- 65~69歳 7万7405円
- 70~74歳 7万4322円
- 75~79歳 6万8274円
- 80~84歳 6万6257円
- 85歳~ 6万3347円
二人以上世帯のひと月の食費平均は、50歳代がピークで約8万円。その後60歳以降は徐々に下がり、85歳以上では6万3347円に落ち着きます。
食費は家族の年齢やライフステージにより大きく変動するものですが、所得が低めの世帯では「家計に占める食費の割合(エンゲル係数)」が大きくなりがちです。
物価上昇が続く今、食料品の値動きを観察しながら、食生活や家計全体を上手に管理していけたら良いですね。
5. まとめ
今回は、65歳以上単身世帯の家計収支と、働き方による年金額の違い、そして年代別の食費データを見てきました。統計上の平均像としては、年金収入だけでは毎月約2万8000円の赤字となり、貯蓄を取り崩しながら生活している厳しい実態が浮かび上がりました。また、現役時代の厚生年金加入期間や収入が、老後の生活レベルを大きく左右する現実も確認できました。
しかし、これらのデータはあくまで平均値です。持ち家か賃貸か、健康状態によって必要な生活費は大きく変動します。
大切なのはこの現実を「自分ごと」として捉え直し、早期に対策を打つことです。
まずは「ねんきん定期便」でご自身の見込み額を確認し、「老後にいくら必要か」をご自身の価値観で試算してみましょう。
その上で、NISAやiDeCoなどを活用した計画的な資産形成を始めることが、年金赤字の不安を打ち消し、豊かな老後への確実な一歩となります。年末に向け、家計を見直すこの機会に、未来の貯蓄計画もアップデートしてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 総務省統計局「家計調査 家計収支編(2024年)第3-2表」
マネー編集部貯蓄班