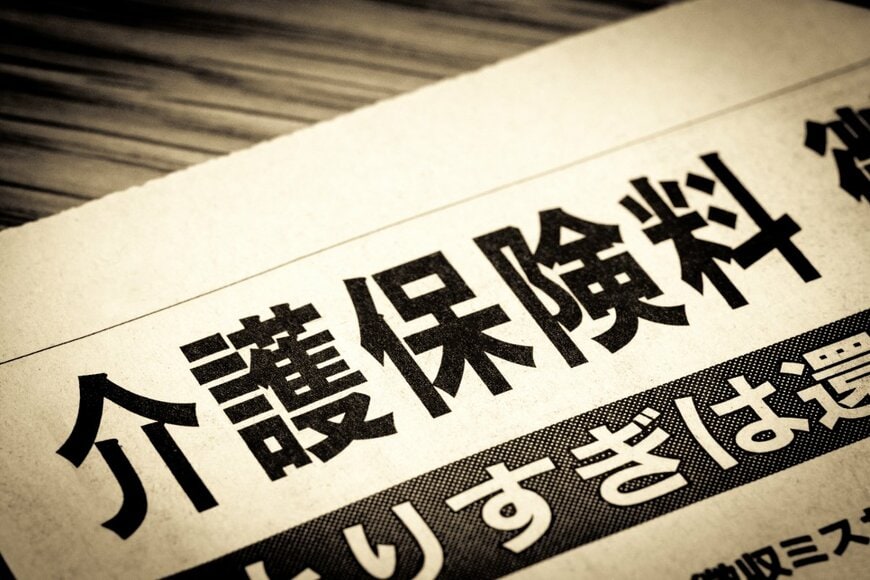「介護保険料を納めていれば老後も安心」と考える人は少なくありません。
しかし実際は、介護が必要になった際に予想以上の自己負担が生じ、家計を圧迫してしまうケースも目立ちます。
こうした負担が重くなる背景には、「制度の仕組み」や「介護保険でカバーされない費用」といった要因が関係しています。
本記事では、公的介護保険の基本を整理しつつ、介護費用への備えがなぜ必要なのかをわかりやすく解説していきます。
1. 公的な「介護保険」とは?加入対象者は誰?
介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えることを目的に設けられており、日本に住む人は40歳になると自動的に加入する仕組みになっています。
一度加入すると、その後は生涯にわたって保険料を支払う必要があり、たとえ要介護認定を受けても保険料が免除されることはありません。
40〜64歳までの現役世代(第2号被保険者)は、健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。
一方で65歳以上になると「第1号被保険者」となり、保険料は健康保険とは別枠で、年金から自動的に天引きされる方式へと切り替わります。
なお、介護サービスを利用するときには、その費用がすべて保険でまかなわれるわけではありません。
では実際に、介護サービスを利用する場合、介護保険の自己負担割合はどのように決まるのでしょうか。