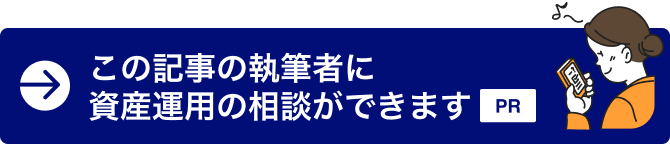3. 定額減税補足給付金(不足額給付)は「手続きが必要なケース」と「必要ないケース」が
定額減税の不足分を補う「補足給付金」は、自治体ごとに申請受付や振込手続きが進められています。
そのため、通知書の発送時期や支給開始日程は地域によって異なり、すでに案内を送付している自治体もあれば、まだ準備中の自治体もあります。
また、受け取るために申請が必要となるケースもあるため、必ずお住まいの自治体からの案内を確認しておくことが大切です。
ここでは例として、東京都港区を取り上げ、申請の基本的な流れを見ていきましょう。
3.1 「通知書」が届くケース:手続きは「原則不要」
区では、定額減税補足給付金(不足額給付)の振込先口座が記載された案内を対象者へ郵送しています。
案内に記載された口座へ給付金が直接振り込まれるため、特別な手続きは必要ありません。
3.2 「確認書」が届くケース:手続きが「必要」
区から、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となる方に「確認書」が送付されます。
必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
なお、電子申請による手続きも可能です。
「令和6年1月2日~令和7年1月1日」の間に東京都港区へ転入した方など、令和6年度の個人住民税が港区で課税されていない場合は、定額減税補足給付金(不足額給付)の案内は送付されません。
対象に該当すると思われる方は、コールセンターまでお問い合わせください(受付期限:令和7年9月30日[火]まで)。
※令和6年1月2日以降に他の自治体から港区へ転入された方については、区が令和6年度個人住民税や過去の給付金情報を把握できないため、申請書類を送付できません。
4. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」に関する詐欺・詐取にご注意!
定額減税補足給付金(不足額給付)に便乗した詐欺には十分注意が必要です。
国や自治体が電話でATMの操作を依頼したり、メールで口座番号や個人情報を求めたりすることは決してありません。
もし不審な連絡を受けた場合は、迷わず「警察相談専用電話(#9110)」に連絡するか、最寄りの警察署へ相談してください。
5. 国や自治体のサポート制度を活用しよう
今回は、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった世帯向けの「定額減税補足給付金(不足額給付)」について、支給要件と給付額を詳しく見てきました。
給付の対象者であっても、自治体から「通知書」ではなく「確認書」が届いた場合は、ご自身で申請手続きが必要です。手続きを忘れると、せっかくの給付金を受け取れなくなるので注意しましょう。
なお、今回ご紹介した補足給付金以外にも、国や各自治体では家計を支援するための様々な施策が実施されています。
常にアンテナを張り、自治体の広報誌やウェブサイトを定期的にチェックする習慣を身につけることが大切です。
日頃から情報収集を心がけることで、自分が対象となる支援策を見つけやすくなります。こうした制度を賢く活用し、家計の負担を少しでも軽減していきたいですね。
参考資料
荻野 樹