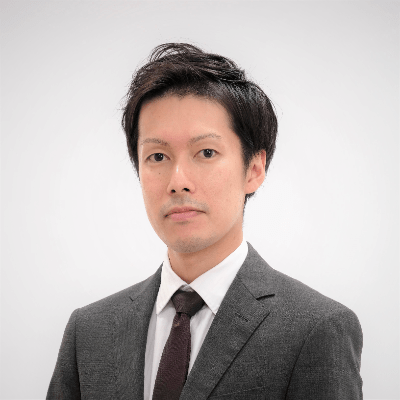3. 後期高齢者医療制度で受けられる給付12選
ここまで、制度の概要や自己負担割合について見ていきました。
続いて、東京都後期高齢者医療広域連合を例に、後期高齢者制度の加入者が受けられる給付について見ていきます。
3.1 ①療養の給付
病気やけがで医療機関を受診した際に、保険証を提示することで受けられる給付です。窓口での自己負担は1割~3割に抑えられます。
3.2 ②療養費
保険証を持たずに診療を受けた場合はいったん全額を自己負担しますが、申請によって認められた部分について自己負担分を除いた額が払い戻されます。
3.3 ③入院時食事療養費
入院した際に発生する食事代について、標準負担額を超える部分を公的医療保険が負担します。
3.4 ④入院時生活療養費
療養病床に入院したときにかかる食費や居住費のうち、標準負担額を除いた部分が負担されます。療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする人向けの病床を指します。
3.5 ⑤移送費
負傷や疾病により移動が困難で、医師の指示に基づきやむを得ず移送された場合に支給されます。緊急性や必要性が認められることが条件で、救急車は無料のため対象外です。
3.6 ⑥高額療養費
1か月ごとの医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超過分が払い戻されます。
3.7 ⑦高額介護合算療養費
1年間(8月~翌年7月)に支払った医療費と介護保険サービスの自己負担額を合算し、基準額を超えた分が払い戻されます。後期高齢者医療制度と介護保険からそれぞれ払い戻しが行われます。
3.8 ⑧保険外併用療養費
保険が適用されない治療を受けた場合でも、通常の診療と共通する部分(検査・投薬・入院料など)については保険が適用されます。
3.9 ⑨訪問看護療養費
主治医の指示で訪問看護を受けた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。
3.10 ⑩特別療養費
資格証明書の交付を受けている人が医療費を全額支払った場合、申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。ただし、保険料の未納があると相殺される場合があります。
3.11 ⑪葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った喪主に支給されます。多くの自治体で申請件数が多い給付のひとつです。
3.12 ⑫自治体独自の助成
給付とは異なりますが、保健事業の一環として独自の助成を行う自治体もあります。
4. まとめ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(または所定の障害認定を受けた65歳以上の方)が加入する高齢者専用の医療保険制度です。
医療費の窓口負担は所得水準に応じて1割・2割・3割と分かれ、特に2022年から導入された「2割負担」は多くの世帯に影響を与えています。
さらに、2025年9月末で経過措置が終了するため、その後は外来医療費の負担が増える方も出てきます。
加入者が受けられる給付は療養の給付や高額療養費の払い戻しなど多岐にわたりますが、条件や申請方法を把握しておかなければ十分に活用できません。
自身や家族の負担割合や給付の内容を確認し、必要なときに制度をしっかり利用できるよう備えておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「給付の内容」
加藤 聖人