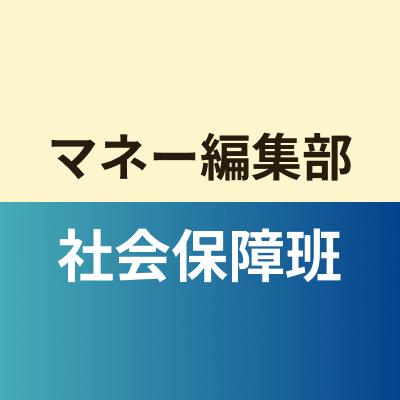6. 「生活保護」を受給している世帯はどれくらいいる?
住民税非課税世帯となり、支援を必要としているのはシニア世代だけではありません。
厚生労働省が公表した「生活保護の被保護者調査(令和5年度確定値)」によれば、生活保護を受給しているのは月平均で約164万世帯。
その内訳を見ると、高齢者世帯だけでなく、母子世帯(3.9%)や障害者・傷病者世帯(25.0%)なども一定の割合を占めています。
さまざまな事情がある世帯の暮らしを支えるため、「住民税非課税世帯」を対象とした支援は「現金給付」のような一時的なものに限りません。
国民健康保険料や介護保険料の減額、国民年金保険料の免除・納付猶予といった負担軽減策や、幼児教育・保育の無償化、高等教育の修学支援新制度といった子育て世帯向けの支援も存在します。
国が定める制度の他にも、自治体が独自に行っている支援策もありますので、活用できる制度を見逃さないよう、お住まいの地域の情報を確認してみましょう。
7. 「活用できる制度」がないか確認することが大切です
今回は「住民税のしくみ」や【住民税非課税世帯】のボーダーラインとなる《収入》や《所得》の目安はいくらなのか(札幌市の例)をもとに解説しました。
また「生活保護を受給している世帯」がどれくらいいるのかも見ていきました。
住民税が非課税になる《3つの要件》のうちの1つ「所得要件」のみ、各市区町村ごとに基準が設けられています。
収入や所得について悩んでいらっしゃる方は活用できる制度がないか、国が定める制度だけでなく、自治体が独自に行っている支援策の対象になっていないか確認することが大切です。
参考資料
- 総務省「個人住民税」
- 札幌市「個人市民税」
- 国税庁 高齢者と税(年金と税)「年金収入の所得計算、所得控除の増額」
- 厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」
- 厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和5年度確定値)の結果を公表します」
マネー編集部社会保障班