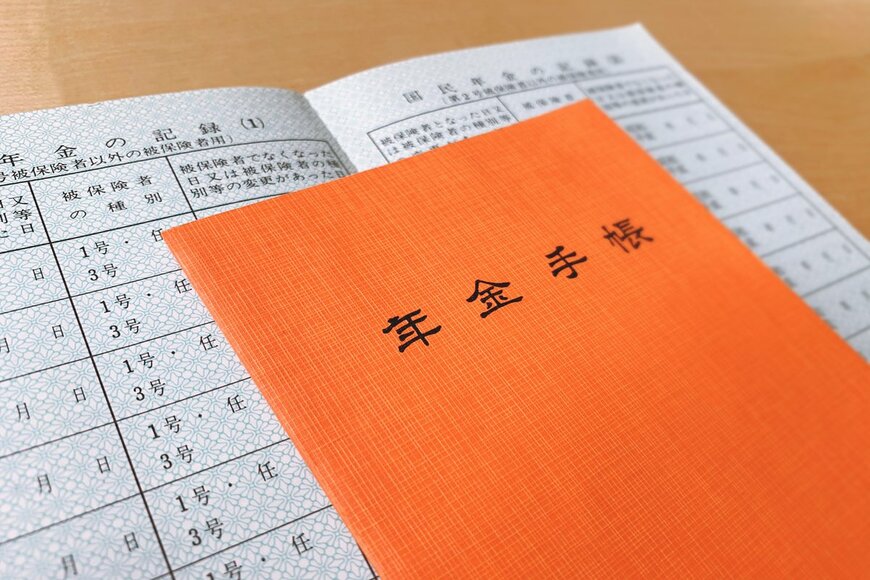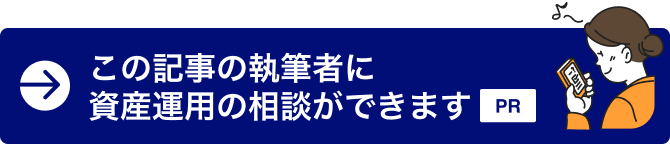2025年度の年金額は前年度から1.9%引き上げが決定しており、増額改定分が6月13日にはじめて支給されます。
しかし、増額改定率は物価上昇率を下回っており、実質的には「増えた」とは言えない状況です。
年金を収入の柱として生活するシニア世代にとって、昨今の物価上昇による家計へのダメージは甚大でしょう。
年金額は個人差があるもので、平均を大きく下回る人は少なくありません。
そこで今回は、老後に受け取る年金が「少なくなる人」の特徴と、低年金にならない対策について解説していきます。
1. 日本の公的年金制度の「キホン」をおさらい
将来的に年金を受け取ることができることは分かっていても、どの種類の年金が自分に該当するのかをしっかりと理解していない方も多いのではないでしょうか。
そこで、まずは日本の公的年金制度について整理してみましょう。
日本の年金制度は「2階建て構造」で成り立っており、基礎部分となる「国民年金(1階部分)」は、国内に住む20歳から60歳未満の全ての人を対象にしています。
国民年金の保険料は全員一律で、40年間の納付を経て、満額の年金を受け取ることが可能です。
国民年金の上に位置するのが「厚生年金(2階部分)」で、国民年金に加えて支給される仕組みとなっています。
厚生年金は主に会社員や公務員が加入し、保険料は各自の年収に基づいて異なります。
次章では、国民年金と厚生年金の具体的な受給額、受給者割合について詳しく解説します。