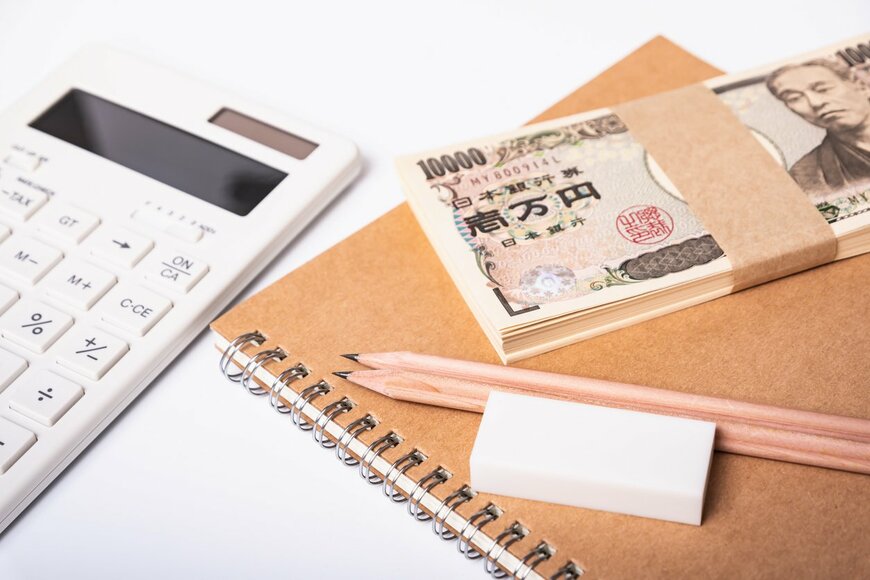日本銀行が発表した資金循環統計によると、2025年6月末時点で家計部門が保有する金融資産残高は2239兆円と過去最高を更新しました。
株価上昇や新NISA制度の拡充を背景に、投資信託や株式などのリスク資産が伸び、個人の資産運用志向が一段と高まっています。
とはいえ、資産全体が増えているといっても、世代によって保有状況には大きな差があります。特に、老後生活の柱となるシニア世帯の金融資産や年金の実態を知っておくことは、将来設計に欠かせません。
ここではまず、シニア世帯の資産の基盤となる家計全体の金融資産の内訳を確認したうえで、貯蓄額や年金額を見ていきましょう。
1. 【みんなの貯蓄】65歳以上無職夫婦の平均貯蓄額は?
総務省統計局の「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果の概要-(二人以上の世帯)」によると、世帯主が65歳以上の無職世帯(二人以上の世帯)の平均貯蓄額は2560万円でした。
1.1 世帯主が65歳以上の無職世帯の貯蓄の種類別現在高の推移(二人以上の世帯)
この貯蓄額は近年増加傾向にあり、2019年の2218万円から2024年には2560万円へと、直近5年間で右肩上がりの状態が続いています。
貯蓄の種類別に見ると、最も多いのは定期性預貯金で859万円です。次いで通貨性預貯金が801万円、有価証券(※1)が501万円、生命保険などが394万円、金融機関外(※2)の貯蓄が6万円となっています。
前年からの増加幅では、通貨性預貯金が+47万円(+6.2%)、有価証券が+21万円(+4.4%)と伸びています。
※1 有価証券:株式、債券、株式投資信託、公社債投資信託、貸付信託、金銭信託など(いずれも時価)
※2 金融機関外:金融機関以外への貯蓄のことで、社内預金、勤め先の共済組合への預金など