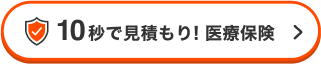2. がん治療費の実態と公的保障の限界
がん治療の基本となる手術・入院費用は、2022年の統計によると乳がんで約62万6千円、子宮がんで約69万9千円となっています。しかし、現役世代は自己負担3割となり、さらに高額療養費制度により月額の上限額が設定されています。
例えば年収500万円程度の方の場合、高額療養費制度を利用すると月額の自己負担は約8万円から9万円程度に抑えられます。ただし、これは同一月内での計算であり、治療が複数月にわたる場合は各月で計算されるため、総額では相当な負担となります。
2.1 公的保障対象外の費用負担
公的医療保険制度は基本的ながん治療をカバーしますが、すべての費用が対象となるわけではありません。代表的なものだと、差額ベッド代(個室利用料)は1日平均8000円以上、医療用ウィッグは数十万円、先進医療の技術料は陽子線治療で約269万円、重粒子線治療で約316万円が全額自己負担となります。
特に女性の場合、抗がん剤治療による脱毛への対応や、乳房再建術などの費用も発生する可能性があり、治療費用は想定以上に高額になることがあります。
がんに罹患したとき、安心した環境で治療に専念したい人や、費用を理由に治療の選択肢を狭めたくないと思う人は、がん保険や医療保険に女性特約や先進医療特約を付加しておくことがおすすめです。
3. がん保険の必要性を判断する3つの視点
まず重要なのは、がんに罹患した場合の経済的負担に対応できるかです。治療が数年にわたって継続し、毎月一定額の医療費負担が発生する状況を想定してください。貯蓄を継続的に取り崩すことなく治療に専念できるか、また治療による収入減少にも対応できるかを検討する必要があります。
3.1 治療選択肢の拡大意向
標準的な保険診療だけでなく、先進医療や自由診療も視野に入れたい場合は、がん保険による備えが重要です。これらの治療法は公的医療保険が適用されないため、数百万円の費用がかかることもあり、保険なしでは現実的な選択肢とはなりません。
3.2 治療環境への要求水準
個室での療養や、通院時の交通手段、日常生活の質(QOL)の維持など、治療環境にこだわりたい場合も保険の必要性が高まります。がん保険の診断一時金は使途が自由なため、これらの費用にも対応可能です。