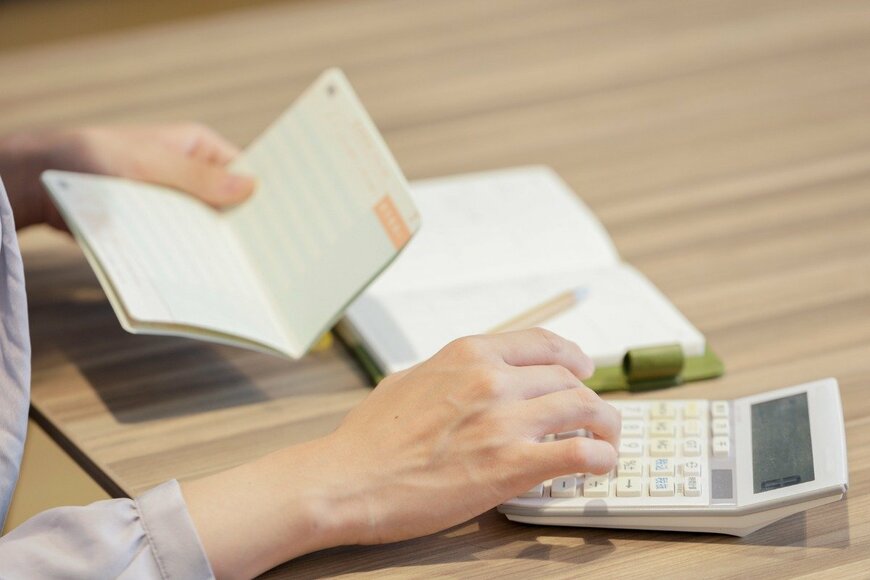昨年11月に閣議決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、住民税非課税世帯への給付金支給が、早い自治体では1月からスタートしています。
収入の減少などにより経済的に困難を抱える世帯には、このように家計を支援する各種減免制度や優遇措置が設けられています。住民税の非課税自体も、そのひとつです。
そこで今回は、住民税を支払っている世帯数を年代別に確認し、住民税非課税世帯がどの程度想定されるのか検証してみます。住民税非課税世帯になる要件や、3万円の給付についても紹介しますので、さっそくみていきましょう。
1. 住民税課税世帯の割合から見る「住民税非課税世帯」
住民税は、私たちが地域で暮らす上で役立てられている税金です。その地域に居住する人や企業などが税を負担することにより、ゴミ処理や水道、学校教育、福祉など、さまざまな行政サービスを受けることができます。
では、実際に住民税を納めている世帯はどれくらいあるのでしょうか。厚生労働省が2025年7月に公表した「令和5年 国民生活基礎調査」より、年代別の住民税課税世帯の割合を確認してみます。
30歳代:88.0%
40歳代:90.0%
50歳代:86.4%
60歳代:78.3%
70歳代:64.1%
80歳代:47.5%
住民税は、その年の1月1日時点で市町村に住所があり、一定の所得がある方に課税されます。したがって、30歳~50歳代は住民税課税世帯の割合が高く、各年代ともに9割程度となっています。
しかし、60歳代からその数は徐々に減少し始めます。80歳代にいたっては47.5%と半数以下となり、65歳以上では、住民税課税世帯の割合は61.9%、75歳以上では50.9%となっています。
つまり、現役世代においては各年代の10%ほどの世帯が、また65歳以上世帯にいたっては、4割から5割の方が住民税非課税世帯に該当している可能性があります。
リタイアしたあとの収入は、多くの場合、給与から年金に変わることになります。収入が減少する人も多く、このことが非課税世帯の割合が上昇する要因のひとつと考えられます。
また、年金は給与と比較して税控除が大きいのが特徴です。給与所得者と年金受給者が同じ収入を得たとしても、年金受給者のほうが所得が低くなり、住民税非課税世帯に該当しやすくなると予想されます。