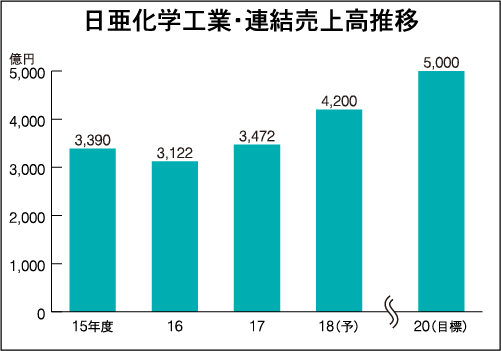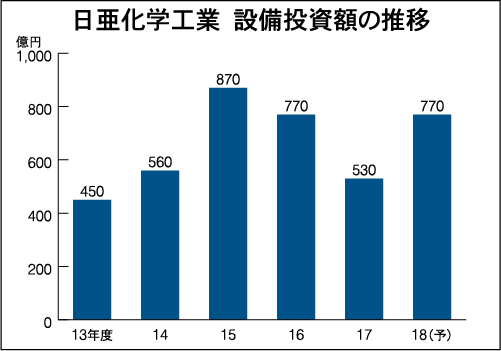本記事の3つのポイント
-
 メディアへの情報発信を行わないことで有名なLED大手の日亜化学工業が4月に事業説明会を開催、20年度に売上高5000億円を目指す中期計画を公表した
メディアへの情報発信を行わないことで有名なLED大手の日亜化学工業が4月に事業説明会を開催、20年度に売上高5000億円を目指す中期計画を公表した -
 主力のLEDでは「フルアクティブ液晶」向けの展開を強化する。また、半導体レーザーや電池材料も今後の伸びを期待。設備投資は770億円と高水準を維持する
主力のLEDでは「フルアクティブ液晶」向けの展開を強化する。また、半導体レーザーや電池材料も今後の伸びを期待。設備投資は770億円と高水準を維持する -
 小川社長は就任後、様々な社内改革を推進。広報部門の設置や生産改革などを行ってきたほか、今後は新事業の創出にも力を入れていく
小川社長は就任後、様々な社内改革を推進。広報部門の設置や生産改革などを行ってきたほか、今後は新事業の創出にも力を入れていく
4月23日、徳島県南東部の阿南市に位置する日亜化学工業本社で、代表取締役社長の小川裕義氏による報道関係者向けの事業説明会が行われた。日亜化学はこれまで積極的にメディアへの情報発信を行っておらず、非上場企業のためその内情や事業戦略の詳細は長らく秘密のベールに覆われていた。
同社がトップ自らによる事業戦略説明会を開催したことは非常に画期的な出来事であり、情報開示姿勢の大きな転換を意味する。筆者はこの席に招かれ、これまで明らかにされてこなかった日亜化学の実像についてトップが語る場面に居合わせる光栄に恵まれた。そこで本稿では、この説明会のレポートを通して、日亜化学の現況と未来像、競争が激化する市場においての生存戦略に迫りたい。
カルシウム塩、蛍光体からLEDへ
日亜化学は1993年に事業化した青色LEDで世界的に知られるが、社名のとおり化学品メーカーとしてスタートした。1956年に高純度カルシウム塩メーカーとして創業し、66年に照明やブラウン管用の蛍光体を事業化したことで化学品メーカーとして飛躍を遂げた。
93年の青色LEDの事業化後は、半導体レーザー(LD)とともに光半導体の世界トップメーカーとして高成長を続けており、96~2017年の21年間に従業員数は11倍、売上高は12倍に拡大した。事業部門は化学品関連を担当する第一部門と光半導体関連を担当する第二部門に大別でき、化学品は世界シェア11%(17年、日亜化学推定、以下同)を持つリチウムイオン電池(LiB)材料や蛍光体、LED用材料などがある。一方の光半導体は、世界シェア20%を持つ青色LED(高出力分野)と95%の寡占シェアを持つLD(高出力GaN系LD)を主力に、それらの応用製品も手がけている。
日亜化学は「地方発のグローバル企業」を謳い、世界中に直接販売網を敷いているにもかかわらず、主力の生産拠点は徳島県内に置いている。なかでも中核となっているのが本社工場と、阿南市東部の那賀川河口部に位置する辰巳工場。本社工場はLEDの前工程とLD、磁性材料を、辰巳工場はLEDパッケージ工程と電池材料、蛍光体などを手がける。徳島県北部の鳴門工場でもLEDパッケージ工程を行っているほか、交通表示機などLED応用製品を生産している。
15年に就任した小川裕義社長は創業者の故小川信雄氏の孫。就任後に進めている社内改革の一環として、17年7月に初めて「広報」の名を持つ部門を設立した。将来的な人材獲得のうえでも広報活動に力を入れるべきだとの声が社内からも上がっており、前向きな情報発信への方針転換はそうした要請を受けてのことという。小川社長が実施している改革については後ほど触れるとして、まずは直近の業績動向を紹介しよう。
18年度に21%の成長を目指す
18年度(18年1~12月)は、売上高を前年比21%増の4200億円と計画する。うち、光半導体事業は同9%増の3000億円、化学品事業は同67%増の1200億円。LEDを中心に海外メーカーとの競争激化が影響し、利益率では苦戦するが前年同等水準の利益を確保したい考えだ(17年度経常利益は658億円)。
光半導体事業のうち、プロジェクターを中心に採用が拡大しているLDは急成長を見込んでいる。LEDは車載用が堅調に伸びて、従来の日米に加えて中国、欧州向けの比率が高まる見通しだ。一方、競争が激化している照明用は横ばいを目指す。
スマートフォンの有機ELシフトにより落ち込んでいた液晶バックライト用は、再成長への転換を図っている。そのカギとなるのが、「フルアクティブ液晶」だ。フルアクティブ液晶は、ジャパンディスプレイ(JDI)が有機ELディスプレーへの対抗馬として投入した超狭額縁を特徴とする液晶パネル。有機ELパネルの生産が技術的な困難さから広がらないなか、米アップルは次期モデルのiPhoneにフルアクティブ液晶の採用を拡大するとの観測が取りざたされている。
この動きを受けて、中国メーカーのハイエンドスマホにおいてもフルアクティブ液晶の採用拡大が予想される。日亜化学はすでにこの動きに伴った需要拡大への対応を進めている。従来より体積を40%減らすとともに効率を12%増、寿命を倍増させたフルアクティブ液晶用LEDの新製品を投入し、生産能力を18年秋ごろまでに前年比8倍に引き上げる予定だ。日亜化学はフルアクティブ液晶用LEDを軸に液晶バックライト用を19年以降に再成長軌道に乗せると意気込んでおり、有機ELに押されて衰退するかに思われた液晶バックライト分野が再生できるのか注目される。
中期的に成長が見込めるLDは、20年に500億円の売り上げ目標を掲げている。プロジェクター用が75%を占め、6%が車載用、残りが光ディスクや産業用となる見込み。現在、本社工場敷地内に19年1月の竣工予定で新たなLD専用棟を建設している。地上8階建て延べ床面積約3万㎡の規模で、稼働後はここを拠点に生産を拡充する。
化学品事業は電池正極材を軸に拡大を目指す。向こう3~4年は車載需要が大幅に伸長すると予想しており、20年度には車載用の比率が72%にまで高まる見通し。ただ、先行きには不透明感があるためリスク管理が重要としている。
18年度は770億円の設備投資を計画
日亜化学は積極的な設備投資戦略を特徴とし、常に先行投資を続けることで競合他社との競争に勝ち抜いてきた。09~17年度の累計投資額は約6300億円にものぼる。光半導体、特にLEDの増産投資が中心だが、近年では需要が高まっている電池材料への投資も増やしている。
18年度の設備投資は770億円を計画しており、うち化学品事業に約90億円、光半導体事業に約680億円を投じる計画だ。ただ、日亜化学の投資は年度単位ではなくプロジェクト単位で決定されているため、実施時期により年度ごとの投資額には増減の可能性がある。18年度の具体的な投資内容としては、電池材料、LED、LDの能力拡充に加え、光半導体事業ではフリップチップ、レーザーリフトオフなどのプロセス革新やフルアクティブ液晶用LEDの拡大を進める。
「Top100 グローバル・イノベーター2017」に選出
積極的な生産拡大と高度な技術力とともに、日亜化学の強さの源泉となっているのが知財戦略である。積極的な知的財産権の行使により侵害行為を防ぐとともに、クロスライセンスやライセンス供与といった他社との協業においても戦略的な知財の活用を行っている。これらの取り組みが評価され、18年度の特許庁の「知財功労賞」において経済産業大臣表彰を受賞した。
また、米クラリベイトアナリティクスによる「Top100 グローバル・イノベーター2017」に選出され、事業説明会と同じ4月23日に表彰が行われた。クラリベイト社はトムソン・ロイターから16年にスピンアウトした企業で、知財情報の提供、分析による企業や大学、研究機関の活動支援を行っている。
「Top100 グローバル・イノベーター」はクラリベイト社が持つ特許データをもとに特許の数量、出願成功率、欧米・中・日市場を網羅するグローバル性、他社引用数の4つの評価軸により知財動向を分析し、知的財産権を駆使して独創的な発明を事業へと昇華させ、世界のビジネスをリードする企業・機関を選出するもの。17年は日本から39社が選出されており、トヨタ自動車やソニー、日立製作所、パナソニックなどの大企業の名が並ぶ。また、初受賞企業としてフェイスブック、鴻海、ウエスタンデジタルといった世界的なIT、エレクトロニクス企業が選ばれている。
受賞を受けて小川社長は「ニッチな製品を手がける当社が、世界的な企業と並んで選ばれたことはとても嬉しい。これからも自分たちの製品を守る特許を出願していくとともに、補完的な技術を持った企業との連携にも取り組みたい」とコメントした。また、日亜化学において知財戦略の陣頭指揮を執る法知本部長の芥川勝行氏は近年の特許の状況について「出願から20年経った白色LEDの基本特許は切れているが、その後の新たな特許出願やLEDの市場拡大によりマイナス影響はカバーできている」と話し、積極的な知財戦略が業績拡大を支えていることを改めて示した。
組織再編、生産改革、新製品創出を推進
さて、日亜化学の事業説明会に話を戻し、小川社長が進めている改革および将来展望について述べよう。先述のとおり、小川社長は就任後に将来のさらなる成長に向けた社内改革を進めており、広報活動の活発化もその一環である。事業活動における改革は、研究開発、生産活動、製品戦略に分けることができる。研究開発活動では、本社における組織再編を行うとともに、県外組織の増強を進めている。
本社では10年以上先を見据えた光・エネルギーに関する素材や技術を手がける研究開発本部と、光半導体の応用開発を手がける先行応用開発センターの2組織を立ち上げ、相互連携により次世代技術の開発を進めていく。県外開発拠点としては県外人材確保の観点から、横浜技術センター(横浜市神奈川区)、諏訪技術センター(長野県下諏訪町)の2拠点を置き、基礎研究、応用開発、LD開発を行っている。横浜では18年9月に新棟を起工する予定で、現在40名の人員を100名に拡大する。諏訪でも人員を増強し、現状の25、6名から50名体制に増やす。両拠点で合計150名体制を構築する計画だ。
生産活動では、中核工場における材料、製造装置からの一貫生産による強みをさらに向上させるとともに、生産性革新推進室を設けて現場力の強化を図っている。例えば、電池材料工場では従業員の目による管理の徹底を追究し、安全性向上およびクリーンな生産環境を実現し、コスト削減につなげている。光半導体工場では、自動化が進んでいるパッケージラインにおけるさらなるスマート化を追求し、より利益を生み出せる生産現場の実現に注力している。
なお、徳島県内に主力拠点を集中させるこれまでの戦略を変える考えはなく、海外拠点はあくまで補完的な位置づけにとどまる。研究開発やプロセス革新などの観点から、拠点が集中していることによる効率の良さを重要視しているためだ。小川社長は「現状の強みを活かせる限りは行けるところまで現状のままで行く。将来は分からないが、向こう10年ほどは現状を維持したまま海外メーカーと戦っていく」と話した。さらに、研究開発や生産活動を支える人事制度においても、自由闊達な気風をさらに発展させるための改革を行っている。
製品戦略では、現状の主力である青色LEDやLDに続く新たな製品創出を模索している。日亜化学は93年の青色LED事業化以降を「ステージ4」と位置づけているが、新領域の開拓こそが「ステージ5」の幕開けになるという。小川社長は「LED、LDはまだ十分に活用され尽くしていない」と話し、性能の向上や新たな用途の提案により新規事業の創出を目指していくという考えを示した。
例えば、顧客からはセンシングなどの光を用いたソリューションのニーズが高まっている。こういったニーズに対し、LDを用いた先進モジュールなどの提案が考えられ、開発を進めているという。光センシングの領域では赤外や赤色LEDの技術が必要になるが、日亜化学はそれらのエピウエハーは手がけているものの、LEDチップの内製は行っていない。このため、他社と協業してチップを調達し、自社モジュールに組み込むことを想定している。
なお、海外LEDメーカーの間では、LEDディスプレー用のマイクロLEDの研究開発が活発化している。この分野に関して小川社長は、「現状製品化しているのはソニーだけで、ハイエンドサイネージからスマホなどの汎用品に広がるにはかなり時間を要するだろう。ただ当社でも研究開発は行っている」とコメントした。
これらの取り組みを通じて、さらなる成長に向けた基盤作りを進めていく。20年度には連結売上高5000億円の目標を掲げており、その先の成長に向けても積極果敢な挑戦を続けていく方針だ。
盤石な事業構造と投資即断で強みを最大化、今後も先進技術で差別化へ
今回、日亜化学を訪れることで、光半導体市場におけるトップリーダーの地位を保持し続けてきた強さの源泉を目の当たりにすることができた。それは研究開発と製造、知財戦略を両輪とする攻守のバランスが取れた事業構造を基盤に、必要な投資を必要なタイミングで即断することで経営スピードを最速化する企業体制である。経営、現場や間接支援部門が理想的に連携することで、日亜化学という企業の強みが最大化されていると言える。
もう1つ、小川社長のコメントで印象に残ったのはLED市場に対する強い危機感である。小川社長は政府の資金援助を背景に、中国メーカーが猛烈な追い上げを見せていることを挙げ、価格や物量では太刀打ちできないと語る。対抗するには先進技術で差別化し続けるほかなく、それができなければ「韓国、台湾メーカー、(欧州トップの)オスラムともに生き残れない」という認識を示した。そのための武器になるのが特許であり、これまで同様に常に最先端の技術を生み出しながら知財という障壁を構築していくことこそが、最大の生存戦略である。
日亜化学は、その製品を利用したことがないという人がほぼいないくらいのポジションを持っているにもかかわらず、世間的な知名度は高いとは言えなかった。今回、情報開示姿勢の転換を明確にしたことで、LEDおよび電池材料のトップメーカーである日亜化学の実像が少しでも世間に広まれば、日本のデバイスメーカーの躍進を願う筆者としても喜ばしい。今後もぜひ定期的にこのような機会を設けてもらえることを願っている。
電子デバイス産業新聞 大阪支局 記者
中村 剛
まとめにかえて
日亜化学は非上場企業であるため、情報発信の頻度や取材にも応じる機会が少なく、メディアのあいだでもその存在はベールに包まれているところが多いです。その日亜化学がある意味で広報戦略において方針展開を図ってきたのは、LED市場が置かれている現状の一端を表しているともいえます。記事にもあるとおり、LED市場は中国勢の一挙参入によって価格競争が激化。同じ国内メーカーの豊田合成などはLED事業において赤字を余儀なくされています。強みとする特許戦略を駆使しながら、同社がLED市場をはじめとする自らのフィールドでどう生き残っていくのか、今後も注目していきたいところです。
電子デバイス産業新聞