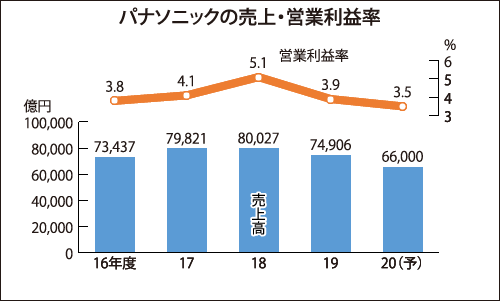本記事の3つのポイント
-
 パナソニックが新体制移行を発表。22年4月から持株会社制度に移行する
パナソニックが新体制移行を発表。22年4月から持株会社制度に移行する -
 ホールディングス傘下には「パナソニック」のほか、それと同格の事業会社が存在。デバイス、エナジー、現場プロセス事業に注力
ホールディングス傘下には「パナソニック」のほか、それと同格の事業会社が存在。デバイス、エナジー、現場プロセス事業に注力 -
 新たな事業領域である現場プロセス事業は製造や流通、物流など様々な現場向けに業務効率化や働き方改革といった経営課題を解決するソリューションを提供する「現場プロセスイノベーション」の実現を掲げる
新たな事業領域である現場プロセス事業は製造や流通、物流など様々な現場向けに業務効率化や働き方改革といった経営課題を解決するソリューションを提供する「現場プロセスイノベーション」の実現を掲げる
2020年11月、パナソニックが体制刷新を発表した。21年4月1日付で常務執行役員の楠見雄規氏が津賀一宏社長に代わってCEOに就任し(同年6月の株主総会を経て津賀氏が代表権のない会長に、楠見氏が代表取締役社長に就任)、22年4月には持株会社制度へ移行する。持株会社制度への移行という企業グループ全体の見直しは、2000年代初頭に中村邦夫社長(当時)が行った「中村改革」以来、約20年ぶりとなる。
再編により各事業がそれぞれの強みを最大限に発揮できる「専鋭化(専門と先鋭を組み合わせた造語)」を図り、経営課題であった低収益体質からの脱却を図る。組織再編において電池関連事業、電子部品・材料事業、製造や物流など各種現場向けソリューション事業は柱事業と位置づけられており、従来の社内カンパニーの制約にとらわれない権限を持つことで意思決定の迅速化、各事業に合った制度設計などを推進する。パナソニックは長年の業績停滞に終止符を打ち、成長路線に向かうことができるのだろうか。
長期停滞に苦しむパナソニック
体制刷新の詳細に立ち入る前に、近年のパナソニックの歩みを振り返ろう。2000~06年まで社長を務めた中村邦夫氏の下で、松下電器産業(当時、08年に社名変更)は大規模な改革を実行する。これは社内において事業間の重複を解消して開発、製造、販売を一本化し、グループでは兄弟会社の松下電工に代表される高い独立性を持った子会社、関連会社を完全に傘下に組み込むものであった。組織改革と薄型テレビやブルーレイ、デジタルカメラなどのデジタル家電に注力したことが奏功し、04年度以降の松下電器産業の業績は右肩上がりとなる。
しかし、社長が大坪文雄氏に代わって以降、08年のリーマンショックや11年の東日本大震災といった経済危機や注力していたデジタル家電市場の縮小により、業績は大打撃を受ける。12年に社長に就任した津賀氏はこの危機的状況のもとで、赤字事業であったプラズマパネルの生産終息をはじめとした構造改革を断行した。
津賀氏は家電をはじめとするBtoC中心のビジネスモデルからBtoBの拡大を掲げ、米テスラ・モーターズとパートナーシップを組んだ車載電池などの新たな事業創出に取り組んだものの、業績は停滞に苦しんだ。売上高は18年度にギリギリ8兆円に届いたが、それ以外は7兆円台、営業利益率は3~5%台を推移し、伸び悩みが続いている。
16~18年度には車載事業を軸に高成長を目指したものの、投資負担の増大で低収益に陥り、成長軌道に転じる機会を逸した。19年度以降は再び収益基盤の再構築を優先させる構造改革フェーズに追い込まれ、米中貿易摩擦と新型コロナウイルス感染拡大の影響もあって、業績は落ち込んでいる。
持株会社制では柱事業が「パナソニック」と同格に
では、この停滞を打破するための施策である持株会社制度への移行で、パナソニックはどう変わるのだろうか。まずグループ全体を統括して全社的な立場から事業戦略を策定するとともに、各事業会社の活動を支援して成長を促す持株会社、パナソニックホールディングス(HD)を置く。また、各事業部門に共通する間接機能を統合し、高効率、高付加価値化を図る専門会社である「プロフェッショナルサービス」が、HDとともに各事業会社を支える。
事業会社のうち、「パナソニック」の社名を引き継ぐ新事業会社は家電や空調、電設などの事業を担い、基幹事業の1つである空間ソリューションと家電や住空間とのシナジーを図る。また、同じく基幹事業である現場プロセスおよびデバイス事業は、それぞれを専門とする事業会社とする。
テスラやトヨタ自動車との協業で事業の方向性が定まってきた車載電池事業は、非車載電池を加えたエナジー事業として事業会社とする。新パナソニックと現場プロセス、デバイス、エナジーの4事業会社は、今後のグループ全体の成長を担う柱に位置づけられる。それ以外の車載機器や住宅システム、AV機器事業についても事業会社として独立させる。
体制刷新のポイントは、4つの柱事業がHD傘下の同格事業会社とされていることだろう。プロフェッショナルサービスにより間接機能の重複を防ぐ一方で、各事業会社にはそれぞれの事業環境に適した人事制度など柔軟な各種制度導入権限を持たせ、各市場において最大限に競争力を発揮できる体制を実現すると謳っている。
AI・5G活用の取り組みを開始した現場プロセス事業
柱事業のうちデバイスとエナジーは、すでに方向性や強みがある程度確立されている。デバイスは、現在のインダストリアルソリューションズ(IS)社で展開するコンデンサーやモーター、電子材料などで構成される。コロナ禍においてもリモート投資需要の活発化で業績が堅調で、自動車の電動化や工場自動化など今後の成長を目指すうえで注力する領域も鮮明である。エナジーも円筒形車載電池はテスラと、角形車載電池はトヨタと協業することで方針が明確となっており、それぞれの強みをどう継続的に発展させるかが焦点だ。
一方、現場プロセス事業は、社内分社のコネクティッドソリューションズ(CNS)社が主導する新たな事業領域だ。CNS社はパナソニックグループにおけるBtoBソリューション事業の中核を担う組織として、17年に発足した。製造や流通、物流など様々な現場向けに業務効率化や働き方改革といった経営課題を解決するソリューションを提供する「現場プロセスイノベーション」の実現を掲げている。
同社社長の樋口泰行氏は、松下電器産業から米ハーバード大学のMBAを経てヒューレット・パッカードやマイクロソフトの日本法人社長を歴任し、ダイエーの経営再建にも携わった経歴を持つ。17年にパナソニックに戻って新設されたCNS社社長に就任するや、カンパニー本社を大阪から東京に移転するとともに「大企業病」から脱するためのカルチャー&マインド改革を推進し、ハードとソフトを組み合わせたソリューションビジネスの拡大を図っている。樋口氏の主導の下、CNS社はパナソニックグループにおいて変革を先導する事業部門として存在感を高めている。
AIや5Gを活用した新規ビジネスの創出にも積極的だ。20年7月にAI顔認証技術やセキュリティーカメラなどのエッジデバイス、音声などの各種センサーを組み合わせたセンシングソリューション事業の立ち上げを発表し、同年12月には顔認証プラットフォームを幅広いパートナー企業に提供して協業を加速するパートナープログラムを開始した。
また、21年2月にはプライベートLTEやローカル5Gを用いたネットワークシステムを様々な現場に提供するマルチネットワークサービスの提供を同4月から開始するとアナウンスした。ローカル5Gの提供は22年4月からの予定だが、先行して自社拠点内での実証を行っている。5Gの活用により、高精細画像を用いた遠隔監視や遅延のないロボットの遠隔制御などの実現が期待できる。
「専鋭化」に不可欠な「格差」の是正
体制刷新により各事業が「専鋭化」し、グループ全体を成長路線に押し上げることはできるだろうか。筆者は持株会社制度への移行により、中核事業会社である新パナソニックと、各事業会社が真の意味で同格となり、「格差」が是正されることが必須であると考えている。
どういうことか。「中村改革」以前の松下グループは、「松下連邦」と称される体制を敷いていた。兄弟会社である松下電工に代表されるグループ会社は自主的に経営され、親会社である松下電器も関与することはできなかった。また、松下電器内においても各事業部は高い自立性を持っていた。そのため事業部、グループ会社同士で機能が重複し、相互に足を引っ張り合う関係となっていた。
これらの弊害を解消するため、中村改革ではグループ本社が各事業部門、子会社を中央集権的に統括する体制へと再編された。この方向性は後任である大坪、津賀社長時代にも踏襲され、09年に子会社となった三洋電機やパナソニック電工(08年に松下電工から社名変更)などのグループ会社の完全子会社化、吸収合併が進められた。
この措置はグループの経営効率化と収益性改善をもたらし、改革後の業績向上に寄与した。中村改革が成功事例として大きく称揚されたゆえんである。しかし、中央集権化においてはリーマンショック後の市場環境変化への対応が急務だったという事情があったにせよ、当初は独立子会社として存続予定としていた三洋電機を実質的に合併(法人格は残存)し、家電部門を中国ハイアールに売却するなど強硬な措置を伴った。
四国において独自にホームビデオやディスクドライブを発売するなど独自性を誇った松下寿電子工業は、10年にヘルスケア事業に特化した子会社として再編された後、14年に米KKRが株式の80%を取得し、グループから離脱した。パナソニック電工などのグループ会社も吸収合併を経て事業再編を行い、往時の自立性は失われた。
結果として、家電部門をはじめとしたパナソニック中核部門とそれ以外の部門ではグループ内における格差が生じた。津賀社長が就任直後に断行したプラズマディスプレー事業の終息以降も、半導体や液晶パネル、太陽電池などの事業が段階的に縮小し、売却・終息に至っている。
これらの事業はいずれも単独で収益化できなかったことが終息に追いやられた主要因ではあるが、半導体や液晶はもともと社内のデジタル家電向けのボリュームが大きく、この領域に代わる収益源を獲得できなかったことが衰退につながった。終息に至るまでの間、黒字転換が課題として掲げられていたものの、グループとしてのテコ入れ策が十分に為されたかどうかは疑問符が付く。トップの津賀氏自らが後押しし、テスラとの協業で拡大した車載電池事業が柱事業の1つに成長したのと比べれば明暗は明らかだろう。
太陽電池のように市場環境から鑑みて存続に固執するのは非現実的なケースもあり、苦境に陥った事業を例外なく全社的に救済すべきであると主張するつもりはない。しかし、電子部品や基板材料、車載電池のように、現状では市場におけるプレゼンスを確保していても厳しい競争環境が予想される事業、現場プロセス事業のようにこれからの立ち上がりが重要な事業が柱事業となっている以上、HDには中核の新パナソニックに偏らないリソース配分が求められる。
パナソニックは歴代社長をAV機器事業部門から輩出しており、新社長の楠見氏も津賀氏の部下としてブルーレイディスクシステムの開発などに従事した経験を持つ。津賀氏はHD社長が新パナソニック社長を兼務することはないと明言しており、楠見氏の出自がイコール新パナソニックの偏重を意味するわけではない。
しかし、新パナソニックは家電のほか空調、電設、食品流通事業と中国・北東アジアへの販売機能を傘下に置くグループ最大の事業会社となる。それだけに新パナソニックが本家本元であり、HDも重視するだろう、と内外から目される状況であることは否めないだろう。HDはその先入観を良い意味で裏切り、新パナソニックに偏らないリソース配分、各事業部門に適した体制整備などのバランスの取れたグループ経営を進めてほしい。現CNS社で先行する意識変革などの取り組みを、グループ全体に取り入れるといった取り組みにも期待したい。
問われる「元主力事業」の位置づけ
最後に、体制刷新後のパナソニックグループ経営において1つ気になる点を指摘しておきたい。それは車載機器事業の扱いについてである。新体制において車載機器事業は、AV機器や住宅システム事業とともに、柱事業ではない事業会社として位置づけられている。
前述のとおり、パナソニックは16~18年度の中期経営計画で車載機器、電池を高成長事業と位置づけ、リソースを集中するとともに売り上げ、利益両方の成長を目指していた。しかし、車載機器は開発負担の大幅な増加、電池はテスラ向け需要の急増への対応に難航したことで収益性が悪化し、全社の利益を押し下げる結果となった。そのため、19年度以降は再挑戦事業に位置づけられ、事業の立て直しを図った。
以降、車載電池はテスラ向けの円筒形に黒字化の見通しが立ち、角形はトヨタとの合弁事業化で安定成長に向けた道筋をつけた。一方の車載機器もマネジメントの強化で開発リソースを最適化し、収益の足を引っ張っていた開発負担の抑制を進めた。なお、車載機器事業の立て直しを担当したのは新社長の楠見氏である。
こうした経緯がありながら、新体制で柱事業の1つとされた車載電池とそうでない車載機器事業とでは明暗が分かれた。楠見新社長は体制刷新の説明会において「収益性、競争力のない事業はポートフォリオから外すことも考える」とコメントしている。
前中計で主力に位置づけられながら挫折し、再構築を余儀なくされた点では同じでありながら、車載機器事業が電池と異なる扱いとされたのはなぜなのか。いくら主力として期待されていても、いつ何時リストラ対象に転落するのか分からないとなれば、新体制で柱事業に従事する社内外の関係者の士気にも影響しよう。車載機器事業への将来成長期待は薄れたのか、だとしたらそれはなぜなのか。新体制を滞りなく軌道に乗せるうえでも、車載機器事業にははっきりした総括が必要ではないだろうか。
電子デバイス産業新聞 大阪支局 記者 中村 剛
まとめにかえて
パナソニックが新たな体制でスタートを切ります。パナソニックは、いわゆる総合家電メーカーのなかでもBtoB分野への傾注を掲げて事業を展開してきました。しかし、テスラ向けの電池事業の収益化で苦しんだり、車載機器事業でも思ったような成果を上げられていませんでした。今回の社長交代と組織体制の見直しでどう変貌を遂げるのか。今後の同社の動きに注目が集まります。
電子デバイス産業新聞