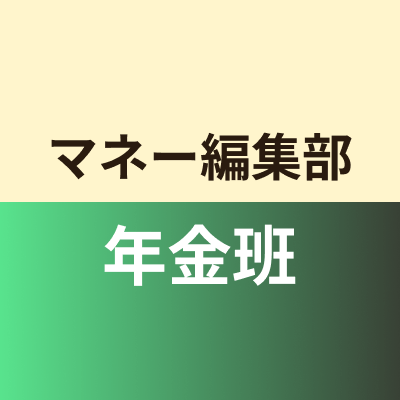4.2 国民年金・厚生年金どちらもOK《最大84%増額》繰下げ受給
繰下げ受給は、老齢年金を遅く受け取り始める代わりに、遅らせた月数に応じて受給額が増える制度です。66歳以降75歳までの間で、1カ月単位で繰り下げることが可能です。
繰下げ受給の増額率=65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数×0.7%(最大84%)
- (例1)1年間繰り下げた場合・・・0.7%×12カ月=8.4%増
- (例2)70歳まで繰り下げた場合・・・0.7%×60カ月=42%増
- (例3)75歳まで繰り下げた場合…0.7%×120カ月=84%増
老齢基礎年金・老齢厚生年金どちらか一方のみ繰下げすることも可能です。また、増額率は生涯続きます。
繰下げ受給のメリットは、受給額が増えること。ただし、繰下げ待機中の資金繰りや健康状態を考慮しながら、慎重な判断が必要となるでしょう。
また、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する点には注意が必要です。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
5. まとめにかえて
家計調査や物価高騰の実感から見えてきたのは、現在の老後生活費と年金収入の間に生じる大きなギャップです。この厳しい現実の中、公的年金を月額20万円以上受け取っている厚生年金受給者はわずか16.3%にすぎません。
すなわち、大多数の人が、現役時代より大幅に減る収入で、日々値上がりする生活費に対応しなければならない状況にあるのです。
また、物価高騰に対抗するため、年金暮らしの基盤となる「資産の目減りを防ぐ」貯蓄や資産形成は不可欠です。同時に年金額そのものを増やす仕組みを現役時代から検討することも、最大の防御策の一つとなり得るでしょう。
具体的には、国民年金の付加年金制度や、将来の受給額を最大84%増やせる繰下げ受給といった公的制度の活用は特に有効です。さらに、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用した資産形成も視野に入れてみると良いですね。
大切なのは、健康寿命と資産の寿命を同時に延ばす準備を「今」から始めることです。
参考資料
- プラネット「FromプラネットVol.238 <値上げと生活防衛に関する意識調査>」〜95%が「物価上昇を感じる」なか、消費行動の変容を探る~(PR TIMES)
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
マネー編集部年金班