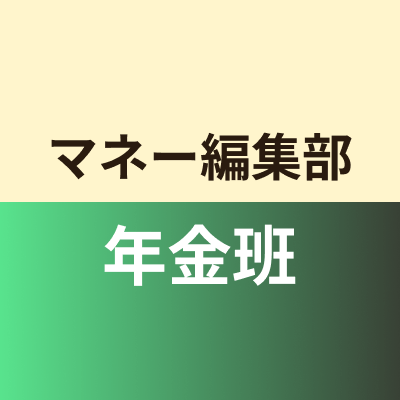4. シニア世帯の6割が「年金以外を頼る」老後資金のリアル
シニア世帯の収入構造については、厚生労働省公表の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」で確認ができます。
同調査では高齢者世帯(※)の年間収入を平均した際、最も大きな比重を占めているのは「公的年金・恩給」で、その割合は63.5%です。これに続くのが、仕事を通じて得る「稼働所得」の25.3%、そして利子や配当など「財産所得」の4.6%です。
これらの数字からも、やはり公的年金はシニア世代の生活資金のメイン財源であると言えるでしょう。
一方で、公的年金のみで生活費の全額を賄えている世帯は、全体の43.4%に留まるのが現状です。シニアの年金世帯の約6割が、公的年金に依存するだけでは不足し、他の収入源を必要としている現状を浮き彫りにしています。
※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯
4.1 【総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成】
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
5. 平均額だけでは見えない格差と「年金+α」の必要性
老後の年金受給額には大きな個人差があり、「月10万円未満」の低年金層が「月20万円以上」の高年金層を上回るという実態が浮き彫りになりました。平均額だけでは見えない、シニア世代の中での経済的な格差が明らかになっています。
さらに、物価高が続く現状では、年金だけで生活費を賄えている世帯は多数派とは言い難いでしょう。加えて、公的年金制度は将来にわたって現在の形を維持し続けるとは限りません。現役世代は「年金だけでは不十分」という現実を直視し、自助努力による備えが不可欠となります。
リタイア後の年金は2ヶ月に一度の支給となり、現役時代とは家計管理のペースも変わります。貯蓄や資産運用、長く働き続ける準備と合わせ、お金の使い方や管理の仕方についても、早い段階から意識を変えていくことが、安心できる老後を築く鍵となるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
マネー編集部年金班