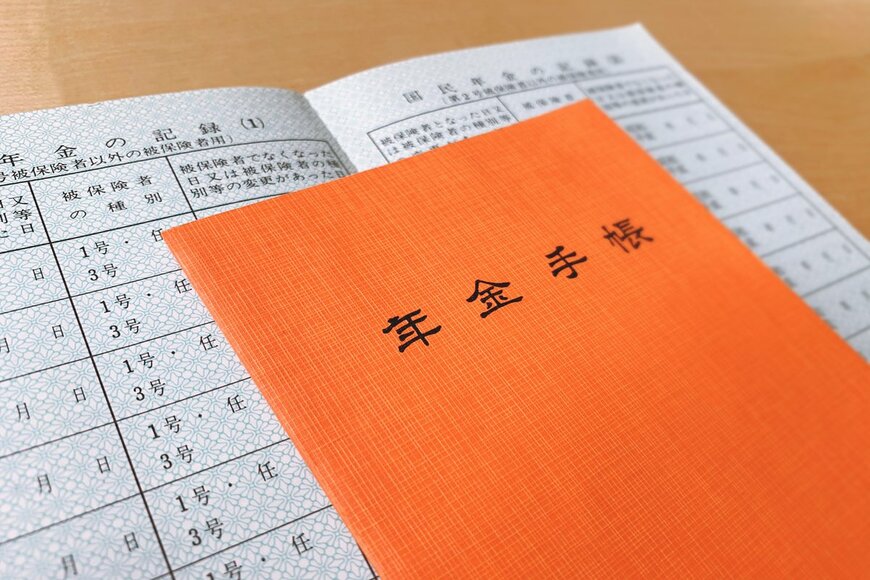2か月に1回振り込まれる公的年金ですが、「年金額は同じなのに、受け取る金額が変わった気がする…」と感じたことはありませんか。
年金から天引きされる住民税や社会保険料などは、年度の途中で金額が変わる仕組みになっています。10月に受け取る年金額にはその変更が反映されるので、実際に年金額が変わる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、厚生年金や国民年金の手取り額が変わる仕組みについて解説します。記事の後半では、シニアが受け取る平均年金月額についてもお伝えしますので、さっそくみていきましょう。
1. 10月分の年金手取り額、変化があるのはどんな人?
公的年金では、所得税や住民税、健康保険料、介護保険料は、天引き(特別徴収)が一般的(※)です。この天引き額は年間を通して同じではなく、年度途中で切り替わる点が大きな特徴です。※特別徴収には一定の条件があります。
特に影響が大きいのが、住民税の「仮徴収」から「本徴収」への変更が行われる10月です。
住民税は毎年6月に税額が確定しますが、確定前の新年度前半(4・6・8月支給分の年金)では、前年の税額をもとに暫定的に徴収されます。これが「仮徴収」であり、前年度の年税額の半額を3回に分けて徴収する仕組みです。
一方、税額が確定する10月以降は「本徴収」となり、本来支払うべき住民税額から既に仮徴収した額を差し引き、その残額を10・12・2月で3回に分けて天引きします。
このため、8月までの天引き額と比べて、10月以降は金額が変わることが一般的で、結果として年金の手取り額も増減します。
特に注意が必要なのは、前年度の所得に大きな変動があった場合です。
不動産売却や退職金の受け取り、パート収入の増加などで所得が増えていた場合、税額が上がり、10月以降の天引きが増えて手取りが減る可能性があります。逆に所得が減っていれば天引きが減り、手取りが増えることもあります。
自身の所得状況によって手取り額が変わる仕組みを知り、10月の変化に備えておくことが安心につながります。