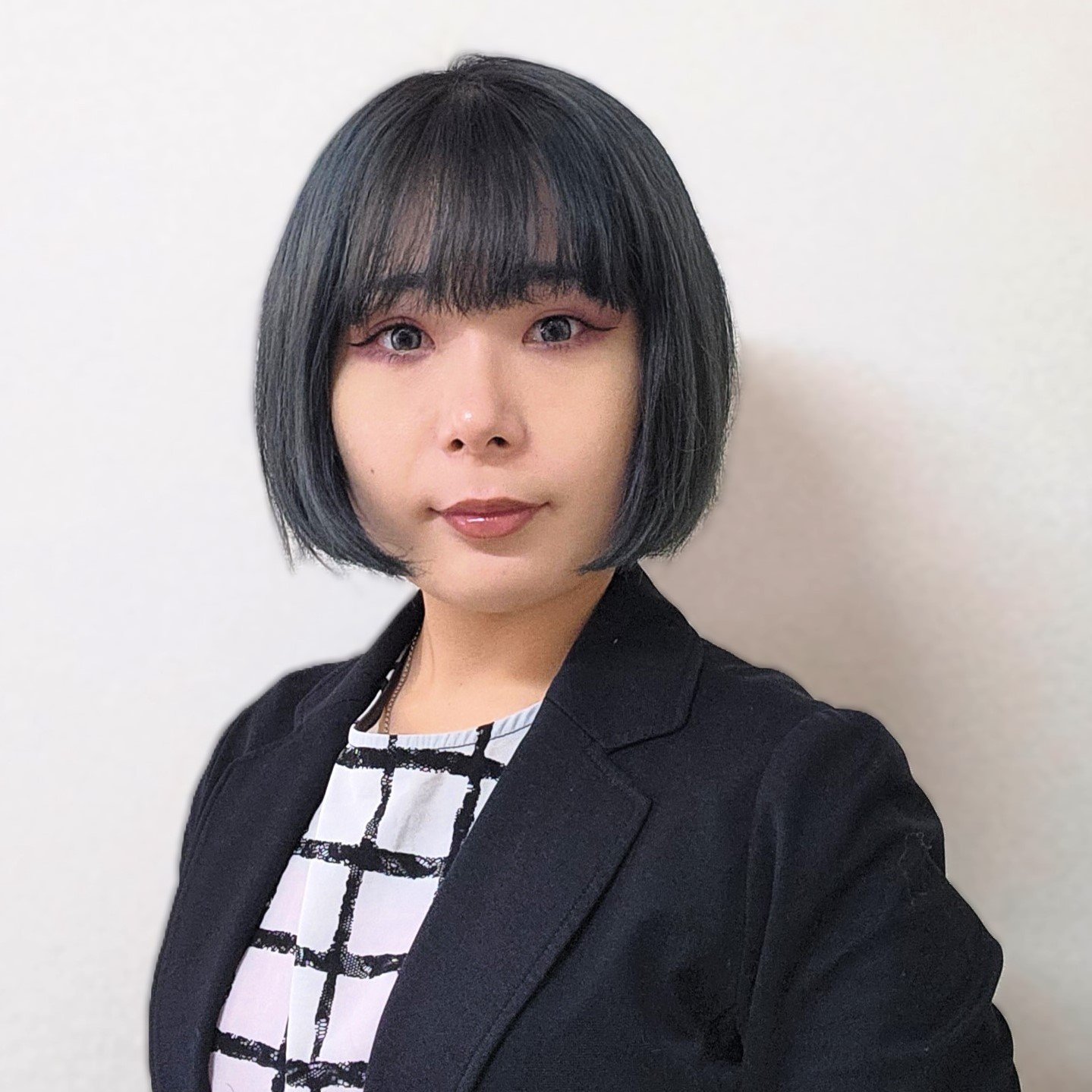5. 今のシニア世代の所得構成、「収入の約6割が年金、約2割が勤労によるもの」
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の収入の実態を見ていきましょう。
まず、高齢者世帯全体の平均的な所得構成を見ると、収入の63.5%を「公的年金・恩給」が占めており、次いで仕事による収入である「稼働所得」が25.3%、「財産所得」が4.6%となっています。
しかし、これはあくまで全体の平均値です。
「公的年金・恩給を受給している世帯」に絞ると、収入のすべてが「公的年金・恩給」である世帯が43.4%にものぼることがわかっています。
※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯
5.1 【総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成】
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
このようにシニア全体で見れば稼働所得なども一定の割合を占めていますが、年金受給世帯に絞ると、その半数近くが公的年金収入のみに頼って生活しているという実態が浮き彫りとなっています。
6. 年金生活者支援給付金、適切な支援が受けられるように情報を確認
今回は、年金生活者支援給付金について解説しました。老齢年金の受給額は、物価上昇を加味して毎年1回改定されています。しかし、実際の物価上昇率に追いつく上げ幅ではないため、実質の手取額は目減りしていることになります。
年金だけで生活費をまかなうことは難しく、貯蓄を取り崩したり、65歳以降も働いて家計を支えている人も珍しくありません。収入が一定以下の年金受給世帯には、「年金生活者支援給付金」が給付されます。いま一度、ご自身が対象世帯になっていないか確認しておくとよいでしょう。
対象者には申請書が届きますが、手続きをしないと給付金は振り込まれないため、うっかり忘れてしまうことがないよう注意してください。その他にも、政府や自治体が実施している所得の少ない方に向けた支援策がいくつかあります。最新の情報はお住まいの自治体のホームページか、役所の相談窓口で確認してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
橋本 優理