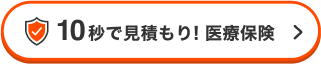3. 受給条件の詳細解説
ここからは、遺族年金を受給する条件について詳しく解説します。
3.1 亡くなった方の要件
遺族年金の支給には、亡くなった方が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 国民年金または厚生年金の被保険者期間中の死亡
- 老齢年金の受給権者または受給資格期間を満たした方の死亡
- 障害厚生年金1級・2級の受給権者の死亡
また、保険料納付要件として、死亡月の前々月までの公的年金の加入期間のうち3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されていることが必要です。
3.2 遺族側の受給要件
配偶者の場合、生計維持要件が重要な判定基準となります。具体的には、亡くなった方の死亡当時、前年の年収が850万円未満であることが目安とされています。
子どもについては、18歳到達年度末までまたは20歳未満で一定の障害状態にあることが条件です。
事実婚の場合でも、法律婚と同様の事情が認められれば受給対象となりますが、同居実態や生計同一関係を証明する書類の提出が必要です。
3.3 受給停止となるケース
遺族年金の受給権は永続的なものではなく、特定の状況で停止または失権します。再婚(事実婚を含む)、子どもが年齢要件を満たさなくなった場合、受給権者の死亡などが主な失権事由です。
また、年収が850万円以上となった場合なども支給停止の対象となる可能性があります。
3.4 申請手続きの実務
遺族年金を受け取るためには、ご自身で手続きを行う必要があります。いざというときのために、手続きの流れを把握しておきましょう。
3.5 申請窓口と相談先
国民年金のみの場合は市区町村役場、厚生年金加入歴がある場合は年金事務所または街角の年金相談センターが申請窓口となります。
共済年金独自の制度についてはそれぞれの共済組合への相談が必要です。
申請前の相談は電話でも可能で、必要書類や手続きの詳細について事前確認することをおすすめします。
3.6 必要書類の準備
年金請求書、死亡診断書の写し、戸籍謄本、住民票の写し、所得証明書、金融機関の通帳など多数の書類が必要となります。
子どもがいる場合は在学証明書、障害状態の場合は医師の診断書、事実婚の場合は申立書なども追加で必要です。
書類不備により手続きが遅延することを避けるため、事前に年金事務所で必要書類の確認を行うことが重要です。
3.7 申請から受給開始までの流れ
申請から受給開始までは通常1〜2カ月程度の期間を要します。
書類提出後、日本年金機構での審査を経て年金証書が送付され、その後年金支給が開始されます。
年金の支払いは請求月の翌月分からとなり、原則として偶数月の15日に振り込まれます。
4. 他制度との関係と注意点
遺族年金を受け取る上で、税金との関係や、他の公的制度との兼ね合いが気になる人も多いでしょう。また、知っておくべき注意点も確認しておきましょう。
4.1 税制上の取扱い
遺族年金は所得税・住民税ともに非課税所得として扱われます。
ただし、遺族年金以外の所得(給与所得、事業所得など)については通常通り課税対象となるため注意が必要です。
年末調整や確定申告の際は、遺族年金を収入に含めないよう注意しましょう。
4.2 他制度との併給関係
労働災害による死亡の場合、労災保険からの遺族補償等年金と遺族年金の両方を受給できる可能性があります。
自身の老齢年金との関係では、65歳以降は遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金の選択または調整されての受給となります。