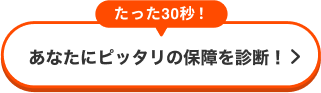5.4 世帯主が65歳以上の無職世帯の貯蓄の種類別貯蓄現在高の推移(二人以上の世帯)
ここからは、世帯主が65歳以上の「無職世帯」に絞って、貯蓄額とその内訳の推移を見ていきましょう。
【65歳以上の無職夫婦世帯】平均貯蓄額の推移
- 2019年:2218万円
- 2020年:2292万円
- 2021年:2342万円
- 2022年:2359万円
- 2023年:2504万円
- 2024年:2560万円
65歳以上の無職二人以上世帯の貯蓄額は、近年増加傾向にあります。2020年までは2200万円台でしたが、2021年に2300万円を超え、2023年以降は2500万円台をキープしています。
2024年の貯蓄内訳のうち、最も割合が大きいのは定期性預貯金859万円(33.6%)です。そして普通預金などの通貨性預貯金が801万円(31.3%)、有価証券(株式や投資信託など)が501万円(19.6%)となっています。
低リスクの預貯金が貯蓄全体の約6割を占める一方で、前年からの増え幅を見ると、通貨性預貯金は+47万円(6.2%増)、有価証券は+21万円(4.4%増)となっています。
預貯金だけでなく資産運用への関心が高まっている様子もうかがえます。
このデータからも分かるように、老後資金は預貯金だけでなく、運用資産もバランス良く持つことが大切です。
資産を持つことで、急な出費にも備えることが可能です。急な出費として挙げられるものはやはり医療費でしょう。50代の今から医療費に備えるのはもう遅いのではないかと思う人もいるかもしれません。
次の項目では、50代ができる医療保険の見直しについて見ていきます。
6. 急な出費が怖い50代だからこそ選びたい保険とは
「若い頃に加入したままの保険をそのまま続けていいのか…」あるいは「更新を機に保険を見直すべきか」と悩んでいる方も少なくないでしょう。
50代以降は、子どもの独立や定年退職といったライフイベントが重なる時期です。ライフスタイルが変われば、必要な保障内容も変化していきます。だからこそ、今の自分に合った保障を持てているかを確認することが欠かせません。
また、保険商品は医療や治療の進歩に合わせて新しいものが登場しています。古い契約のままだと、いざという時に十分な給付が受けられないケースもあります。定期的にチェックし、少なくとも数年に一度は見直しの機会を持つことをおすすめします。
ただし、健康状態によっては新しい保険に加入できない場合もあるため、まずは自分が加入できる状況かどうかを確認することが第一歩です。そのうえで、必要な保障を改めて整えていけば、今後の生活により安心を加えることができるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」
- 厚生労働省「生涯現役支援窓口事業」
- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果の概要-(二人以上の世帯)」
中川 由佳