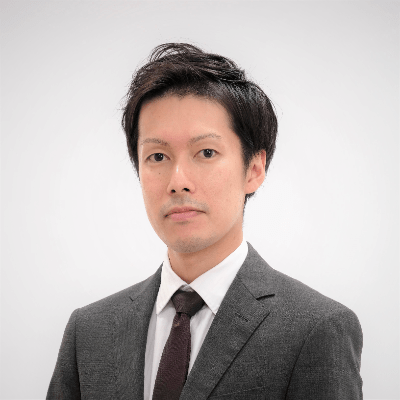4. 老後資金は「3つの口座」で目的別に管理するのがおすすめ
老後生活では、収入の大半が年金などの固定額に限られる一方、支出は生活費・娯楽費・医療費など性質が異なるものが混在します。
1つの口座で全てを管理すると、想定外の出費が生活費を圧迫し、資金計画が崩れるリスクが高まります。
そこで、用途別に3口座に分けることで、資金の見える化と計画的な取り崩しが可能になります。
4.1 1. 生活費口座
【用途】
家賃・食費・光熱費・通信費など、毎月発生する固定支出の決済
【ポイント】
- 年金の振込先をこの口座に設定する
- クレジットカードや公共料金の引き落とし先も統一する
- 毎月の予算を明確にし、残高が予算以上になった分は他の口座へ移す
【メリット】
生活費が不足する事態を防ぎ、家計の安定を保てる
4.2 2. 娯楽費口座
【用途】
旅行・趣味・孫への贈り物・交際費など、生活必需品以外の支出
【ポイント】
- 日常的には使わないため、利息の高いネット銀行や定期預金を活用する
- 年1〜2回、旅行や大きなイベントの前に必要額を移す
- 毎月の生活費口座から一定額を振り替える
【メリット】
「楽しみのための資金」と明確化することで、娯楽費の使い過ぎ防止につながる
4.3 3. 医療・介護費口座(将来に備える緊急・長期支出)
【用途】
手術費用・介護サービス利用料・高額療養費制度の自己負担分
【ポイント】
- 原則として引き出さず、医療や介護の支出が発生した時だけ使用する
- 目安として、最低でも100万円〜200万円を確保する(介護が長期化すると月10万円以上かかるケースも)
- 高額療養費制度や介護保険の自己負担割合を把握し、必要額を逆算する
【メリット】
突発的な高額支出でも生活費や娯楽費を切り崩さずに対応できる
5. 老後資金は「最新の生活実態」に合わせた管理をするよう心がけましょう
老後資金を3つの口座に分けて管理する際は、残高の見える化と資金移動を組み合わせることで、日々の管理負担を減らしつつ計画的な運用が可能になります。
長期にわたり保有する医療・介護費口座は、普通預金に置きっぱなしにするのではなく、たとえば短期国債や定期預金、個人向け国債(変動金利型)などインフレ対策を考慮した選択肢を検討するのも1つです。
また、生活環境や支出状況は年々変化するため、年1回を目安に配分や金額を見直し、最新の生活実態に合わせた管理を心がけましょう。
参考資料
加藤 聖人