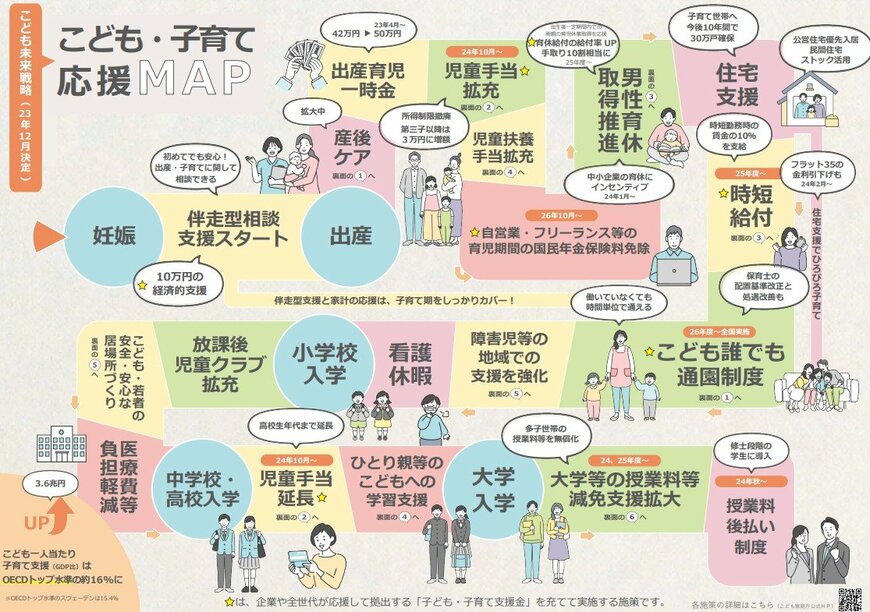2026年4月から、新たな制度として「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
この制度の最大の特徴は、医療保険に加入しているすべての人が支援金を負担するという点にあります。
75歳以上の後期高齢者も対象であり、現役世代だけでなく、年金生活者にも新たな経済的負担が課される仕組みです。
「支援金」という名称ではありますが、実際には医療保険料に上乗せされて徴収されるため、実質的には新たな社会保険料として認識すべき制度です。
月額の負担額はおおむね数百円と見込まれていますが、年収や加入している保険制度(協会けんぽ、共済、国保、後期高齢者医療制度など)により異なります。
特に低所得の高齢者については、一定の軽減措置が講じられる一方で、今後数年にわたり負担額が段階的に増えていく見通しです。
本記事では、この「子ども・子育て支援金制度」の概要、世代別の負担の違い、そして後期高齢者の家計に与える影響について、わかりやすく解説していきます。
将来の生活設計にも関わる重要な制度ですので、ぜひ最後までご確認ください。
1. 2026年4月から徴収開始の「子ども・子育て支援金制度」とは?
「子ども・子育て支援金制度」は、2026年4月から導入される新たな財源制度で、子育て支援を社会全体で支えるという考え方のもと設計されています。
この制度では、医療保険制度を通じてすべての加入者から一定額の「支援金」を徴収し、それを少子化対策の財源として活用します。
従来のように国の一般財源(税金)でまかなうのではなく、医療保険料に上乗せする形で徴収される点が大きな特徴です。
表向きの名称は「支援金」ですが、実質的には保険料の引き上げにあたるため、「実質的な増税」や「隠れた社会保険料の引き上げ」といった指摘もあります。
負担の形が見えにくいため、制度の内容を正しく理解しておくことが重要です。