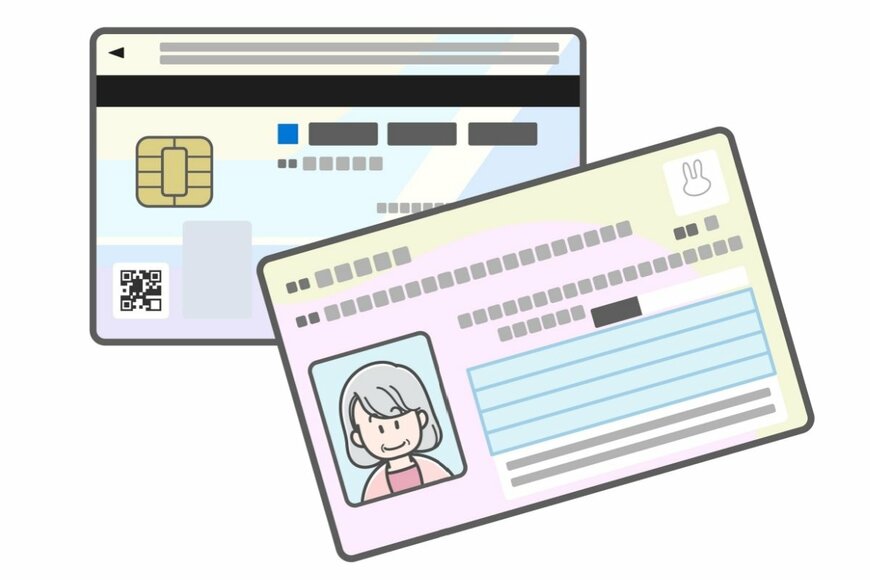2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されず、「マイナ保険証」が基本となる仕組みに移行しました。
このマイナ保険証を利用することで、ご自身の受診履歴や支払った医療費を簡単に確認でき、手続きの簡略化も期待されています。
本記事では、「後期高齢者医療制度」について詳しく解説するとともに、マイナ保険証の概要についても確認していきます。
なお、後期高齢者の医療保険料は都道府県ごとに異なるため、お住まいの地域の金額もあわせて確認してみてください。
1. 後期高齢者医療制度:医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)
日本では少子高齢化が進んでおり、75歳以上の高齢者の数が増加しています。これにより、医療費の負担が増大し、現役世代の負担も増えることが予想されます。
また、高齢者の医療費は年々増加しており、これを支えるための財源が必要です。
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、このような変化に対応するために見直しが行われています。
見直しは住民税課税所得などをもとにおこなわれ、毎年8月1日に決定されます。
原則として、自己負担割合は1割で済みますが、一定以上の所得がある場合は2割、現役並みの所得がある場合は3割と、負担割合が増えます。
これまで1割負担だった人でも、前年の所得に変動があれば自己負担割合が変わることもあります。例えば、不動産や株式の売却益などが発生して所得が増えた場合などです。
自己負担割合の判定基準についても、整理しましょう。
自己負担割合の判定基準
後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合の判定基準は、以下のとおりです。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、詳しくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。
もし1割負担だった人が2割や3割に変更されると、医療費が2倍・3倍になる可能性があります。これは特に医療費が高額になる場合に大きな影響を与えるため、注意が必要です。
新しい保険証が届いたら、まず自己負担割合に変更がないかを確認しましょう。