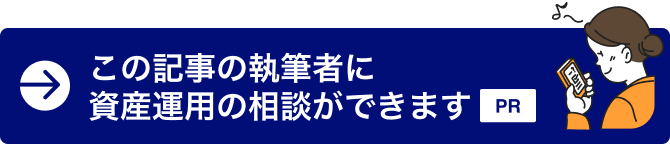2. 60歳代の貯蓄事情「貯蓄に回す割合」と「金融商品を選ぶ基準」
同資料より、60歳代世帯が年間手取り収入(臨時収入)のうち、どれくらい貯蓄に回したか、その割合も見ていきましょう。
また、参考までに、金融商品を選ぶ際には何を基準にしているのかも確認していきます。
2.1 60歳代「年間手取り収入(臨時収入を含む)」からの貯蓄割合(金融資産保有世帯)
貯蓄の割合:回答者の割合
- 貯蓄しなかった:39.1%
- 5%未満:5.1%
- 5%~10%未満:9.9%
- 10%~15%未満:15.2%
- 15%~20%:3.2%
- 20%~25%:8.4%
- 25%~30%:1.6%
- 30%~35%:6.3%
- 35%以上:6.9%
手取り収入を「貯蓄しなかった」世帯が約4割と最多でした。
60歳代は、これから年金暮らしの世帯とすでに年金暮らしの世帯とが混在する年代です。
年金暮らしが始まっている世帯であれば、手取り収入を貯蓄に回す余裕はないかもしれません。
一方、これから退職を迎える世帯では、ラストスパートとしてできるだけ多く貯蓄に回すよう意識していることも考えられます。
2.2 60歳「金融商品を選ぶ基準」とは
収益性:28.7%
- 利回りが良いから:16.4%
- 将来の値上がりが期待できるから:12.2%
安全性:36.2%
元本が保証されているから:28.3%
- 取扱金融機関が信用できて安心だから:7.9%
流動性:21.6%
- 現金に換えやすいから:11.1%
- 少額でも預け入れや引き出しが自由にできるから:10.5%
その他:13.5%
安全性が36.2%で最多となり、収益性の28.7%を上回りました。
貯蓄の目的が「老後資金」となる場合には、やはり安全性を重視することになるでしょう。
ただし、老後のお金も「短期・中期・長期」といつ頃使う予定なのか、色分けしておくとベターかもしれません。
10年、20年と手をつける予定のない資産であれば、安定性を重視しながらも預貯金より増える期待がもてる金融商品で資産運用を行い、インフレリスクによる資産価値の目減りを回避する。そんな方法も一つです。