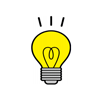C子さんの実家は比較的所得の高い人が多い地域です。C子さんが子供のころ、近所のおばさんたちの井戸端会議で「Bちゃんは、保育園に通っているそうよ、かわいそうに」とウワサしているのを聞いたことがあります。そんな環境で育ったC子さんは、保育園に子供を預けることで後ろめたさを感じつつも、反面教師な気持ちもあり保育園に子供が0歳の時から預けて仕事をしています。
C子さんのお母さんから「お迎え行こうか?」「ご飯のおかず、持っていこうか?」というLINEがきても頼り切れず、とても複雑な心境だとC子さんは嘆いていました。
「子供も親も笑顔でいられる」を判断材料に
子育ての主体はあくまでも「親」です。子供が悪いことをしたときに責任が生じるもの「親」です。祖父母は代わりに責任を負ってくれません。
そんな祖父母も、昔は自分たちを育ててくれた「親」でした。でも、孫に関してはかわいさ故についつい甘やかしてしまいます。嫌われたくないので、いい顔をし続けます。お金も許せる範囲で出してくれます。ありがたい側面もありますが、時として親の意見の口封じの材料にもなります。「お金をもらっている」ということが「弱み」になるのです。
しかし、子供の親は「自分」です。独立した世帯なのですから、過干渉に「NO」という権利があります。「親がそう言っているからしょうがないか」という判断基準だと、うまくいかなかった時に「親のせい」になってしまいます。それでは親から自立していることになりません。祖父母の過干渉が当たり前で、自分達で判断できなくなっている夫婦がいるのもまた事実です。
自分たちが人の親となった以上、責任を持って判断することが大切です。もちろんアドバイスを受けるのは良いですが、最終的な判断の責任は親にあります。困った時には他人のサポートを受けるかどうかの判断をするのも親です。子供も親も笑顔でいられるためにどうしたらいいか?を判断材料に取捨選択していくことをお勧めします。
堀田 馨