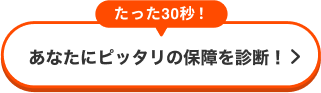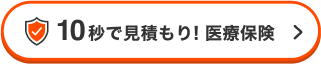3. 年代別に見る必要な保険
最低限入っておくべき生命保険は、年代によっても異なります。ここからは、年代別に必要な保険について解説していきます。
3.1 20代:基礎的な保障の確保
20代は健康に自信を持っている人が多いですが、収入は安定していない時期です。そのため、将来のリスクを考慮した保険選びを始めることがポイントです。
独身であれば医療保険やがん保険による最低限の医療保障を確保し、万が一の時に家族に迷惑をかけたくないのであれば、最低限の死亡保険の加入を検討しましょう。保険料負担は無理のない範囲に抑え、資産形成とのバランスを考慮することが重要です。
3.2 30~40代:ライフステージに応じた保障
結婚や出産、住宅購入などライフスタイルが大きく変化するこの時期は、目的に応じた保険の見直しが最も重要になります。
家族を支える立場にある場合は、十分な死亡保険による備えが必要です。教育費や住宅ローン、家族の生活費を考慮した保障額を設定しましょう。また女性の場合は、女性特有のがんリスクが高まる年代でもあるため、医療・がん保険の検討も必要です。
3.3 50~60代:保障の無駄の見直し時期
子どもの独立や住宅ローンの完済に伴い、必要な死亡保障額が減少する時期です。
過剰な保険を見直し、老後の医療・介護リスクに備えた保障にシフトすることが重要になります。同時に、保険と資産形成のバランスを再検討し、老後資金の準備を進めることも大切です。
3.4 70代以降:最低限の保障への調整
十分な資産がある場合は、保険に頼らなくても良くなる可能性があります。
ただし、葬儀費用や相続対策としての小規模な終身保険、増加する医療費への備えとしての医療保険は引き続き検討が必要です。保険料負担が老後資金を圧迫しないよう注意し、公的制度を最大限活用しながら最適な保障を維持しましょう。
4. 保険種類別の適切な保障額設定
保険に入るなら無駄のない保障で備えておきたい、と思っている人がほとんどでしょう。ここからは、保険種類別に適切な保障額の設定について見ていきましょう。
4.1 死亡保険の保障額算定
死亡保険の必要保障額は、残された家族の生活費、教育費、住居費などを総合的に考慮して決定します。
共働き世帯では配偶者の収入や公的年金も考慮し、過大な保障を避けることが重要です。住宅ローンがある場合は団体信用生命保険でカバーされることも計算に入れましょう。独身の場合は、葬儀費用程度の保障で十分な場合が多いです。
4.2 医療保険・がん保険の保障設定
医療保険では、公的医療保険制度や高額療養費制度を考慮した適切な保障額を設定します。
入院日額は5,000円~10,000円程度を目安とし、差額ベッド代や入院時の食費など公的保障でカバーされない費用に備えましょう。また、医療保険の先進医療特約は毎月数十~数百円程度で付加できるため、最低限の保障として持っておくことを検討しましょう。
がん保険では、長引く治療の可能性を考慮して診断一時金を設定しましょう。診断一時金を複数回受けられる保険で再発や転移に備えることもおすすめします。最近では入院は短期化し、通院での治療も多くなっているため、通院治療や抗がん剤治療にも対応できる保障内容を選ぶことが重要です。
4.3 就業不能保険の必要性判断
就業不能保険は、病気やケガで働けなくなった際の収入を補填する保険です。
会社員の場合は傷病手当金を考慮し、不足分を補う保障額を設定します。自営業者やフリーランスは公的保障が少ないため、生活費の全額に近い保障が必要になる場合があります。住宅ローンや教育費などの固定支出がある場合は、特に重要な保障となります。