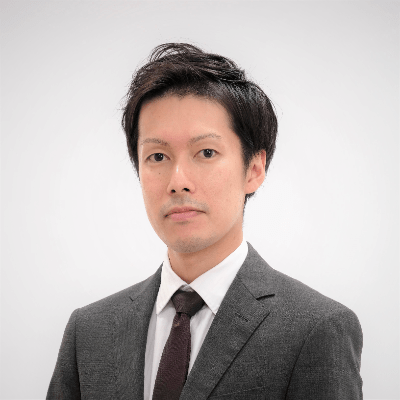4.2 エンゲル係数は29.8%とやや高め
同世帯のエンゲル係数(消費支出に占める食料費の割合)は29.8%と、一般的にはやや高めの水準です。
エンゲル係数の計算式は以下のとおりです。
- エンゲル係数(%)= 食料費 ÷ 消費支出 × 100
シニア世帯のエンゲル係数が高くなる背景には、以下のような要因が挙げられます。
- 年金収入など可処分所得が限られている
- 外食が減り、自炊中心となることで食材購入費がかさむ
- 教育費や住宅ローンなどの支出が減少し、食費の比率が相対的に上昇する
したがって、エンゲル係数が高いからといって「贅沢な暮らし」をしているとは限りません。生活構造の変化による自然な結果といえるでしょう。
ただし、外食費や高級食材などの支出が多い場合や、食費の増加によって医療費や光熱費などの必要支出が圧迫されている場合は、支出のバランスを見直す必要があります。
4.3 可処分所得を超える支出|平均消費性向は115.3%
さらに注目すべき点として、65歳以上・無職夫婦世帯の平均消費性向は115.3%に達しています。
つまり、支出が可処分所得(収入から税金・社会保険料を差し引いた金額)を上回っていることを意味します。
このような状況が続けば、預貯金などの蓄えに依存した生活が続くこととなり、将来的に資金が枯渇するリスクが高まります。
老後生活を安定させるためには、現状の支出構造を把握したうえで、家計の見直しや収入補填の対策を講じることが重要です。
5. 自分自身の「老後資金のあり方」を考えよう
今回の年金制度改正は、社会の変化に対応し、より多くの人が制度の恩恵を受けられるよう改善されたものです。特に、パートなど短時間勤務の人の社会保険加入拡大や、遺族年金の見直しは、将来的な年金額の底上げにつながる可能性があります。
しかし、制度が整備されても、実際の生活に直結するのは「いくら受け取れるのか」「毎月の支出と収入のバランスが取れているのか」といった現実です。
総務省の調査によれば、生活費の平均は月約28万7000円とされており、毎月約3万4000円の赤字が出ているのが実態です。
つまり、公的年金だけでは生活を維持するのが難しい家庭も少なくなく、貯蓄の取り崩しや、収入源の確保が重要になります。
公的制度を正しく知り、自分自身の「老後資金のあり方」を考えていきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 総務省「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」
加藤 聖人