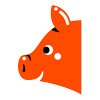EV(電気自動車)用電池事業からの撤退が報じられる
2017年8月3日、NEC(6701)がEV用電池事業から撤退し、中国の投資ファンド(GSRグループ)に売却すると複数のメディアが報じています。
売却を行うのは、日産自動車(7201)とのEV用電池の合弁会社であるオートモーティブエナジーサプライ社(以下、AESC)のNECグループの持分49%と、AESCに電池用電極を供給しているNEC100%子会社のNECエナジーデバイス社の全株式とされています。
ちなみに、AESC社の2016年3月期売上高は366億円で、車載用リチウムイオン電池市場ではパナソニック(6752)に次いで2番手のポジションにあります。現在は日産のEV車である「リーフ」向けが主力製品となっています。
一方、NECエナジーデバイスは、2010年にNECトーキンの大容量ラミネートリチウムイオン二次電池事業を承継して設立されており、各種報道によると直近の売上高は約150億円であった模様です。
やや意外感があった売却報道
このニュースにやや意外感があったのは、最近の株式市場ではEV用電池市場が成長分野として注目を浴びていたことに加え、直近のNECの決算説明会における質疑で、以下のようなやり取りがあったためです。
証券アナリストからの質問は、「世界的に自動車のEV化が進む中で、NECの現在のポジションはどうなっているのか」という趣旨でしたが、これに対する答えは次のようなものでした。
「これまで日産との合弁会社であるAESC向けにEV⽤電極を出荷しており、今年度の当社の電極売上は増加する⾒込みです。また、技術的な優位性も維持できています。当社の電極は出荷開始以来、発火事故もなく、安全性が高いと考えています」
こうしたNECの電池事業の優位性を強調する回答からは、撤退の可能性を読み取ることはほぼ困難であったと思われます。
伏線は去年からあった
とはいえ、撤退の伏線は以前からあったことも事実です。
というのも、カルロス・ゴーン氏(現日産自動車取締役会長)は以前から、電池についても「QCD(品質、価格、納期)で調達先を決める」と公言しており、電池の内製化には固執しない考えを示していたからです。
また、昨年の夏には日産がAESCの持分を中国のGSRグループに売却する検討をしていることや、日産が独自に米国・英国で展開している電池生産事業を売却する方針も複数のメディアにより報じられていました。
なぜNECは売却を検討しているのか
では、報道が事実であると仮定して、NECはなぜリチウムイオン電池事業を手放そうとしているのでしょうか。理由はいくつか推測されます。
まず第1は、GSRグループがAESCの全株式の売却を強く求めている可能性です。GSRグループは、日産の持分だけではなく、残りのNECグループの持分も取得し、100%保有する株主となることで、より迅速にAESCの企業価値を高めるための施策に取り組もうと考えている可能性が推察されます。
第2は、仮に日産だけがAESCの株式を売却し、GSRグループを経由した新たな買い手が電池メーカーであった場合、主導権はその電池メーカーに取られてしまい、NECエナジーデバイスからの電極の購入も取りやめとなってしまうことが懸念された可能性です。
第3は、NECはNECエナジーデバイスの電極事業から得られるシナジーが限定的と判断したことが考えられます。NECは、家庭用および業務用の蓄電システムなどのスマートエネルギーソリューション事業も展開していますが、採算は厳しく、最近の業績悪化の一因となっていました。
また、他社から購入した電池を活用することで採算改善を目指す考えも示していたため、そのことも撤退を検討している背景にあると推察することができます。
最後は、電池事業を売却することで多額のキャッシュを得て、それを新たな成長分野に投資することを検討している可能性です。なお、8月3日付け日本経済新聞によると、NECが保有するAESCの持分の売却金額は1,000億円前後、また、NECエナジーデバイスについては150億円前後と報じられています。
今後の注目点
EV用の電池事業は、中長期的に高い成長が期待できる事業分野であるため、撤退というのはあまりにももったいない、あるいは、いさぎよすぎるという印象は免れません。成長事業を育て上げるまでもう少し忍耐があってもいいように感じてしまいます。
また、仮にNECが日産からAESCの持分を買い取り100%子会社化すれば、「“日産色”を取り除き、他の自動車メーカーによる拡販が可能となる」という、GSRグループの狙いと同じことが実現できるわけですが、それがなぜ検討されないのかという疑問も残ります。
とはいえ、今のNECには電池事業を抱えるだけの体力がないというのが現実なのかもしれません。そうであれば、ここで得られるキャッシュが次の成長戦略に有効に活用されるのかを注視していきたいと思います。
LIMO編集部