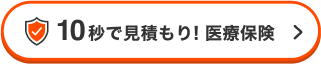病気やケガに備える医療保険への加入を検討する際、「公的医療保険があるから民間の医療保険は不要なのでは?」と疑問に思う人もいるでしょう。特に毎月の保険料負担を考えると、その必要性について慎重に判断したいものです。
本記事では、プロの視点から、医療保険が本当に必要な人・不要な人の特徴と、自分にとって最適な判断をするための具体的なポイントを詳しく解説します。
1. 医療保険が不要な人の特徴
日本の充実した公的医療保険制度を考慮すると、民間医療保険への加入が必要でない人もなかにはいます。保険のプロが考える「医療保険が不要な人」の特徴を見ていきましょう。
1.1 十分な貯蓄がある人
厚生労働省の統計によると、日本人が生涯にかかる医療費は約2300万円で、その半分は70歳以上で必要になります。実際の負担額は、公的医療保険を利用することで1~3割に抑えられます。これらの費用を自分の貯蓄で十分賄えるのであれば、民間医療保険の優先度は低くなります。
ただし、医療費だけでなく老後資金や生活費なども考慮する必要があります。治療が長期化した場合の収入減少や、せっかく蓄えた貯蓄が医療費で減っていくリスクも想定しておくべきでしょう。
公的医療保険制度の自己負担割合
公的医療保険では年齢と所得に応じて自己負担割合が決まります。
- 小学校入学前:2割負担
- 小学校入学後から70歳未満:3割負担
- 70歳~74歳:一般・低所得者2割、現役並み所得者3割
- 75歳以上:一般・低所得者1割、現役並み所得者3割
例えば100万円の治療費であっても、現役世代なら30万円の自己負担で済みます。
また、高額療養費制度を利用すればさらに1カ月の自己負担額を抑えられるケースもあります。ただし、先進医療や差額ベッド代などは全額自己負担となる点に注意が必要です。
1.2 健康保険組合の保障が充実している人
大企業の健康保険組合には、独自の付加給付制度を設けているところが多くあります。例えばトヨタ自動車健康保険組合では、医療費の自己負担額から2万円を差し引いた額が還付される制度があり、実質的な月額負担は2万円程度に抑えられます。
このような充実した健保組合に加入している場合、民間医療保険の必要性は大幅に低下します。自分の加入する健保組合の付加給付内容を確認してみましょう。
2. 医療保険が必要な人の特徴
一方で、民間医療保険への加入が特に重要となる人の特徴も明確に存在します。
2.1 医療費負担で家計に支障が出る人
入院や手術により仕事を休まざるを得なくなった場合、収入減少と医療費負担が同時に発生します。会社員の場合は有給休暇である程度カバーできますが、自営業者や日給制の労働者は休んだ分だけ収入が減少してしまいます。
生命保険文化センターの調査によると、入院時の自己負担費用平均は約19.8万円で、入院期間が長くなるほど負担額も増加します。15~30日の入院では平均28.4万円、61日以上では平均759万円もの費用がかかっています。
2.2 治療選択肢を広げたい人
公的医療保険の対象となるのは保険適用の治療のみです。より良い治療環境や最新の医療技術を希望する場合、以下のような費用が全額自己負担となります。
- 差額ベッド代:個室平均約8437円/日、4人室平均約2724円/日
- 先進医療技術料:重粒子線治療約318万円、陽子線治療約265万円
- 入院諸費用:食事代、交通費、日用品など
民間医療保険からの給付金があれば、これらの費用を気にすることなく最適な治療を選択できるようになります。