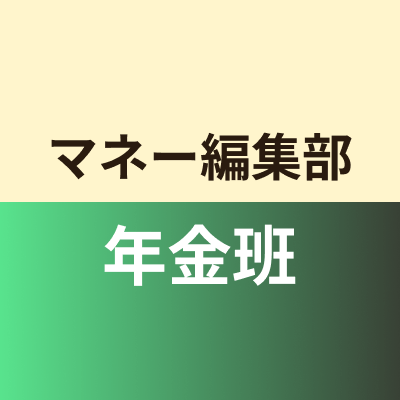6. 年金シニア世帯の43.4%で「公的年金は唯一の収入源」
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の収入の実態を見ていきましょう。
まず、高齢者世帯全体の平均的な所得構成を見ると、収入の63.5%を「公的年金・恩給」が占めており、次いで仕事による収入である「稼働所得」が25.3%、「財産所得」が4.6%となっています。
しかし、これはあくまで全体の平均値です。
「公的年金・恩給を受給している世帯」に絞ると、収入の全てが「公的年金・恩給」である世帯が43.4%にものぼることがわかっています。
※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯
6.1 【総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成】
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
このようにシニア全体で見れば稼働所得なども一定の割合を占めていますが、年金受給世帯に絞ると、その半数近くが公的年金収入のみに頼って生活しているという実態が浮き彫りとなっています。
7. まとめ
今回は、日本の公的年金の仕組みと、最新データに基づくシニア世代の受給実態について解説しました。
まず個人の受給額を見ると、厚生年金の平均年金月額は14万円台、国民年金のみでは6万円台ですが、これらはあくまで平均値です。実際に受け取る額は、加入期間や現役時代の収入により一人ひとり大きく異なります。
また、老後の生活は個人だけでなく、夫婦など「世帯単位」で捉える視点も欠かせません。その上で注目すべきは、「年金を受給している高齢者世帯」の約4割が、他の収入源を持たず公的年金のみで生活しているという実態です。
個人の受給額、そして世帯の状況。このふたつをじっくり見ることで、公的年金を主な収入源としながらゆとりある暮らしを送るための課題点が見えてくるかもしれません。
今回ご紹介したデータが、働き盛りの現役世代のみなさんにとって、ライフプランや資産形成について具体的に考えるきっかけとなれば幸いです。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「『年金額改定通知書』と『年金振込通知書』(年金受給者用:はがきサイズ)」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
マネー編集部年金班