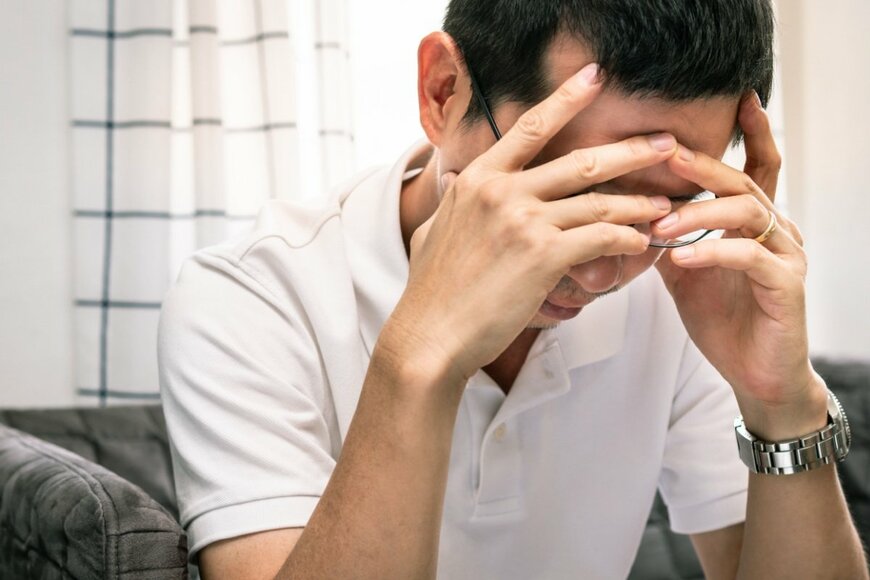4. 国民健康保険料の支払いが苦しいときの軽減措置はある?
国民健康保険料は、たとえ所得がゼロであっても原則として納付義務があります。
特に、保険料は前年の所得をもとに算出されるため、退職した翌年などは収入が減っていても高額な保険料が課されることがあり、支払いが困難になるケースもあるでしょう。
しかし、支払いを滞納してしまうと延滞金が加算される可能性がありますので、早めの対応が重要です。
まずは、お住まいの市区町村(または特別区)の国民健康保険窓口に相談してみましょう。
たとえば、会社都合による離職(解雇や倒産など)で収入が途絶えた場合、一定の軽減措置が受けられることがあります。
さらに、災害などで生活が著しく困難になった世帯に対しては、保険料の減免が認められる場合もあります。
窓口での相談を通じて、分割納付が認められるケースもありますので、一人で抱え込まず、まずは状況を伝えてみてください。
また、自営業などで確定申告をしていない場合、本来受けられるはずの軽減措置(均等割・平等割の軽減、未就学児に対する軽減など)が適用されていない可能性があります。
確定申告や住民税の申告を行うことで、保険料が軽減されることもありますので、必要に応じて手続きを行うことが大切です。
5. 「もしも」に備える対策を進めておこう
今回は、国民健康保険の基本的なしくみや保険料について確認してきました。
自営業や無職の方は、会社員に比べて保障が限られているため注意が必要です。たとえば、国民健康保険には「出産手当金」や「傷病手当金」がなく、病気やケガ、出産などで収入が途絶えてしまったときに備えるには、民間の保険を活用するのも一つの方法です。
また、将来受け取る年金についても、厚生年金に加入していない分、会社員の方に比べて少なくなる可能性があります。
老後は、介護や医療などの出費が増えることも想定されますし、思っていたよりも長く働けなかった…というケースも珍しくありません。そうしたリスクに備えて、年金だけに頼らず、早めに貯蓄や資産形成を進めておくことが大切です。
夏本番を迎える今、少し立ち止まって、これからの暮らしやお金について考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
- 名古屋市「令和7年度 名古屋市国民健康保険料 概算早見表」
- 奈良市「令和7年度国民健康保険料決定通知書の送付について」
- 厚生労働省「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(通知)」
矢武 ひかる