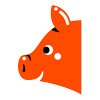はじめに
あなたは労働時間と休憩時間、休日の定義・ルールについてどのくらい知っていますか?労働基準法に定められた内容を知らずに働いている人は意外に多いのではないでしょうか。
この記事では、適切な労働環境で仕事をするためにも、法律によって定められた労働時間の限度や制度、休憩時間と休日の遵守についてご紹介していきます。
目次
1. 労働時間・休憩・残業時間の定義とは
2. 時間外労働に関する労使協定(36協定)と労働時間について
3. 労働時間には種類がある
4. 週40時間の労働時間の実現に向けて
5. 法定労働時間を超過した「時間外労働時間」の限度に関する基準
6. 労働時間の裁量労働制の詳細
7. 労働時間の変形労働時間制の詳細
8. おわりに
労働時間・休憩・残業時間の定義とは
従業員の労働時間の規定については、労働基準法を基に制度化されており、厚生労働省のホームページ等で確認する事ができます。労働基準法第32条によると、従業員の勤務時間は原則、1日8時間以内、1週間40時間以内におさめなければなりません。また、労働時間が6時間を超過した時は45分以上、8時間を上回った場合には、使用者は1時間以上の休憩時間を設ける必要があります。また、休日においては、毎週1日の休日、または4週間を通じて4日以上を従業員に与えるよう定められています。
労働時間とは従業員が業務に従事している時間に留まりません。「労働」が具体的にはどこからどこまでを示すのかは、労働基準法には明記されてはいませんが、裁判の判例の解釈では、使用者の指揮命令下に置かれている時間も一般的に労働時間に含まれているのが現状です。
例えば、昼休み中であっても、来客対応や電話番をしなければならない時は労働時間に該当します。同じように、警報が鳴り響いた時のような緊急対応しなければならない環境下での仮眠時間も労働時間として認められていますが、それが業務から解放されている状態であれば休憩時間に当たります。
通勤時間や出張先への直行・直帰は該当しませんが、指定の制服・作業服の着用義務がある場合の更衣時間は労働時間に入ります。また、外部研修や社員旅行は会社から強制・強要されたものに限り、労働時間として扱われています。
そして上記のような様々なケースの労働時間の合計が、労働基準法で定められた上限時間を超えた場合には、残業時間としてカウントされます。
時間外労働に関する労使協定(36協定)と労働時間について
時間外労働時間、いわゆる残業については、労働基準法第36条にて定められており、これを基に「36(サブロク協定)」と呼ばれる労使間協定を結ぶことが必要となっています。これは労働組合、または組合でなくても従業員の過半数を代表する者が会社と書面による時間外労働協定を結んだ場合には、法定労働時間を超えた労働(残業や休日出勤)をさせることができるというものです。
ちなみに36協定は、たった1人の従業員の時間外労働であっても、労働基準監督署に届ける事が義務付けられており、違反した場合は労働基準法違反となり罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が設けられています。そして、36協定で合意された法定労働時間を超えた分は、時間外労働としての1.25倍の割増時給になり、休日労働であれば所定の賃金の1.35倍が支払われます。
逆に労働時間を1日7時間として雇用契約を結んでいる場合には、1時間以内の残業であれば、会社が定めた所定労働時間ではなく法定労働時間の基準が適用されるため、36協定の対象外となり、会社側は割増賃金を支払う必要がありません。
ところで、36協定については、労使間で締結し、労基署に届けでさえすれば際限なく残業が認められるわけではなく限度が定められています。ただし、システムの大規模改修や、繁忙期などやむを得ない場合、労使間の合意に基づいた「特別条項付の36協定届」によって、年間6ヶ月以内に限り、1.5倍の割増時給にて限度を超えた残業が可能とされています。これら労働時間の上限については厚生労働省の「時間外労働の限度に関する基準」通達に基づいて運用されています。
労働時間には種類がある
さまざまな仕事がある現代社会では、1日8時間、1週間40時間以内という法定労働時間に基づいて仕事を行うのは難しい現状があります。労働基準法にはそのようなケースのための規定もあり、業種・業務内容や雇用形態に合わせて様々な形の労働時間が定義されています。
この内、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内であれば、特定の日あるいは週において法定労働時間を超過して労働させる事ができる制度を「変形労働時間制」といいます。この制度を上手に利用すれば、一時的に労働時間が1日当たり8時間、1週当たり40時間を大幅に超えても、仕事が少ない時期と帳尻を合わせる事で残業代の支払いがなくなります。
他には労使協定で結ばれた一定期間の総労働時間に基づいて、始業・終業時刻を労働者が自主的に決める事ができる制度「フレックスタイム制」と呼ばれるものがあります。多くの場合、フレックスタイム制では、必ず勤務すべきコアタイムと、いつでも出勤・退勤可能なフレキシブルタイムを設定しています。
一方、営業を始めとする外回りの仕事や、研究職等は正確な労働時間を算出する事が困難です。こういった業務に携わる人達のために、「みなし労働時間制」という制度があります。これは業務によって3種類あり、それぞれに細かい条件が設定されています。
1つ目は、事業所の外で働く労働者に適用される「事業場外みなし労働時間制」です。2つ目は、業務時間配分・手段を労働者自身が決めるデザイナー・中小企業診断士・システムエンジニアのような特別な職業に適用される「専門業務型裁量労働制」です。そして3つ目が、主に本社等で重要な企画や調査分析を担うホワイトカラーに属している従業員に適用される「企画業務型裁量労働制」です。
週40時間の労働時間の実現に向けて
特定の業種かつ常時10人未満の特例措置対象事業場では1週間の法定労働時間は44時間と定められていますが、先述の通り、原則として使用者は労働者に対し、休憩時間を除き1日8時間、1週間40時間を超えて働かせてはいけません。労働基準法第32条に記載されているこの規則は「週40時間労働制」と呼ばれています。厚生労働省や労働基準監督署等では、この制度にもとづいた運用法をいくつか提案しています。
もっとも広く行われているのが完全週休2日制を導入した上で、1日8時間労働とする方法です。これは主に工場や役所関係で多く採用されています。この方法では全員一斉に休日を取る必要がないため、年中無休の販売業等では個別に休日を定めるシフト制を用いているところもあります。
もし週休2日制が難しいのであれば、週1の休日であっても、数日間を早退にしたり、午後出勤にしたりするなどの調整をして、出勤日の労働時間を短縮するという方法もあります。そうすることで1週間当たりの労働時間を40時間以内に抑える事ができます。また季節ごとの業務の繁閑が激しい企業や、特殊な事業を手掛けている会社では、もっと臨機応変に所定労働時間を配分したい場合も多いかと思います。そのようなケースでは1ヶ月、1年単位の長期的な変形労働時間制を利用し、1週間当たりの平均労働時間を40時間にする方法がお勧めです。
週40時間労働制はどんな業種であっても臨機応変に取り組めば、無理なく実現させる事ができます。
法定労働時間を超過した「時間外労働時間」の限度に関する基準
通常、36協定で定める残業時間には上限が細かく定められています。具体的に説明すると、時間外労働時間の上限は1週間で15時間、2週間で27時間、4週間で43時間以内となっています。また、月単位では1ヶ月で45時間、2ヶ月で81時間、3ヶ月で120時間以内です。そして、年単位では1年間360時間以内となっています。なお、この時間外労働の上限には法定休日における労働は含まれていません。
対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制で働いている方の上限はさらに短くなります。時間外労働時間の上限は1週間では14時間、2週間で25時間、4週間で40時間以内と定められています。また、月単位では1ヶ月で42時間、2ヶ月で75時間、3ヶ月で110時間以内です。そして、年単位では1年間320時間以内となっています。
止むを得ない事情で、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない場合には、先にも紹介した「特別条項付き協定」を労使間で結ぶ事になります。特別条項付き協定で認められる延長時間の上限は、労使協定を経た上で、1ヶ月60時間、1年420時間までとなります。半年以内の案件が対象となり、あくまでも止むを得ない一時的な事例に限られます。
決算業務やボーナス商戦、納期のひっ迫、大規模なクレーム対応、突然のトラブル対応等がこれに当てはまりますが、この上限時間を超える回数は限度が定められています。なお、これは新商品研究開発、自動車の運転業務、工作物の建設事業等には適用されません。
労働時間の裁量労働制の詳細
先にも述べた通り、裁量労働制は労働時間制度の一つで、法律が認めた特定の業種について、実労働時間ではなく就労規則に則った一定の時間を労働時間とみなす制度です。出勤・退勤時間の自由が利く点はフレックスタイム制度と似ていますが、あくまでも実労働時間を計算しているフレックスタイム制度とは全くの別物です。
裁量労働制を適用する上で、使用者は労働者に対し、実働時間とのギャップがないよう、みなし時間は今までの労働環境を元に労使で決定する事が求められます。当然のことながら、みなし時間であっても労働基準法の規制の対象となります。
法定労働時間を超えた分は36協定を結ぶ必要があり、残業代の支払いが必要となります。とはいうものの、実際には実労働時間に応じた残業代を出す事ができないため、不当な長時間労働に及んでしまうケースも少なからず出ています。
しかし、元々この制度は、正当な成果を評価されにくい職業の労働環境を改善し、より効率的に働けるように作られました。
そのため、この制度の対象となる労働者を第一に考えた健康確保措置や苦情処理措置も含めて労使協定を締結し、労働基準監督署に届ける仕組みになっているのです。
今なお、長時間労働の問題が後を立ちませんが、自分一人で解決しようとせず、労働者側の立場にある労働組合または又は労働者代表に相談してみましょう。それでも状況が改善されない時は、労働基準監督署や弁護士への相談をお勧めします。
労働時間の変形労働時間制の詳細
先にも紹介した変形労働時間制は、一定の単位期間において、週当たりの平均労働時間によって規定の労働時間を達成する目的で作られました。この方法は、時期によって業務量が著しく激しく変動する企業が主に採用しており、1ヶ月単位、あるいは1年単位の変形労働時間制と、1週間単位非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制の4種類が存在します。この内、1週間・1ヶ月・1年単位の変形労働時間制では、各日の労働時間を会社が設定し、逆にフレックスタイム制は会社が1ヶ月の総労働時間を設定した上で、各日の労働時間を従業員が決めるという特徴があります。
また1ヶ月単位の変形労働時間制は使用者が作成した就業規則によって導入可能ですが、1年単位の場合は、労働組合か労働者の過半数の代表者と労使協定を締結する必要があります。これは労働時間を平均する期間が長いと、極端な長時間労働の日が出てくる可能性があるためです。そのため、1年単位の変形労働時間制については、労働時間は原則1日10時間、1週間52時間以内と労働基準法に定められています。
一方で単位期間が短くても、1週間単位の変形労働時間制には労使協定の締結が求められます。しかしながらこの制度を利用できる事業所は労働者30人未満の販売店・飲食店等に限定されているため、採用している企業はあまり多くはありません。
ケースが細分化され融通が利きやすいこの制度ですが、所定労働時間が不規則になるリスクを抱えています。そのため職種関係なく一定の適用適応基準が設けられています。特に妊娠中や、産後1年を経過していない女性にはこの制度を適用活用する事はできません許されません。他にも育児中や、シニア世代の介護をしている人にも配慮するよう労働基準法に定められています。
おわりに
いかがでしたか?労働時間について詳しく知る事で、自分の働き方、会社との向き合い方を見直すきっかけになります。労働基準法を始めとする法律の内容は、とても難しく感じてしまうかもしれませんが、それが自分自身の一生を左右するかもしれません。
私たちは過ごしやすい職場環境、最適な労働時間の中でこそ、最高のパフォーマンスを発揮できるものです。もし、あなたが今の労働環境に不満を感じているのであれば、これを機に、身の回りの働き方改革を始めてみませんか?
LIMO編集部