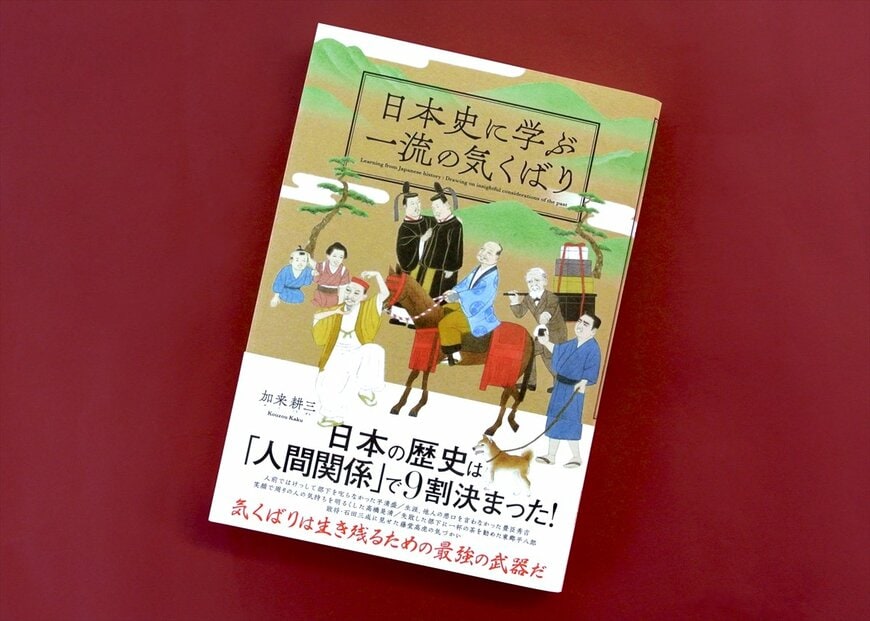皆さんの職場は、チームワークがうまくとれているでしょうか。お互いを高め合うような人間関係ができていれば、おのずと結果はついてきて、チームの成果は上がるものです。しかし昨今は、職場の雰囲気が悪い、人間関係がよくない、皆の気持ちがバラバラだ、などという声をよく耳にします。これでは、チーム一丸となって、いい結果を残すことなどできないでしょう。
『日本史に学ぶ一流の気くばり』の著者であり、歴史家・作家の加来耕三氏は、「強いチームづくりのヒントは日本史にあります」と言います。同書をもとに加来氏に解説してもらいました。
薩摩藩の掟、一度決めたら「議を言うな」
強いチームとして、まず挙げたいのは薩摩藩です。薩摩では、「チームの決定に従う」ことを徹底していました。勘違いしてほしくないのは、「リーダーの決定には従う」ではなく、「チームの決定」に従うのです。
薩摩藩では、チームの方針を決めるプロセスに、各メンバーが参画します。メンバー同士が意見を出し合って、徹底的に議論をします。その上で、チームとしての方針が決定したら、あとはその実現に向けて全力を尽くすのです。
薩摩では、これを「議を言うな」(薩摩弁では、議を言な〈ぎをゆな〉)と称しました。皆でやると決めたことに関して、あとになってから理屈(や文句)ばかり言うな、という意味です。決定事項・チームの方針には従い、全身全霊で目的を達成する。その代わり、議論はとことんやります。「オレはこう思う」「それは違うだろう」と、薩摩藩士は意見をぶつけ合います。でも、最終的に決まったあとは、自分は反対意見であろうと、その方針で動くのです。
これぞ、強いチームの原動力です。重要なのは、「どれだけ密度の濃い話し合いをしたか」です。
なぜ居酒屋で「俺は反対だった」と言う人間が出てくるのか
現代でも、会議の席で上司から「意見があれば遠慮なく言ってほしい」と促されるでしょう。でも、口を開く人は少ないのではありませんか?
「〇〇君はどう思うんだ」と指名されると、「部長の意見に賛成です」と議論にならない発言をする場面も、多いのではないでしょうか。
本気で活発な議論を望むのなら、上司は「反対意見を言え」と促すべきです。そこまでやらなければ、不完全燃焼のまま、プロジェクトに参加する人間ができてしまいます。反乱分子や不協和音を抱えたまま、チーム一丸となって前に進むことは不可能です。
そうでないと、居酒屋に行ってお酒が入ってから「実は俺は反対だ」とか、「部長のプランは失敗すると思うな」と吐き出すメンバーが出てきます。このような状態では、強いチームワークが生まれるわけがありません。
強いチームには多様性が欠かせない
強いチームに欠かせないのは、「メンバーの多様性」です。同じような考え方の人間しかいないチームでは、想定外の事態が起きたときなどに、脆さを露呈するでしょう。
その点、西郷隆盛・木戸孝允と並ぶ「維新の三傑」の一人、大久保利通は、多様性ある人材を集め、成果を挙げた一人です。
大久保は内務卿という国の最高権力者まで上り詰めました。そして彼は、自らの出自である薩摩藩以外の出身者からも広く慕われました。彼の「多様性を受け入れる気質」は、現代でもチームをまとめる上で、大いに参考になるはずです。
部下にとって「仕え甲斐」のある上司とは
大久保が創立した内務省には、とてつもない力がありました。日本の歴史上、最高に権力が集中した組織です。なにしろ大蔵省・外務省・文部省・陸海軍省以外の権益をすべて行使できる組織でした。司法権も警察権も持っています。
その最高の機関に、大久保は多くの人材を集めました。彼の下には、政治家として伊藤博文(長州藩)、大隈重信(肥前藩)があり、官僚には前島密(幕臣)、千坂高雅(米沢藩)などがいました。
郵政を担当した前島は、一度は薩摩藩士となりながら、それを捨てて幕臣となった経歴の持ち主です。もちろん、薩摩の人間を使わないのではありません。警察を率いた大警視・川路などは薩摩藩出身です。優秀な人材は出自に関係なく、次々に登用したのです。
信用した相手には、実務は任せてしまう。部下にとって、大久保は仕え甲斐がある上司でした。
柴田勝家が犯した致命的なミス
一方で、豊臣秀吉に敗れた柴田勝家は、多様性を受け入れられず、失敗したといえるでしょう。勝家は、自分の経験してきた世界、価値観の中にいない人間を、「異物」として扱っています。考えの違う人間、異文化の人間を理解できない、理解しようとしないのです。
致命的だったのが、秀吉を拒んでしまったことでしょう。勝家からは、秀吉は別世界の人間に見えたのです。合戦に強い勝家から見れば、秀吉なんて槍も使えないし、戦闘力は足軽以下としか見ていません。その感情は当然、秀吉にも伝わっています。だから、それを逆手に取られたこともありました。
勝家が上杉謙信と戦った北陸戦線において、秀吉の軍勢が援軍として回された合戦がそうでした。大嫌いな勝家の許で戦うなんて、秀吉にすれば不満でなりません。あえて軍議の席上、援軍を得て、いよいよ決戦を挑もうとする勝家の策に異議を唱えました。
「ただ突っ込んでいくのは、無策というものです」
普段から虫が好かない勝家は、この一言で冷静さを失いました。
「そこまで従えないというなら、兵をまとめて帰れ」
ついに、怒鳴ってしまいます。
嫌いな相手ほど気をくばるべし
でも秀吉は、勝家からのその「帰れ」のひと言がほしかったのです。
逆に、「おまえの言うことにも一理ある。だが、今回はオレの策に従ってほしい。力を貸してくれ」と勝家が一歩退いていたら、局面は大いに違っていたでしょう。少なくとも勝家に分が生じます。
筆頭家老が頭を下げているのだから、今度は秀吉が従う以外に選択肢はなかったでしょう。そういう駆け引きにおいては、勝家はセンスがありませんでした。秀吉の心中を理解しようとする気くばりが、足りなかったのです。
自分が嫌いな相手、理解できない相手にも、気くばりを欠かしてはダメです。こちらから歩み寄って、理解しようと努力をする。これが本当の気くばりです。相手がその歩み寄りを知るだけでも、その先の好意につながるものなのです。
■ 加来耕三(かく・こうぞう)
歴史家・作家。1958年大阪市生まれ。奈良大学文学部史学科卒業後、同大学文学部研究員を経て、現在は大学・企業の講師をつとめながら、独自の史観にもとづく著作活動を行っている。『歴史研究』編集委員。内外情勢調査会講師。中小企業大学校講師。政経懇話会講師。主な著書に『坂本龍馬の正体』『刀の日本史』『1868 明治が始まった年への旅』などのほか、テレビ・ラジオの番組の監修・出演も多数。
加来氏の著書:
『日本史に学ぶ一流の気くばり』
加来 耕三