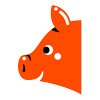8月のトルコショック以降、新興国では連鎖的な通貨不安が発生しています。これまでのところ「有事の金」は輝きを失っており、代わってブームが去った仮想通貨に人気復活の兆しが見え始めています。
トルコショックをきっかけに連鎖的な通貨安
新興国では連鎖的な通貨不安が続いています。震源地となったのはトルコで、米国人牧師の解放を巡って対米関係が悪化する中、8月10日にはトルコ・リラが対ドルで20%程度急落する「トルコショック」が起きています。
トルコショックにより外貨建て債務が膨らみ、返済負担が増大したほか、インフレ率も急上昇していることが投資家心理を冷ましています。リラ急落に見舞われたトルコ中銀は政策金利を24%にまで引き上げて通貨防衛を図っていますが、インフレ率が24.5%と政策金利を上回っていることから、実質ではマイナス金利となり効き目がありません。
対米関係の悪化、高インフレ、債務膨張の3重苦となっており、投資家にはトルコ・リラを買い戻すインセンティブが見当たらないようです。
トルコショックが最も顕著に波及したのが慢性的なデフォルトリスクを抱えているアルゼンチンです。アルゼンチンは8月29日、国際通貨基金(IMF)に対して追加支援を要請し、通貨不安に拍車をかけました。8月30日には政策金利を60%にまで引き上げて通貨防衛を試みましたが、結果は空振りに終わり、アルゼンチン・ペソの対ドルでの下落率は年初来で50%を超えました。
アルゼンチン・ペソの急落はお隣のブラジルへと波及しています。ブラジルでは5月に発生したトラック運転手のストライキの影響で経済活動が一時的にマヒしました。ただ、当初は一時的とみられていた景気の落ち込みですが、政治不安も重なって停滞が長期化することが懸念され始めています。
ストライキは収拾していますが、補助金による燃料費引き下げや最低賃金の引き上げなどで財政収支が悪化しており、通貨安の一因となっています。また、10月の大統領選挙では右派と左派の激突が予想されており、どちらが勝利してもその後の議会運営が難航することが見込まれています。
さらに、新興国での通貨安連鎖は経済が好調なインドにも及んでいます。4月まで1ドル=65ルピー台を推移していましたが、9月下旬現在は72ルピー台とこの間に10%程度下落しています。
8月下旬にインフラ開発・金融大手のインフラストラクチャー・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス(IL&FS)がデフォルトを起こし、信用不安が広がったことも下落に拍車をかけました。ただ、インド政府が10月1日、IL&FSの経営権を把握し、混乱の拡大阻止に動いてたことで事態は収拾に向かうことが期待されています。
また、インドの4-6月期のGDP成長率は前年同期比8.2%増と約2年ぶりに8%の大台を回復。2016年11月に突然発表された高額紙幣の廃止や2017年7月の財・サービス税(GST)導入に伴う混乱で一時6%台まで成長が鈍化していましたが、ようやく混乱前の水準を取り戻しています。
原油高による貿易赤字の拡大というネガティブ材料もあるにはありますが、景気の拡大が続くインドの通貨ルピーがさらに売り込まれる理由を経済ファンダメンタルから正当化するのは難しいでしょう。
底流にはドル高
新興国での通貨不安の個別要因はさまざまですが、底流にあるのはドル高であり、背景には米利上げがあります。
米連邦準備制度理事会(FRB)は3カ月に一度のペースで利上げを続けており、12月には追加利上げが実施される見通しです。また、欧州中央銀行(ECB)も量的緩和を年内で終了する見通しのほか、日銀も資産の買い入れペースが鈍化していることから、隠れテーパリング中との見方も少なくありません。
このように、米国を先頭にして先進国で緩和的な金融政策が徐々に引き締めの方向に向かっていることが、新興国からの資本流出を促しています。一方、通貨安に見舞われた新興国では資本の流出を防ぐために利上げが必至の状況となっていることも、新興国の景気見通しに暗い影を落としています。
中国の米国債売却の動きを警戒
米中貿易戦争は材料が出尽くした感があり、材料視されることが少なくっていますが、このまま終息に向かうと考えるのは時期尚早なようです。
注目は人民元安の動きです。米国は対中貿易赤字の削減を目的として中国からの輸入品に対して追加関税をかけていますが、人民元安が関税を相殺しているからです。
人民元の対ドルレートは4月の1ドル=6.2元台から8月には一時6.9元台となり、この間に10%以上下落しています。関税のよる輸出競争力の低下を人民元安で補う格好となっており、8月の米貿易収支を見ても対中貿易赤字が過去最大となり、米国の思惑は完全に外れています。
また、ドル高・人民元安を促しているのは米利上げのみではないようです。7月の中国による米国債の保有残高が1月以来、半年ぶりの低水準となったことから、トランプ政権による関税への対抗手段として米国債を売却しているのではないかとの観測が浮上しています。
米国ではインフレ基調が鈍化している中で長期金利の上昇が続いていることも、中国による米国債売却観測に信憑性を持たせているようです。
中国が対抗カードとして米国債売却を加速させた場合には、同時に新興国通貨安も加速させることになりかねません。また、米国債の売却は長期金利の上昇を招き、世界的な景気減速を招く恐れもあります。さらに、人民元安により期待された貿易収支の改善がみられませんので、トランプ大統領が人民元安に対抗措置を取らないとも限らないでしょう。
仮想通貨にスポットライト、円安基調の反転も?
こうした新興国での通貨不安をきっかけに、仮想通貨に再びスポットライトが当てられているようです。
トルコショックでトルコ・リラが急落する中、トルコの仮想通貨取引所ではビットコインの取引高が急増しました。また、通貨安に歯止めがかからないアルゼンチンでも仮想通貨への需要が急拡大しています。
トルコやアルゼンチンではインフレと通貨安がほぼパラレルで発生しており、自国通貨の購買力が急速に低下している状況です。インフレといえば金(ゴールド)がヘッジ手段として有名ですが、金利を生まない金は金利上昇局面に弱く、米利上げのあおりを受けて金価格は低迷しています。
ビットコイン価格は昨年12月の高値からあっという間に60%超下落しましたが、今年の6月以降に限るとほぼ横ばいで推移しています。昨年のようなブームは去ったとはいえ、認知度が高まった仮想通貨がいよいよインフレによる通貨価値の下落に対抗するヘッジとしても利用されつつあることは確かなようです。
米金利上昇を背景としたドル高の恩恵を受けて円安も進んでいますが、新興国での通貨安の背後にインフレ懸念があることを踏まえると、仮想通貨に並んで円の人気が高まる可能性もありそうです。というのも、現在最も物価が安定しているのが日本であり、インフレリスクには無縁な状況にあるからです。
一方、3月の1ドル=104円台から10月には一時114円台まで円安が進んでおり、米国の対日赤字を問題視するトランプ大統領が円安に対して懸念を表明するかもしれません。
日米金融政策の方向の違いを理由に円安が進むとの見方は後を絶ちませんが、インフレヘッジや割安感などから円安基調が反転する可能性には十分な警戒が必要となりそうです。目先的には10月中旬の公表が予定されている米財務省の為替報告書に注目です。
LIMO編集部