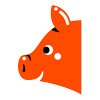編集部より
フィデリティ投信(以下、フィデリティ)の元ファンドマネージャーで現在相談役である山下裕士氏に、長い運用経験の中で印象に残っている銘柄をエピソードとともに語っていただきました。当時はまだ少なかった証券アナリストの仕事内容や印象深い企業とのやり取りなど、個人投資家にとっては貴重な情報が満載です。是非ご覧ください。
今回は山下氏が大学卒業後、大阪屋証券(現・岩井コスモ証券)で証券アナリスト業務に従事したのち、1978年4月にフィデリティに入社して以降、特にバブル崩壊前後から2000年にファンドマネージャーを引退するまでを取り上げます。
バブル崩壊でも突出したパフォーマンスの銘柄群-セガ、シマノ、しまむら
――バブル崩壊前後に記憶に残っていることはどのようなことでしょうか。
ご承知のように1985年から1989年にかけて大相場となりました。1984年7月23日に9,703円だった日経平均が、1989年12月29日には38,915.87円にまで上昇したのです。
1985年から1989年の間、私は海外の企業年金のうち日本株投資分の約3,500億円の運用を行っていました。しかし、1989年になると(海外企業年金の)彼等が全額を日本から引き揚げていきました。その際に彼らはこう言っていました。
「日本株は業績では説明がつかないくらい高い(割高)株価水準になった」
当時の株式市場を振り返ってみると、日経平均株価は1989年12月29日の38,915.87円から1990年10月1日の20,221.86円と48%急落するような状況でした。1991年は小康状態でしたが、1992年は2桁の続落となりました。
今振り返ってみれば、彼らの意思決定は賢明であったと思います。株価上昇と円高メリットで、4年間で4倍という投資リターンを確定したことになります。
海外の大手企業年金が資金を引き揚げたこともあり、私は1990年から1991年は比較的アセットサイズ(資産規模)の小さいファンドを運用することになりました。
――株式市場が大きく下落する中で、ほとんどの銘柄がお先真っ暗という状況だったのでしょうか。
そんなことはありませんよ(笑)。株式市場とは不思議なもので、その中にあっても必ず勢いのある銘柄が存在するものです。たとえば、セガエンタープライズ(現・セガサミーホールディングス)、次いで島野工業(現・シマノ)、コナミ(現・コナミホールディングス)、しまむら等、1990年の相場環境でも逆行高になった銘柄はありました。
セガは1986年に店頭登録されました(東京証券取引所第2部への上場は1988年、第1部への指定替えは1990年)。同社への投資は1年限定でしたが、業績に関して会社から何回も説明を受けた記憶があります。
当時はコンシューマー(消費者)向け事業(ハードウェアとソフトウェアの売上高比率は半々)、アーケード業務用機器の販売、オペレーション(自社経営と共同経営)がバランスよく利益を上げていました。1990年の株価の上昇率は115%で東京証券取引所第1部市場のトップでした。
シマノは当時の島野善三社長、角谷景司経理課長(現在は専務)に詳細な説明をしてもらった記憶があります。変速機、ブレーキ部品などの自転車部品では世界首位、加えてマウンテンバイクブームや消費者の健康娯楽指向もあり業績は好調でした。当時でも海外比率は85%あり、1990年の株価上昇率は84%と、株式市場が暴落の中で値上がり率第3位の逆行高でした。
出所:SPEEDAをもとに編集部作成
――図表1を見ると、確かに1990年のシマノの株価は逆行高ですね。それにしても、その後もすごいですね。
これが長期投資の醍醐味です(笑)。景気循環といったサイクルも投資では注意をしておく必要がありますが、同社の競争優位と消費者の嗜好が長期的なトレンドを形作っているという証拠です。アベノミクスで円安に振れましたが、そこでも恩恵を受けた格好です。
しまむらの藤原秀次郎社長は私の尊敬する経営者の1人です。同社は当時でも衣料品においてならイトーヨーカ堂、イオンと並ぶ存在感を持っていました。当然ながら藤原社長はアパレル業界の事情に精通しており、時代の先を読む力もすばらしかったと思います。1990年当時の店舗数は129店でしたが、現在では1,800店近くになっていることを考えればその展開力には感心します。
バブル経済でおかしくなった経営と企業-マイカル、そごう、イトマン
――バブル崩壊により経営がおかしくなった企業も多かったと思います。記憶に残っている企業はありますか。
バブル経済の中で放漫経営に走ったツケを払わされる会社もありました。経営実態が悪化しているにもかかわらず、粉飾決済をしてでも資金調達を目論んだ会社もあったのではないでしょうか。私自身も「何かがかおかしいな」と調査の中で気がついた会社もいくつかありました。
――どのような会社がおかしいなと感じたのでしょうか。
マイカルは米国での資金調達後に国内でも資金調達を計画していました。当時のマイカルの経理部長がフィデリティにプレゼンに来ましたが、日本の決算書ではそれなりの利益を計上していました。しかし、ニューヨーク証券取引所に提出した同社のアニュアルレポートに示されていた数字は数年にわたって赤字の決算でした。
数か月も経たないうちに、同社の業績の実態はアニュアルレポートに書かれたP/L(損益計算書)とB/S(貸借対照表)の方が正しかったとメディアで報道されました。
そごうは、長期にわたって計画された粉飾でした。そごう本体は心斎橋、有楽町等、数十年前からの店舗を有し安定した利益を上げていました。ところが、バブル時代に新設した横浜、千葉その他多数の店舗はそれぞれ別会社にし、相互に15%ずつの持ち合いという形をとっていました。
「なぜ15%程度の持ち合いなのか、なぜすべての店舗を連結するような経営にしないのか」
当時の私はそのことを非常に気にしていたのを覚えています。そごう本体の決算書には、横浜そごう以下のP/L、B/Sが全く反映されていなかったのです。その実態は赤字会社ばかり、多額の負債を抱えた会社ばかりということが後日明らかになりました。
伊藤萬(後のイトマン)は、某大手証券のアナリストから「EPSは50円で株価が500円であることを考慮すると割安だと思います。投資対象として興味はないですか」という連絡を受けました。一緒に行こうと誘ってくれたので、アポを取ってもらい同行しました。
一方で、連結決算では赤字、バランスシートにはいくつかの問題があったのを覚えています。当時の河村良彦社長や伊藤寿永光取締役の評判も良くありませんでした。後に許永中氏を含めた3人で会社から多額の資金を引き出しているという事実が検察によって暴露されました。最近出版された「住友銀行秘史」という本で全貌が明らかにされています。
マイカルはイオンの子会社となり、そごうは西武百貨店の支援を受けたのち、セブン&アイ・ホールディングスの傘下に入ることになりました。イトマンは住金物産(現・日鉄住金物産)に吸収合併されました。
バブル経済崩壊後に飛躍した企業-トヨタ、ダイキン、ローム、武田
――バブル経済は日本企業にとって結果的には悪い話ばかりだったのでしょうか。
いや、決して悪い話ばかりではありません。バブル期間中は多くの企業が大した企業努力をしなくても利益を上げられたことでしょう。しかし、バブルに踊らされることなく、粛々と企業体質を強化していた企業があったのも事実です。
結果として、バブル崩壊後はその企業努力が明暗を分けることになります。製造コストや販管費の削減、国際競争力の強化により逆境を乗り越え、持続的な利益成長を目指す企業が外部からもはっきりと見えるようになりました。
――どのような企業が魅力的に見えたのでしょうか。
皆さんご存知のトヨタ自動車はその代表例です。トヨタ自動車へは東海道新幹線の三河安城駅からトヨタ町の本社にタクシーで向かったと記憶しています。1995年2月には、当時の経営企画部副部長(後の副社長)の浦西徳一氏を訪ねました。トヨタでは中期経営戦略を策定し決定する、いわば戦国時代の軍師のようなポジションの方です。
――当時、トヨタ自動車はどのような策を持っていたのでしょうか。
トヨタ自動車は、毎年1,000億円前後の「バブルの垢落とし(合理化)」や1ドル100円を前提として新車開発でいかにコストを下げられるかなどに取り組んでいました。同時にそれらに必要なプラットフォームや部品の共通化などを進めていたと思います。これにより1994年には700億円、1995年は1,500億円を目指すとしていました。
また、1995年の年間生産台数は300万台程度でした。ただ、同年秋に作成した国際ビジネスプランでは2000年に600万台を悲願として決めていました。その後の進展状況については当時の鈴木武経理部長(後の専務)から詳細に説明してもらいました。バブル崩壊後、1992年3月に1,260円の安値をつけた株価は一時8,000円を上回りました(図表2参照)。
出所:SPEEDAをもとに編集部作成
――日本の製造業が強さを発揮した例は他にもあるのでしょうか。
ええ、事例には事欠きませんね。日本の製造業の強さそのものや事業構造改革といった経営者の努力の結果が数多く確認できた時代でもありました。
ダイキンはバブルのピーク時に生産キャパシティを拡大し、その負担で業績が低迷していました。業務用のパッケージエアコンを得意とする同社ですが、その技術を活かしルームエアコンでもグローバル展開することに踏み切りました。
1997年に当時の松居毅副社長、1998年に岡野幸義常務(後の社長)に経営戦略を伺いました。当時から、空調事業の成長ポテンシャルや同社の事業戦略に注目していました。海外比率は現在では70%超に達し、まさに日本の製造業としてお手本となるようなグローバル企業です。
株価は1997年から1998年に400円台をつけていましたが、2000年には2,000円台に達し、リーマンショックなどを乗り越え、最近では10,000円を達成しました(図表3参照)。
出所:SPEEDAをもとに編集部作成
また、1983年に上場したロームも、90年頃よりリストラ(生産合理化、不採算品整理、品番統廃合、小口受注排除)に取り組み、ニッチマーケットでの高付加価値製品に集中するという戦略が成功しました。当時の疋田純一常務とは再三ミーティングをしたものです。バブル時代は大きくは注目されませんでしたが、1992年に1,590円の安値からITバブルのピークでは4万円台に大化けした銘柄です。
同じくビジネスモデルの転換、リストラで業績を急回復させたのが武田薬品です。当時の武田國男社長の強力なリーダーシップのもと、事業の高付加価値化を推進していきました。食品、農薬、化粧品、工業薬品、化学、ヘルスビタミンをすべて売却し、医薬品に集中しました。驚きましたね。
平行して人員の適正化にも取り組み、当時11,000人いた従業員を7,500人にまで縮小させました。リュープリン、タケプロン、ブロプレス、アクトスなど大型新薬が全盛期であったこともあり、業績は急回復し、1995年の株価は1,100円台から1,700円台で推移していたのに対し、2000年は8,080円の高値を付けました。
「技術×経営」を評価-キヤノン、SMC
――当時から経営が上手だったなという企業はありましょうか。
キヤノンは当時の田中稔三経理部副本部長(現在の副社長)の時代から丁寧なIR(インベスター・リレーションズ)をしていました。その中で、ステッパー、インクジェットプリンター、バブルジェットプリンター、一眼レフカメラなど、ほぼ10年に1つのペースで大型新製品を発表し成長を続けてきました。これは非常に素晴らしい実績ですし、経営として技術の目利きと最終商品にする実行力があると思います。
また、キヤノンは生産面でも工夫を重ねてきた企業です。バブル崩壊後はトヨタの大野耐一氏が開発したセル生産方式を積極的に取り入れるなど、コストダウンに努め、業績を急回復させました。株価も1992年の1,200円の安値から、2000年5,020円、2006年9,020円と新高値を記録ししました。
ただ、そうした輝かしい実績がある一方で、最近はその流れが滞り気味なのが気になります。
――他に技術と経営において印象に残った製造業の企業はありますか。
忘れられない銘柄の1つがSMCです。1988年に初めて当時の高田芳行社長(現会長)、丸山勝徳取締役(現社長)と面談をしました。その後、1993年の面談で同社の長期的な成長力に確信を持ちました。同社は空気圧の世界No.1メーカーで、多品種ながら豊富な在庫を常に持ち、短納期の体制を整えています。また、先行投資的に必要以上のセールス体制をとり、年々グローバルのシェアを高めています。
初対面から20数年、一貫した経営体制は私の出会った会社の中でも抜群の評価をしてよいと考えています。1992年の株価は2,000円前後でしたが、現在の株価はご存知の通りです(図表4参照)。
出所:SPEEDAをもとに編集部作成
コーポレート・ガバナンスの先駆者-HOYA
――コーポレート・ガバナンスで特徴的な会社はありましたか。
コーポレート・ガバナンスについては、HOYAなくしては語れません。HOYAはコーポレート・ガバナンスを1994年に実施し、社外取締役を大量に迎え入れました。社内取締役はたったの3人だけでした。委員会等設置会社にもいち早く移行しました。
また、同社は事業の選択と集中にも積極的に取り組みました。祖業のクリスタルを分社化、高採算成長製品(ガラス、磁気メモリーディスク、眼内レンズ、LCD関連等)への投資を行い、メガネレンズの生産はタイ工場へ移すなどビジネスモデルの組み替えを大胆にそして積極的に行いました。
これらの施策に伴い、従業員も単体3,000人から2,000人へ、連結ベース9,000人から7,500人へリストラを行いました。結果、業績も急回復しました。
同社の長坂工場には年1回の工場見学の際にお邪魔させてもらいました。また、シンガポール工場へも個別にお願いして見学させていただいたのをよく覚えています。
運用で失敗したら悪あがきするべきではない教訓-オリンパス
――コーポレート・ガバナンスでその他に印象深い企業はありますか。
コーポレート・ガバナンスという意味で記憶に残っているのはオリンパスです。バブル崩壊後の1992年当時に森久志経理部主任(後の副社長)にお目にかかりました。同社は内視鏡の世界トップメーカーで、高採算潜在成長力も高いと評価できたものの、赤字と黒字を繰り返す傾向にありました。
また、カメラ部門を抱えていたため、株価はディスカウントされていました。当時の岸本正壽社長、その後の菊川剛社長にお目にかかった時もカメラ部門の売却について議論をした記憶がありますが、今日に至るも聞き入れられていません。
また、1992年時点で特金運用の損失が220億円あったので、早く処分するようアドバイスしました。後日、菊川社長、森副社長の時に特金の損失が大きく膨らみ、経営の根幹を揺るがす事態に至ったことを知って、忸怩たる思いがしました。株式投資で失敗をした時、悪あがきしてはいけないという貴重な経験であったといえます。
2000年にファンドマネージャーを引退
――ファンドマネージャーとして長期間の好パフォーマンスを維持していたこと自体、めずらしいと思います。
1978年に500億円で預かったファンドがあります。途中2回、他のファンドマネージャーに運用をお願いしましたが、大半の期間は私が運用しました。そしてファンドマネージャーを引退した2000年の運用資産規模(アセットサイズ)は5,500億円になっていました。平均して年率10%を超えるパフォーマンスということになります。
これは前半の1978年から1989年の11年間のバブル形成期〜バブル時代と、後半の1990年から2000年までの11年間のバブル崩壊〜ITバブル期を平均しての結果です。
この間には、今回お話しした銘柄以外にも、日本ガイシ、アサヒビール、オリエンタルランド、コマツ、ジェイテクト、信越化学、豊田合成なども特に思い出に残っています。株式市場は、その時々の経済を映し出す鏡とも言えますし、同時に時代時代で主役を生み出す力も持っていて、ファンドマネージャーを引退した今でも毎日相場を見ていると楽しいものです。
――大変貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
LIMO編集部