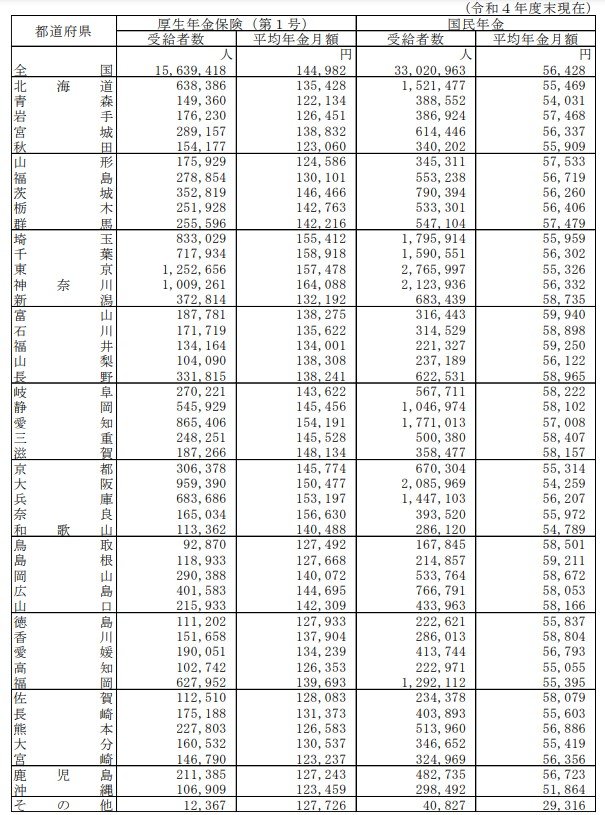2. 厚生年金の平均年金月額が高い都道府県・少ない都道府県ベスト5
厚生労働省の同資料より、「厚生年金の受給額」を都道府県別のランキング形式で見ていきます。
2.1 厚生年金の平均年金月額が高い都道府県ベスト5
- 神奈川県:16万4088円
- 千葉県:15万8918円
- 東京都:15万7478円
- 奈良県:15万6630円
- 埼玉県:15万5412円
2.2 厚生年金の平均年金月額が少ない都道府県ベスト5
- 青森県:12万2134円
- 秋田県:12万3060円
- 宮崎県:12万3237円
- 沖縄県:12万3459円
- 山形県:12万4586円
1位の神奈川県と47位の青森県では、月額4万円以上の差があります。
その差は年間にして50万円以上です。この違いに驚かれた方もいるのではないでしょうか。とはいえ、もちろん居住地で年金額が決まるわけではありません。
3. 厚生年金の年金月額に都道府県で差が出るのはなぜ?
厚生年金の受給額が個人で違う理由として、現役時代の賃金や加入期間が関わってきます。厚生年金の報酬比例部分は、以下の合計で決まります。
- A(2003年3月以前):平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの加入期間の月数
- B(2003年4月以降):平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数
このことから、年収が高い人や加入期間が長い人ほど、多くの厚生年金が受給できるといえるでしょう。
賃金の水準は都道府県によって差があり、都市部より高い傾向にあります。
その他、自営業の比率や共働きの比率も都道府県で異なるでしょう。こうした背景が絡み合い、年金受給額にも影響したと考えられます。
4. 国民年金の月額平均は5万円台
厚生年金は現役当時の働き方が影響する一方、国民年金は「国民年金保険料をどれだけ納めたか」で受給額が決まります。
このため、平均額は5万円台で個人差・男女差・都道府県格差も大きくありません。
参考までに、国民年金(老齢基礎年金)における都道府県の差も見ていきましょう。
4.1 都道府県別「老齢基礎年金」の平均年金月額
- 北海道:5万5469円
- 青森県:5万4031円
- 岩手県:5万7468円
- 宮城県:5万6337円
- 秋田県:5万5909円
- 山形県:5万7533円
- 福島県:5万6719円
- 茨城県:5万6260円
- 栃木県:5万6406円
- 群馬県:5万7479円
- 埼玉県:5万5959円
- 千葉県:5万6302円
- 東京都:5万5326円
- 神奈川県:5万6332円
- 新潟県:5万8735円
- 富山県:5万9940円
- 石川県:5万8898円
- 福井県:5万9250円
- 山梨県:5万6122円
- 長野県:5万8965円
- 岐阜県:5万8222円
- 静岡県:5万8102円
- 愛知県:5万7008円
- 三重県:5万8407円
- 滋賀県:5万8157円
- 京都府:5万5314円
- 大阪府:5万4259円
- 兵庫県:5万6207円
- 奈良県:5万5972円
- 和歌山県:5万4789円
- 鳥取県:5万8501円
- 島根県:5万9211円
- 岡山県:5万8672円
- 広島県:5万8053円
- 山口県:5万8166円
- 徳島県:5万5837円
- 香川県:5万8804円
- 愛媛県:5万6793円
- 高知県:5万5055円
- 福岡県:5万5395円
- 佐賀県:5万8079円
- 長崎県:5万5603円
- 熊本県:5万6886円
- 大分県:5万5419円
- 宮崎県:5万6356円
- 鹿児島県:5万6723円
- 沖縄県:5万1864円
- その他:2万9316円
国民年金においてはどの都道府県もあまり差がなく、受給金額は概ね5~6万円の範囲でおさまっています。
ちなみに全国平均は5万6316円となっています。
5. 年金受給額はそれぞれで目安を確認しておく
ここまで厚生年金や国民年金の平均受給額、都道府県による特徴を解説してきました。
それぞれで傾向がつかめるものの、やはり個人の事情によって異なるものです。
老後が近づいてから「ねんきん定期便の金額に驚いた」ということにならないよう、早くから見込額を把握しておけるようにしましょう。
ねんきんネットであれば、目安額だけでなく「今後の働き方を変えた場合の年金額シミュレーション」などもできます。
老後の収支を把握し、不足分の老後資金も早めに洗い出しておきましょう。
参考資料
太田 彩子