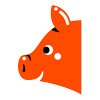株主優待を受けるために必要なのは、その企業の株主になることです。そして、ひとたび株主になれば、その企業の株価が今後どうなるかが気にならない人はいないでしょう。
どんなに株主優待の内容が優れているからといって、自分が購入した時の株価と比べて今の株価が大きく下落したのでは意味がありません。株主優待をきっかけに株式に投資をしたという場合でも、その企業の業績と株価には注意したいものです。
過去1年の株価動向
最後に同社の株価動向をチェックしておきましょう。
同社の過去1年の株価推移を振り返ると、下値は1900円台、上値は2600円を超えた水準での推移となっています。
1年前は2600円前後でしたが、現在は2100円台となっています。今後、第七次中期経営計画「IMPACT2020」を踏まえ、どのような株価展開になるのかに注目です。
まとめにかえて
多くの投資家を惹きつけてやまない株主優待ですが、実は一部では批判もあります。長期で保有する株主からすれば、「短期で売買を繰り返す株主に優待を提供するのはいかがなものか」というものです。
株主優待は自社サービスや商品の一部に関連する内容を提供する企業も多いですが、現金同等物のような内容の企業もあります。これは発行体からすれば確実なキャッシュアウト(現金流出)となります。短期間しか株主でない投資家のために、なぜ費用をかけなければならないのかという観点です。
様々な議論のある株主優待制度ですが、ぜひ、皆さんも株主優待でお得なライフスタイルを確立されてみてはいかがでしょうか。
【用語確認】そもそも「株主優待」とは何か
株主優待とは、「株主優待制度」とも呼ばれ、株主が何らかの特典を得られる制度のことを言います。
株主優待制度は日本の上場企業の中で広く実施されている制度です。発行体が提供するサービスや商品に関する優待内容、クオカードといった金券、または食料品などのケースもあります。日本の株主優待内容は多様性があり、世界でも稀な制度です。
ちなみに、日本の上場企業の株式に投資をしている投資信託を購入するのでは、個人投資家は株主優待の特典を享受することはできません。個別株式への投資が必要です。
【補足】株主のメリットは株主優待だけではない
株主のメリットはここまで見てきたような株主優待内容だけではありません。株主の権利としてより中心的なポイントとしては、配当を受ける権利があります。配当を出している企業であれば、年に2回、上期と通期決算のタイミングで配当が支払われることがあります。
会社の業績が良ければ増配されることもありますし、投資先などがない場合も配当を増やす企業もあります。株主優待の内容もさることながら、投資先企業の業績内容を確認して、配当が増えていくのを期待するのも株式投資の醍醐味です。
【注意点】株主優待を受けるために気を付けておきたいこと
株主優待を受けるためにはいわゆる「株主名簿」に株主として氏名が記載されていないといけません。「株主権利確定日」といわれる決算期末日に株主として記載されていなければなりません。
たとえば、決算期末日に売買をしたのでは、株主名簿に氏名が記載されません。株主権利確定日を含む4営業日前までに株式を購入する必要があります。
また、証券会社によっては単元未満株のサービスがありますが、株主になるためには最低の単元株式数を保有しておく必要があります。単元株とは、通常の株式の売買で取引される単位です。たとえば、100株というような単位となっています。銘柄ごとにご確認ください。
【ご参考】株主優待をはじめるにあたって必要なこと
証券会社を通じて株式を購入する必要があります。証券口座を開設するまでにはある程度時間が必要ですので、株主優待に興味のある方でまだ証券口座をお持ちでない方は前もって口座を開設しておくことをおすすめします。
余談ですが、株式投資をする際には、少額投資非課税制度である「NISA(ニーサ)」などを活用すれば非課税枠を利用することもでき、さらに「お得な株式投資」をすることができます。
【参考資料】
LIMO編集部