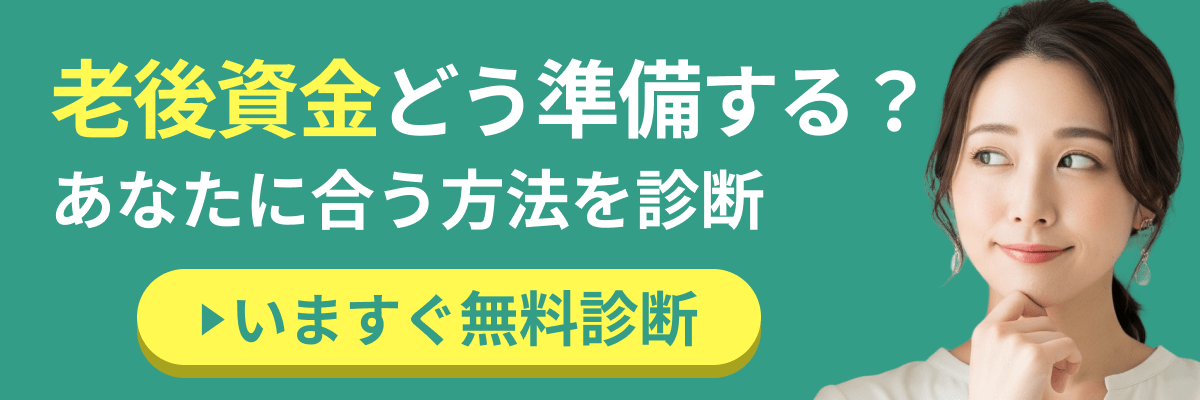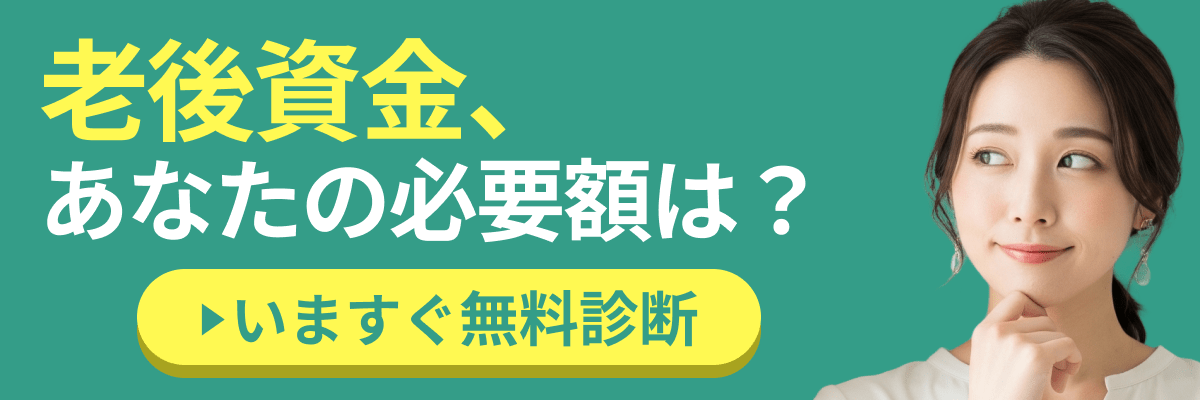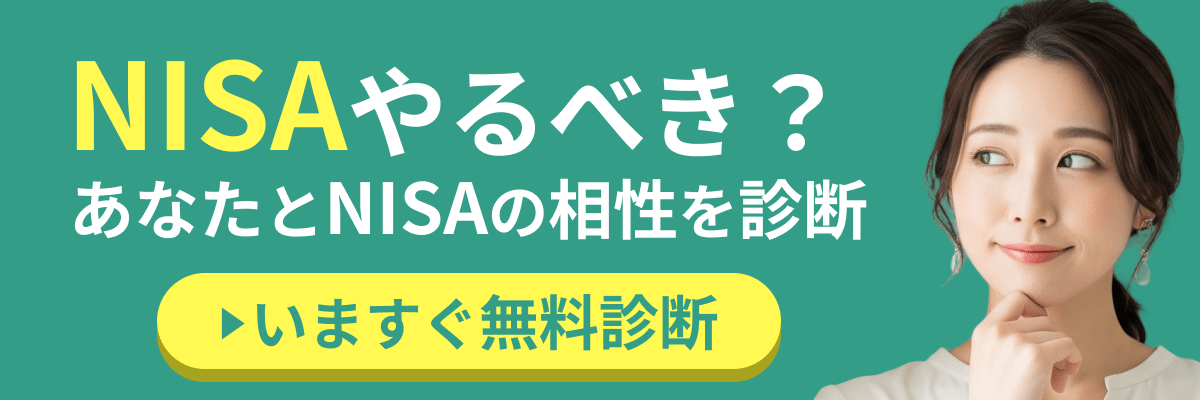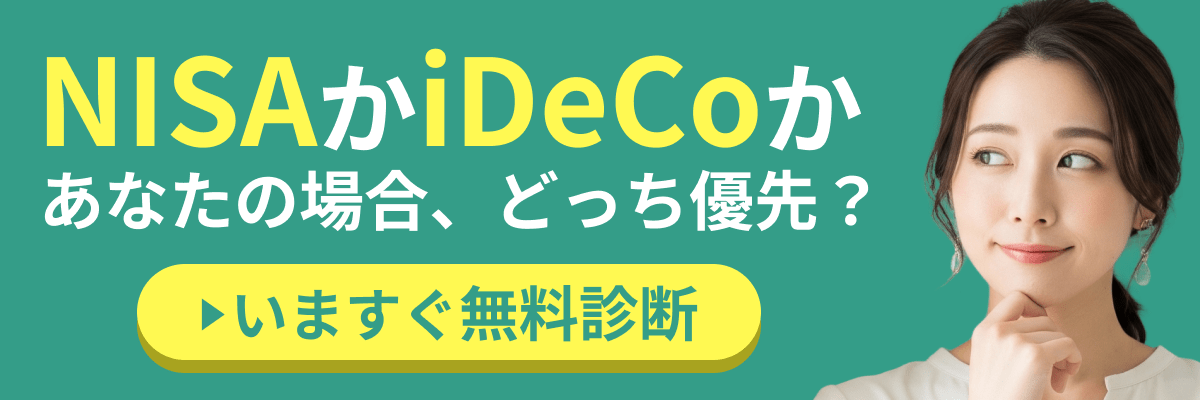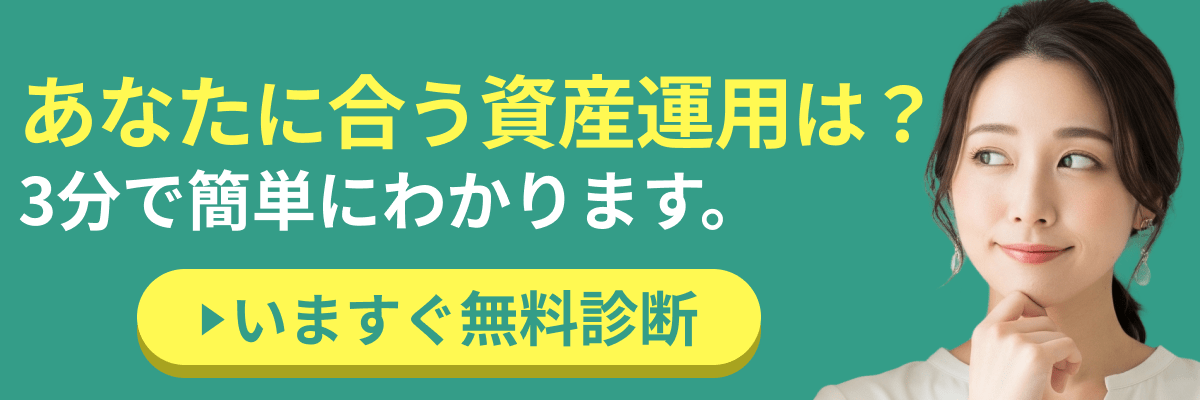老後資金が心配になる50代こそ、資産運用を始めるか悩む時期かもしれません。
「もう遅いのでは?」と心配な方もいるかもしれませんが、まだ間に合う可能性は十分にあります。
本記事ではその理由と投資のコツをわかりやすく解説します。
【無料】あなたがやるべき資産運用は?年収・資産から3分で診断
1. 50代の投資は本当に遅い?不安を払拭するためのポイント
50代から老後資金作りのための投資を始めても遅いのではと思っていませんか?その不安を払拭するポイントを紹介します。
1.1 定年までの期間を活用
職種や会社によって定年までの残り年数はさまざまですが、一般的には65歳が一区切りといわれています。たとえば50歳なら15年、55歳なら10年は老後資金を形成する余裕があります。さらに平均寿命の伸びによっては、働ける期間も延びる見込みがあり、その分運用で資産を増やすチャンスも高まるでしょう。
1.2 50代はまとまったお金を利用しやすい
20~30代に比べると、50代は預貯金や収入が多い場合が多く、子育てが落ち着いているケースも増えてきます。そのため、比較的まとまった資金を運用に回せるタイミングといえるでしょう。こうしたメリットを活かして分散投資を行えば、効率よくお金を増やすことも期待できます。
1.3 効率的に資産を増やせる可能性がある
積立投資は、複利効果を活かし、長期で運用するほど利益が増大しやすくなります。例えば、年利3%で毎月2万円を10年間積み立てる場合、合計元本240万円に対して約279万円に成長します。短期的には元本割れのリスクは高くなるため、長期運用を前提に、リスクを抑えることが大切です。
2. 50代が投資で気をつけたいポイント
実際に50代で投資を始める際に気をつけたいポイントについて解説します。
2.1 将来必要な資金を把握する
まず、老後にどのくらいのお金が必要かを計算してみましょう。年金収入や貯蓄、退職金の見込みを踏まえ、支出との差額を把握するのが大切です。よく用いられる計算方法としては「(年間支出 - 年間収入)×生活年数 - 現在の金融資産額」が挙げられます。先にゴールを明確にすることで選ぶべき運用方法が見えてきます。
現状で足りる場合
もし既に十分な貯蓄があるなら、リスクの高い商品を無理に選ぶ必要はありません。元本の安全性が高い債券や、値動きが比較的安定している投資信託などを活用し、積極運用よりも大きく損をしないことを重視した選択が適しています。
現状で足りない場合
一方、不足が見込まれるなら、以下を検討しましょう。
- 働く期間を延ばして年金増額や収入確保に努める
- 節約や生活水準の見直しで支出を抑える
- 投資信託と債券を組み合わせ、リスクを分散する
これらを並行して行うことで不足分を補いやすくなります。
2.2 資産を守りつつ運用を行う意識を持つ
50代の資産運用では、大きく増やすより減らさないことが重要になります。投資には元本割れの可能性が常にあり、リスクが高い金融商品ばかり選ぶと大きな損失につながるかもしれません。そこで積立投資の安定性と一括投資による効率性を組み合わせ、分散を図る工夫が求められます。
「毎月積立投資」+「まとまった資金の一括投資」
まとまったお金がある方は、まずは債券や保険商品といった元本を守りやすい手段で運用し、それと並行して少額の積立投資を行うのがおすすめです。こうしたハイブリッド型の運用なら、将来の予測が読みにくい状況でもリスク分散とリターンの両立を目指しやすくなります。
2.3 投資商品は慎重に選ぶ
世の中には投資信託だけでも約6000本あり、それぞれ手数料やリスク、運用方針が異なります。焦って選ぶと元本割れの可能性が高まるため、自分の許容リスクや目的に合った商品を選ぶことが大切です。迷ったときは経験豊富なFPやIFAに相談すると安心できます。
3. 50代におすすめの投資方法
50代が検討したい投資法には、毎月少しずつ買い増す積立投資と、一度にまとまった資金を投入する一括投資があります。ここでは、それぞれの代表的な商品について解説します。
3.1 積立投資
毎月コツコツ投資を続ける方法です。購入タイミングを分散できるため、相場下落時も一定額を買い付けることで平均取得単価をならし、リスクを軽減する効果が期待できます。
NISA
専用口座で投資商品を運用した際の運用益が非課税になる制度です。2024年に改正され、従来より投資可能期間や非課税枠などが充実。長期・積立・分散投資を促進する仕組みがさらに強化されています。つみたて投資枠と成長投資枠の2つを併用できるため、幅広い投資商品を非課税で保有できるのも特徴です。
3.2 一括投資
一度に大きな資金を投じる方法で、株式や債券、一時払い保険などが代表例です。まとまった額を運用するため、運用益が出れば大きなリターンが期待できますが、相場が下落すれば損失も大きくなる可能性があります。
債券
債券は国や地方自治体、企業が資金調達のために発行するもので、保有期間中は利息を受け取り、満期時に元本が返還される仕組みです。株式などに比べ価格変動が緩やかなため、リスクを抑えた運用に役立ちます。ただし信用リスクや金利変動リスクがある点は把握しておきましょう。
貯蓄型保険
保険料の中に貯蓄成分を組み込む一方、死亡保障などの万一の備えも得られる保険です。終身保険、変額保険、個人年金保険など種類が豊富なため、目的に応じて選べます。老後資金や教育資金を積み立てながらリスクヘッジをしたい人に向いています。商品ごとに異なる特徴があるため、事前にリサーチしておきましょう。
3.3 50代のポートフォリオの考え方
50代は、これまでに築いた資産を守りつつ、必要に応じて増やす運用スタンスが基本です。投資信託と債券など、価格変動の異なる商品をバランスよく組み合わせることでリスクを分散できます。まずは守りを優先し、負担にならない範囲でリターンを追求しましょう。
4. NISAとiDeCo、50代にはどちらが向いている?
NISAとiDeCoはどちらも税制優遇を受けられる便利な制度ですが、50代から始めるならどちらが適しているのでしょうか。目的や運用期間、引き出しの自由度などを総合的に検討する必要があります。
4.1 NISAは18歳以上なら誰でも利用可能
NISAは18歳以上なら誰でも口座を開設できます。売買の自由度が高く、非課税期間に制限がないため、柔軟に投資がしやすいのが利点です。ただし、投資の元本保証はなく一定のリスクを抱えることになるため、自分のリスク許容度に併せた商品選びが重要になります。
4.2 iDeCoは65歳まで拠出可能で節税効果が大きい
iDeCoは国民年金や厚生年金に加入していれば利用でき、掛金が全額所得控除になるなど節税面で優位性があります。ただし60歳までは原則引き出しができず、拠出可能な年齢にも制限があります。50代からでも将来に向けた積立を続けられますが、途中で資金が必要になると対処できない点は注意が必要です。
4.3 柔軟性重視ならNISA、節税重視ならiDeCo
運用期間や資金の流動性を重視するなら、NISAが向いています。掛金の自由度が高く、途中で引き出しもできます。一方、高い節税効果を求めるならiDeCoが有利ですが、60歳まで引き出せない制約を理解しておきましょう。両方を併用して運用の幅を広げるのも一つの手段です。
5. 50代からの投資に関するよくある質問
5.1 Q. 暴落した場合はどうすればいい?
投資は価格変動がつきものです。長く投資を続けていると、一時的な暴落に遭遇することもあるかもしれません。そんなときでも、慌てて売却せず長期で持ち続けることで回復してくる可能性があります。
実際、リーマンショックやコロナショックのように相場が大きく下がった後でも、歴史的には多くの場合、市場は時間とともに回復してきました。冷静に、投資を続けることを意識しましょう。
5.2 Q. 万が一の死亡時、投資資産はどうなる?
投資中に死亡した場合、保有する金融商品は相続の対象となり、遺族が手続きを行って引き継ぐ仕組みです。特にNISAやiDeCoの場合も、名義変更や解約などの手続きが必要になるため、遺族が困らないように証券会社や運営管理機関についての情報を共有しておきましょう。
5.3 Q. NISA・iDeCo以外の選択肢は?
50代の資産運用で大切なのはリスクを適切にコントロールしながら資産を守ることです。そのため、NISAやiDeCo以外にも、債券や保険といった商品を活用するのがおすすめです。必要に応じて複数の手段を活用しながら、資産を守りながら増やす戦略を検討するとよいでしょう。
6. まとめ:50代からでも遅くない!今から投資を始めよう
50代は老後までの時間が限られていますが、資産運用を始めるのに決して遅いということはありません。資産運用を活用するか否かで老後の生活水準に差が出る可能性があるため、少しでも早く始めるのがおすすめです。
50代からの資産運用では、リスクを抑えた堅実な運用をすることが重要になります。まずは将来必要となる金額を把握することからスタートし、リスクを取りすぎない方針で運用を行うことで、老後資金不足への不安を大きく軽減できるでしょう。
【無料】あなたがやるべき資産運用は?年収・資産から3分で診断
参考資料
マネイロ編集部