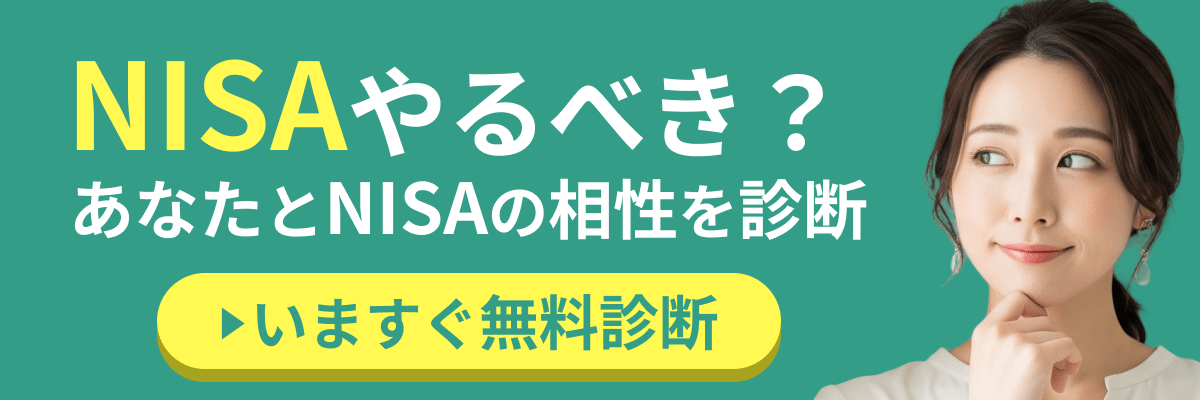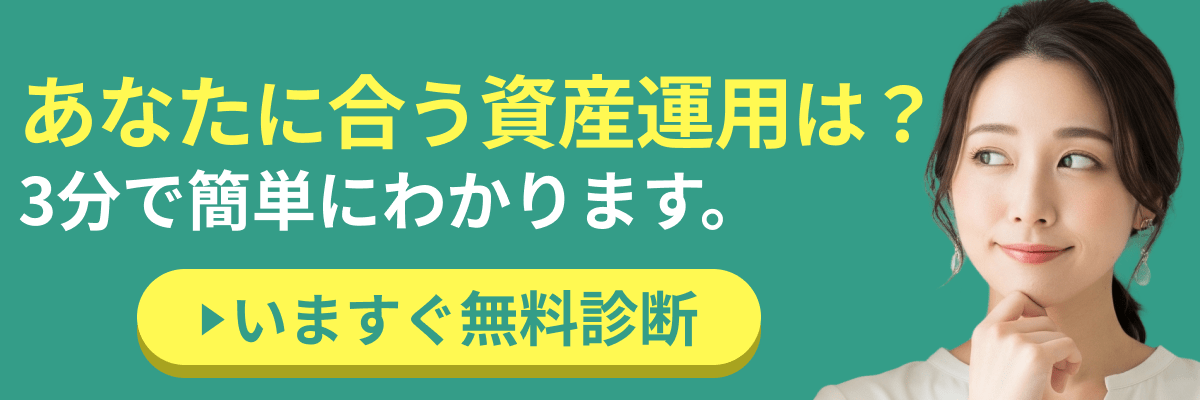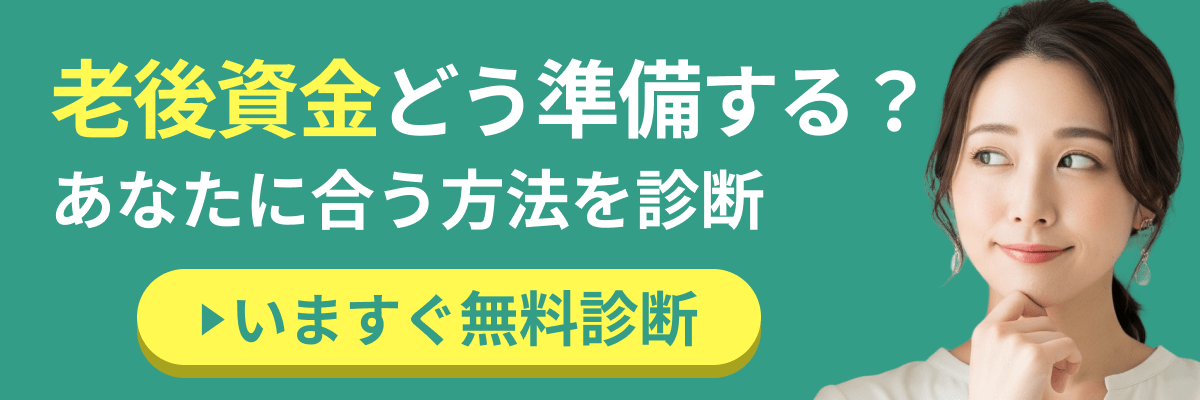投資による利益が非課税になるNISAは、少額からの資産形成を始める人に人気の制度です。
しかし、選び方次第では思わぬ損失や上手な運用ができないリスクもあります。
本記事では、初心者が避けるべき投資信託の特徴やNISAを活用するコツをわかりやすく解説します。
【無料】NISAはやるべき?あなたに向いている資産運用を3分で診断
1. NISAの基本をおさらい
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益が非課税になる特典があるため、多くの人が注目しています。一般口座や特定口座だと20.315%の税金がかかるところ、NISA口座ならその分がゼロになるので運用効率を高めやすいのがメリットです。
2024年からスタートした新NISAでは非課税保有期間が無期限となり、さらに長期的な視点で投資を続けられるようになっています。
1.1 新しいNISAの特徴
NISAは2024年に改正され、年間360万円(成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円)まで投資できるようになった他、非課税保有期間も無期限化されたのが大きな特徴です。生涯投資上限額も1800万円となり、より計画的に資産形成しやすくなりました。
1.2 NISAと一般口座・特定口座との違い
一般・特定口座では利益が課税対象となりますが、NISA口座なら運用益が非課税になるため、手残りが増えやすいという特徴があります。反面、NISAには投資できる上限額があるため、「大きな資金を一度に投じたい」という人には物足りない面もあるでしょう。それぞれの口座特性を理解し、資産状況や投資目的に合わせて使い分けることが大切です。
2. NISAのデメリットにも注意
NISAには魅力的な節税効果がある一方、把握しておきたいデメリットも存在します。制度の裏側を知った上で活用すれば、より失敗を回避しやすくなるでしょう。
2.1 元本割れのリスク
NISAが対象としている投資信託や株式は価格変動を伴います。相場の下落や運用方針の失敗によって、投資した資金が目減りし、最初に投じた元本を下回ることもあります。非課税だからといってリスクがないわけではないので、投資額やリスク許容度を慎重に考えましょう。
【無料】NISAはやらないほうがいい?あなたに最適な資産運用を3分で診断
2.2 判断を自分でしなければいけない
年々拡充されるNISAは自由度が増し、投資できる枠も広がっています。しかしそれは、いつ売却するか、どの枠をどう使うかなど、自分で決める事項が増えることも意味します。投資経験が浅いと、その多様さがかえって負担になる場合もあるでしょう。
2.3 意外と節税メリットが少ない場合も
NISAは「運用益が非課税」になる点がメリットですが、たとえばiDeCo(個人型確定拠出年金)のように積立時も所得控除を受けられる仕組みではありません。NISAの場合、利益が出ないと非課税の恩恵を感じにくい点を理解しておきましょう。
3. 初心者が避けたい「要注意の投資信託」とは
投資信託は、一見どれも似ているようでいて運用方針やコスト構造が異なります。特に以下の特徴を持つ商品は、初心者にはハードルが高いので注意が必要です。
3.1 特徴1 純資産総額が少ない
純資産総額が小さいファンドは運用終了(繰上償還)リスクが高まります。純資産が大きいファンドほど多くの投資家から信頼を集めている証でもあり、安定運用が期待できます。純資産総額の推移をチェックし、右肩上がりに増加している投資信託を選ぶとリスク低減につながるでしょう。
3.2 特徴2 信託報酬が高額
投資信託を保有している間ずっと支払う信託報酬は、運用成績に直接影響します。信託報酬が高いと本来得られる利益が圧縮されるため、リターンが伸びにくくなる点に注意が必要です。購入前に運用コストをチェックし、なるべく低コストのファンドを選びましょう。
3.3 特徴3 テーマ型投資信託
ITや医療など、特定のテーマに特化した投資信託は魅力的に見えますが、テーマが外れたりブームが終わると大きく値下がりする危険があります。長期運用を目指すなら、幅広い分野にリスクを分散できる商品を検討するのが無難です。
NISAで買えない投資信託の一例
NISAでは、信託期間が20年未満のファンドや毎月分配型、高レバレッジの投資信託などは対象外です。このように、つみたて投資枠・成長投資枠いずれにも該当しない投資信託もあるため、購入前に必ず確認が必要です。
【無料】NISAはやるべき?あなたに向いている資産運用を3分で診断
4. 投資信託を上手に組み合わせるコツ
異なる特徴をもつファンド同士を組み合わせることでリスクやリターンバランスを整えやすくなることがあります。ここでは上手に組み合わせるヒントをご紹介します。
4.1 インデックスファンドを中心に
日経平均株価やS&P500など、市場指数に連動するインデックスファンドは運用コストが低い傾向にあります。主軸にインデックスファンドを据えることで、長期的に安定した成長を期待できる仕組みを作りやすくなるでしょう。
4.2 値動きの異なるファンドを組み合わせる
複数の投資信託を組み合わせる際は、値動きの異なるファンドを選ぶことが、リスク分散のポイントです。例えば、S&P500などの株式型ファンドをメインにしている場合は、債券型のファンドを組み合わせることで「アセット(資産)クラス」の分散が図れます。これにより、相場変動時のダメージを抑え、全体のリスクを軽減する効果が期待できます。
5. 年代別・基本の投資信託の選び方
投資スタイルは年齢によっても変わります。ライフステージに応じてリスク許容度が変わるため、以下を目安に考えてみましょう。
5.1 20~30代
運用期間を長くとれるため、世界株式中心の投資信託でリスクを取りながら成長を期待するのも選択肢です。相場が下落しても複利効果を活かし、続けることで巻き返しを図りやすい年代といえます。
5.2 40~50代
段々と運用できる期間が短くなる他、セカンドライフも視野に入ってきます。株式などリスクの高い資産に偏らず、債券や保険などの安定型商品も組み込んで、バランス良く組成するのがポイントです。
6. まとめ
NISAは投資の利益が非課税になる魅力的な制度ですが、対象商品の特徴やコストを誤ると十分なリターンを得られないリスクも存在します。長期・積立・分散投資を意識して、下記のポイントを押さえましょう。
・元本割れのリスクや自己判断の増加にも注意
・信託報酬や純資産総額を確認し、投資信託を選ぶ
・不安があるならプロに相談し、計画的に運用する
NISAの非課税メリットを最大限に活かして、長く続けられる堅実な投資環境を整えましょう。
【無料】NISAはやるべき?あなたに向いている資産運用を3分で診断
参考資料
マネイロ編集部