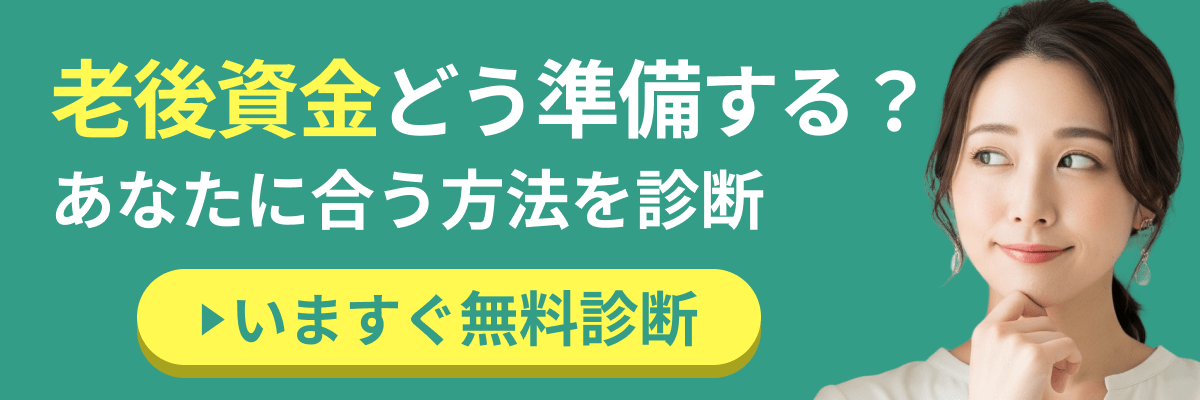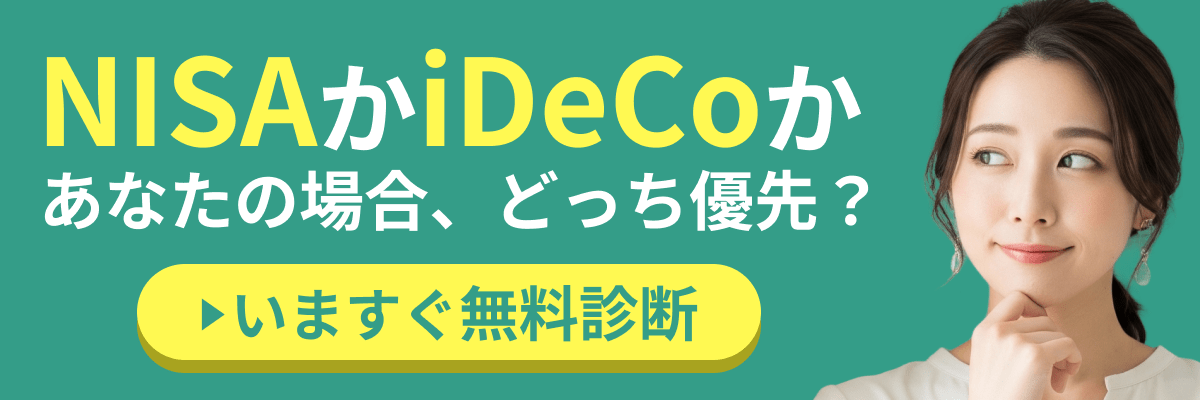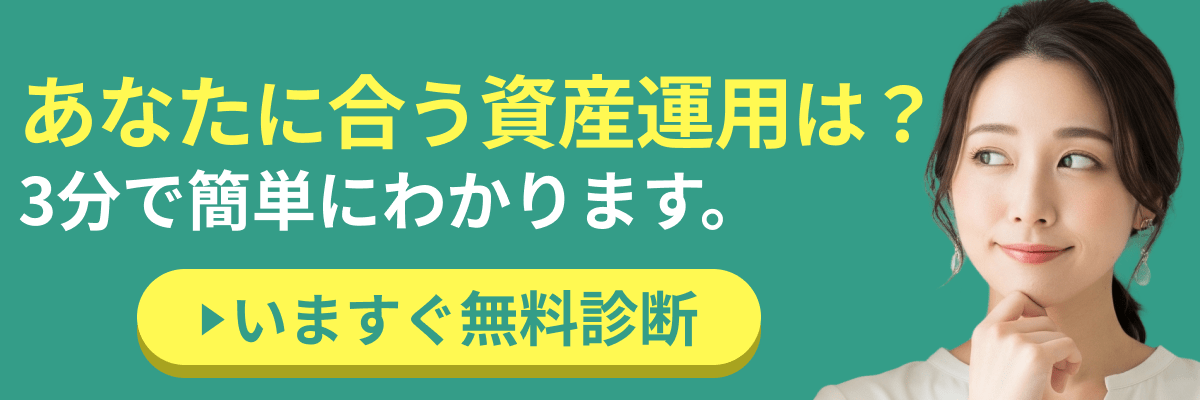将来への不安や理想の暮らしを実現するために、「お金をどう増やすか」に頭を悩ませる人は多いでしょう。
預貯金だけではなかなか増えにくい時代だからこそ、資産運用や税制優遇制度の活用が重要です。
本記事では、初心者でもできる実践的なポイントや具体的な運用方法をわかりやすく解説していきます。
1. お金を増やす前にやるべき3つのSTEP
効率的にお金を増やすには、まず事前にやっておくべき3つのステップがあります。しっかり確認しておきましょう。
1.1 STEP1.現在の資産を正確に把握する
まずは自分がどれくらいの資産を持っているか、全体像をしっかり把握しましょう。銀行口座にある普通預金や定期預金、さらに株式や投資信託など、どの金融機関にいくらあるのか一覧表を作成すると便利です。
定期預金であれば満期の時期、株式や投資信託なら評価額も併せて記入し、資産の現状を明確に確認してみましょう。
1.2 STEP2.増やしたい金額と期限を設定する
「いつまでに」「いくら」増やしたいのかを決めることで、お金を増やす手段を選びやすくなります。例えば、教育資金や老後資金、あるいは将来の住宅購入に向けた積立など、目的を定めることで具体的な金額と時期がクリアになり、目標に合った運用がしやすくなるでしょう。
1.3 STEP3.目標達成に向け、投資対象を検討する
目標がはっきりしたら、どの資産にどれだけ投資するかを考えます。株式や投資信託はリスクとリターンが高めですが、預金や保険商品は比較的リスクが低い分、リターンも小さめです。資産のリスク許容度を踏まえて、複数の商品を組み合わせる「分散投資」を意識すると安心です。
2. お金を賢く増やすカギは資産運用
資産運用は、余裕資金を預金以外の金融商品に投じることで、より効率的にお金を増やす方法です。銀行預金の金利が低い現状では、投資信託や株式などを活用し、利息や運用益を狙うほうが長期的な資産形成に有利といえます。毎月100円から積立ができる投資信託もあるため、大きな金額がない人でも始めやすいでしょう。
2.1 複利効果を活用する
複利は、「利息にさらに利息がつく」仕組みです。単利の場合、元本にのみ利息が付与されるため増え方は一定ですが、複利運用では運用益を再投資し続けるほど加速度的に資産が増えていきます。
例えば月2万円の積立投資で年利4%で運用できれば、30年後には720万円の元本が、倍近い1375万円にもなります。長期目線で投資を行うことで複利効果を最大化できるため、少額でも早めのスタートするのがおすすめです。
3. 資産運用を始める前に知っておきたい基本知識
3.1 長期・積立・分散が基本
投資は景気や政治情勢などで価格が上下しますが、長期間保有すれば一時的な値下がりを乗り越えやすくなります。
また、一度に大きな資金を投じるより、少額でもコツコツと積み立てることで買付価格を平準化し、リスクを抑える効果が期待できます。さらに、資産を国内外の株式や債券などに分散することで値動きの波を和らげることができます。
3.2 リスクとリターンは表裏一体
金融商品の世界では、リスクとは「値動きの振れ幅」のことを指します。
ハイリスク商品は短期で大きな利益を得る可能性がある反面、損失も拡大しやすい特徴があります。反対にローリスク商品は価格変動が小さい分、大きなリターンは見込みにくいでしょう。
自分がどの程度のリスクを取れるのかを認識したうえで、商品を選択することが重要です。
3.3 商品の仕組みを理解しよう
投資信託や株式、保険商品など、それぞれ値動きの特徴や運用ルールが異なります。仕組みを知らずに投資を始めると、相場の下落で即座に売却してしまうなど、タイミングを見誤る恐れがあります。商品のメリット・デメリットを把握し、長期的視野を持って運用することで、複利の恩恵も受け取りやすくなるでしょう。
4. 初心者向け!おすすめ資産運用4選
ここでは、特に初心者にもおすすめできる資産運用を4つ紹介します。
4.1 ①NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、株式や投資信託などの運用益にかかる税金が非課税になる税制優遇制度です。2024年に制度が改正され、非課税保有期間が無期限化されるなど、より柔軟に運用が可能になりました。
初心者にもおすすめなのは、「つみたて投資枠」を活用した長期目線での積立投資です。1本で世界株式に投資できる投資信託など、長期的に成長の見込める市場に投資するのがおすすめです。
4.2 ②iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、毎月の掛金が全額所得控除になるうえ、運用益も非課税となる私的年金制度です。NISAよりもさらに節税メリットが大きいのが特徴です。
ただし、原則60歳まで積み立てた資産を引き出せないため、急な出費には対応しづらい側面があります。掛金の上限は勤め先の年金制度によって異なる場合もあるので、事前に確認が必要です。老後の資金を手堅く作りたい人におすすめの制度といえます。
4.3 ③投資信託
投資の専門家が集めた資金を運用し、利益や損失を投資家に配分する仕組みが投資信託の特徴です。自分で銘柄を分析・選定する手間を省けるうえ、少額から分散投資も実践しやすいメリットがあります。国内外の株式や債券、不動産投資信託(REIT)など、多彩な分野に投資する商品が存在するため、目的やリスク許容度に合わせて選びましょう。
参考:NISAと投資信託の違い
NISAは、運用益が非課税になる「制度」であり、投資信託はその制度を利用して購入できる「金融商品」です。NISA口座を通じて投資信託を購入すれば、通常は20.315%かかる運用益への税金が非課税になります。なお、投資信託はNISA口座以外でも購入可能ですが、その場合は課税対象となります。
4.4 ④変額保険
変額保険は、死亡保障を備えながら保険料の一部を投資信託等で運用し、運用益によって受取額が変動する商品です。基本保険金額は保証される一方、満期保険金や年金原資は運用成果次第で上下します。積極的な資産形成と保険による保障を同時に得たい人には魅力的ですが、元本割れリスクがあることも理解しておきましょう。
貯蓄型保険という選択肢
保険の中には、満期時や解約時に資金が戻る貯蓄型保険もあります。変額保険ほどのリターンは期待できないものの、将来の受取額の目安が立てやすいのが強みです。投資リスクを抑えつつ、保障と貯蓄の両方を重視したい場合に検討してみましょう。
5. まとめ
お金を増やすには、まず自分の資産状況や目的を明確にし、必要な額と期間を設定することが大切です。その上で、NISAやiDeCoをはじめとする非課税制度や投資信託などを活用し、「長期・積立・分散」を意識した運用を続けましょう。
少額からでも複利効果を最大限に生かすことで、将来に向けた資産形成を着実に進めることが可能です。
投資は一攫千金を狙うものではなく、計画的に資産形成を目指すための手段です。短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点でじっくり取り組んでいきましょう。
参考資料
マネイロ編集部