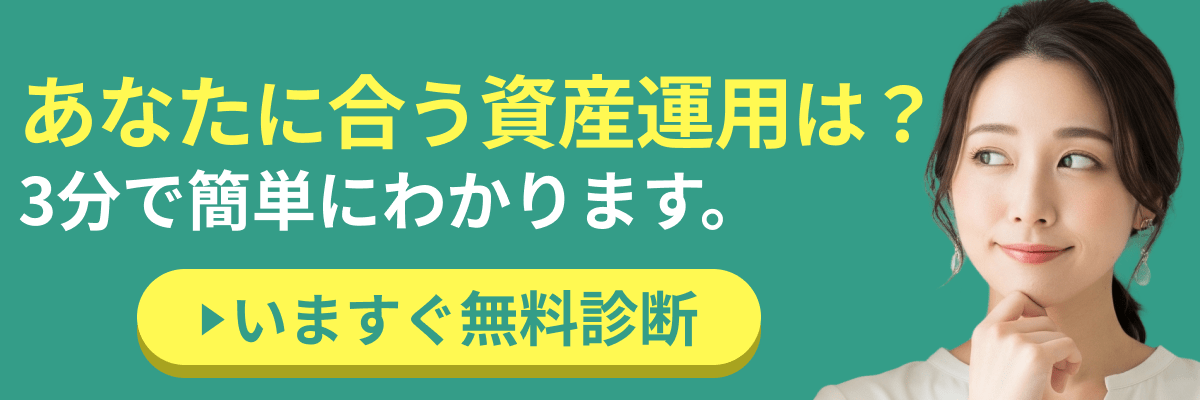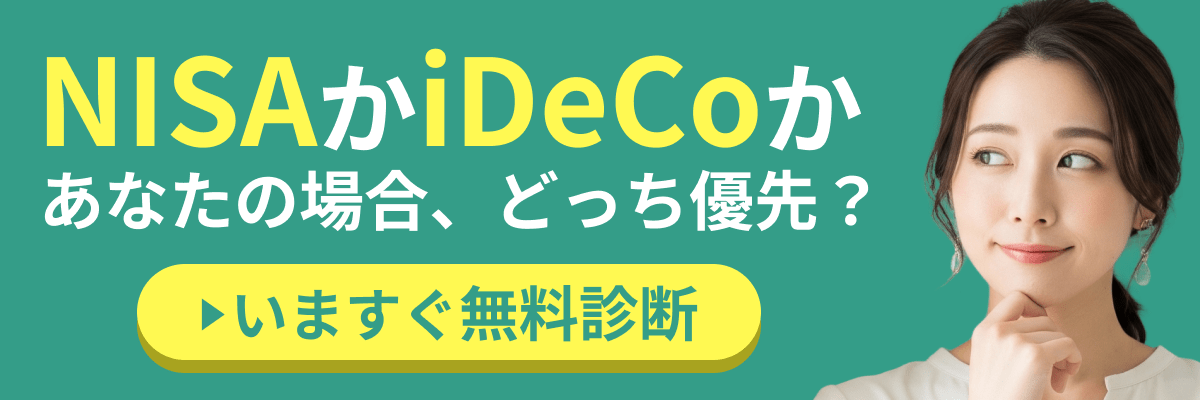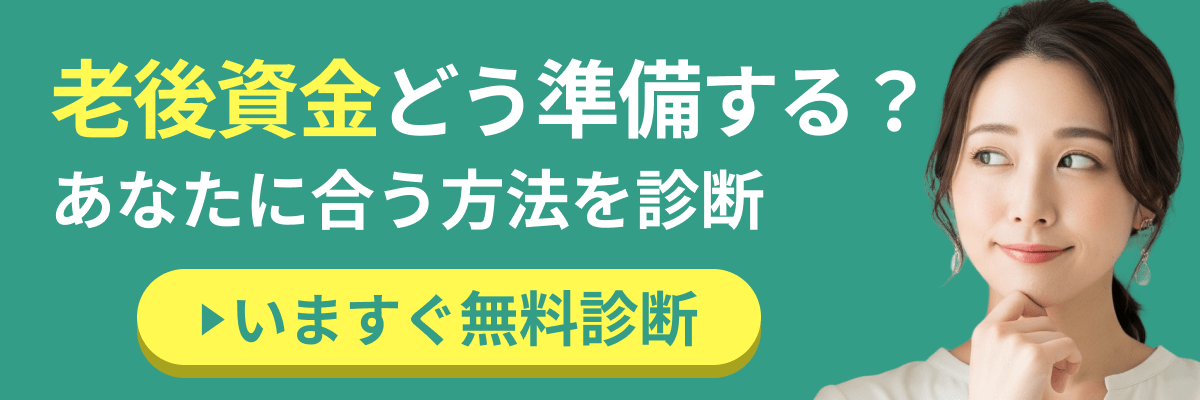500万円という資金を、効率的にかつリスクを抑えながら運用する方法はある?そんなお悩みはありませんか?
本記事では、まとまった資金の運用でお悩みの方に向けて積立投資と一括投資を上手に組み合わせる方法や、低リスクの商品を選ぶポイントを詳しく解説します。
堅実にお金を増やすイメージをつかむためにも、ぜひ最後までご覧ください。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収・資産から3分で診断
1. 500万円を運用する前に
まとまったお金の運用を検討する前に、まずは必ず押さえておきたいポイントを紹介します。
1.1 金融商品の多くは元本保証がない
金融商品は株式や投資信託、外貨預金など多岐にわたります。しかし、銀行預金など一部を除いて元本が保証される商品は多くはありません。値動きのある商品に投資する場合、運用益が期待できる一方で、元本割れのリスクも常に存在します。大切な資金を減らさないためにも、特性を理解しておくことが大切です。
1.2 金融商品ごとに異なるリスクとリターン
投資における「リスク」とは、「危険性」ではなく「価格の振れ幅」のことを指します。振れ幅が大きいほどリターンも大きくなりやすい反面、損失リスクも高まります。
反対に、リスクが小さいほどリターンも小さくなります。金融商品にはさまざまなものがありますが、「リスクが低くてリターンが高い」ものは基本的に存在しません。自分のリスク許容度に合わせて投資対象を吟味しましょう。
1.3 リスクが低めの商品から始めると安心
特に投資初心者は、まず値動きが比較的緩やかな金融商品から始めるのがおすすめです。たとえリターンが小さくても、投資経験を積みながら知識を身につけることで、徐々にリスクの高い資産に移行していく手もあります。いきなり大きくリスクを取らず、まずは「試し乗り」できる商品から検討するとよいでしょう。
1.4 万が一のために準備しておきたい「保険」
運用中にケガや病気で働けない状況になると、投資していた資金を取り崩さざるを得ない場合があります。しかし、投資商品はタイミングによっては元本割れすることも起こり得ます。もし医療保険や就業不能保険などの備えをもっておけば、運用している資産を取り崩す必要を減らせるでしょう。
1.5 生活防衛資金は預貯金で確保
投資するうえで、もっとも重視したいのは「生活に必要なお金は投資に回さない」ということです。必要不可欠な生活費や家賃、予定のある支払いなどに使う資金まで投資に充当すると、突然の出費に対応できなくなりかねません。
まずは預貯金で生活費6ヶ月分程度の生活防衛資金を確保し、それ以外の余裕資金で投資を行うのが基本です。
500万円をすべて投資に回すのはNG
貯めた500万円をそっくりそのまま投資に回すと、想定以上のリスクを背負ってしまいます。大幅な暴落があったとき、投資資金をすぐ取り崩す必要が出ると、回復を待てずに損失が確定する可能性も少なくありません。まずは当面必要な生活防衛資金を除き、残った余裕資金だけで投資するのが賢明です。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収・資産から3分で診断
1.6 ポートフォリオを分散してリスクを抑える
投資先を一つに集中すると、値下がりが起きたときのダメージが大きくなります。そこで、複数の資産や金融商品への分散投資が重要になります。分散投資を実践することで、全体のリスクを軽減させることができます。
株式、債券、投資信託、保険商品、不動産投資信託(REIT)などを組み合わせ、さらに国や通貨も分散すると価格変動の影響を抑えられるでしょう。
2. 運用のコツは「毎月の積立投資」と「まとまったお金の一部を一括投資」
次に具体的な運用のコツについて見ていきましょう。ポイントは、積立投資と一括投資の併用です。
2.1 積立投資は長期積立・複利効果・分散を意識
積立投資を行うと、タイミングを分散できるだけでなく「複利効果」も期待できます。特に投資信託を毎月コツコツ積み立てれば、基準価額が高いときには少量購入、低いときには多めに購入する「ドルコスト平均法」のメリットも発揮され、リスクを平準化できるのが大きな利点です。
複利で増やせる商品を選ぶ重要性
複利とは、利息や配当が再び運用に回ることで、お金が雪だるま式に増える仕組みです。積立投資型の投資信託や債券など、複利効果を生かせる商品に長期投資すると、時間の経過とともに効率よく資産が増える可能性があります。
2.2 一括投資は安定性や流動性もチェック
500万円のうち、ある程度大きな金額を一括投資する場合、リスクが高い資産だけに集中するのは避けましょう。株式はリターンが大きい反面、値下がり幅も大きくなりがちです。債券や保険商品など、安定性や換金性が比較的高いものに投資し、かつ複数の商品でリスクを分散すると安心感が増します。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収・資産から3分で診断
3. 積立投資をするなら!おすすめの資産運用
3.1 NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、個人の資産形成を後押しする、長期・分散投資に適した制度で、一定の投資枠内で得られる運用益や配当が非課税になります。少額からの積立に向く「つみたて投資枠」と、より幅広い商品が選べる「成長投資枠」の2つの投資枠があり、年間360万円、総額1800万円まで非課税で投資が可能です。また、売却した分の枠は翌年に再利用ができます。
3.2 iDeCo(個人型確定拠出年金)
老後の備えを強化したいなら、iDeCoという選択肢もあります。掛金が全額所得控除になり、かつ運用益が非課税で、受け取るときにも各種控除が受けられるなど、節税に優れた制度です。ただし、原則60歳まで資産を引き出せないというデメリットがあるため、事前によく比較して検討する必要があります。
3.3 投資信託
投資家から集めたお金を運用の専門家が株式や債券などに投資する仕組みが投資信託です。1本買うだけで複数の銘柄に分散投資できるなど初心者にとっては始めやすい反面、銘柄選定や売却判断が難しいというデメリットもあります。
4. 一括投資をするなら!おすすめの資産運用
4.1 債券
国や企業が資金調達のために発行する債券は、一般的に株式などより値動きが緩やかな傾向があります。ただし、まったく元本割れがないわけではなく、途中売却時の価格変動や発行体が破綻するリスクもゼロではありません。
それでも比較的リスクが低い選択肢として、株や投資信託と組み合わせて分散するのがおすすめです。
4.2 貯蓄型の保険(終身・変額・個人年金)
保険と資産運用を組み合わせるなら、貯蓄型保険が候補になります。外貨建て保険は金利が高いことが多く、円建てよりも返戻率が上がる可能性があります。
また、掛け捨てではなく資産として積み立てられるため、「貯めながら保障を確保したい」方には魅力的です。ただし、解約時期によっては元本割れとなる場合がある点にも注意が必要です。
外貨預金はどうか
外貨預金は一般的に高金利が期待できますが、為替手数料がかかり、為替相場次第で円換算時に目減りすることもあります。短期のキャンペーン金利だけに惹かれず、長期で見たときのリスクやコストも確認しましょう。場合によっては債券や保険商品の方が安定的に運用できるケースもあります。
5. 資産運用の始め方
5.1 STEP1. 目的と目標額の設定
まず、何のために資産を増やしたいのかを明確にしましょう。例えば老後資金が目的なら、60歳時点までにいくら必要かを逆算し、毎月の投資可能額や期間を割り出します。明確なゴールがあれば、使える制度や商品も絞りやすくなります。
5.2 STEP2. 投資対象を選ぶ
目標額や期間をもとに、どの程度のリスクを取れるかを検討します。長期運用できるなら高めのリスクを取ってリターンを狙うことも可能ですが、小さいリスクで堅実に運用したい場合は、預貯金や債券寄りの構成にするなど、人によって選ぶ金融商品は異なります。
5.3 STEP3. ポートフォリオを組む
株式・債券・保険・投資信託など複数の資産をどの割合で持つかを考えるのがポートフォリオ設計です。例えば若いうちは株式比率を高めにしてリターンを狙い、年齢が上がるにつれて安定重視にシフトするなど、ライフイベントや収入状況に応じて柔軟にアップデートしていくと安心です。
5.4 STEP4. 運用商品を選択
具体的な商品を決める段階では、信託報酬や為替手数料、保険料などのコストもチェックが欠かせません。同じカテゴリーの商品でも手数料が異なるため、ネットや店舗型の金融機関を比較しましょう。
5.5 STEP5. 口座を開設してスタート
金融機関で投資用の口座を開き、実際に購入する商品を設定すれば資産運用が始まります。ネット証券なら場所を選ばず申し込みできたり手数料が安かったりするメリットが、店舗型の証券会社なら対面サポートが受けられるメリットがあります。運用を開始したあとは、定期的に状況を確認し、必要に応じてリバランスを行いましょう。
6. まとめ
500万円のようにまとまった資金がある場合、資産運用の可能性が大きく広がります。ただし、失敗しないためにはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。
まず大切なのは、資産のすべてを投資に回すのではなく、生活防衛資金と投資資金をきちんと切り分けることです。そして、初めて投資を行う場合は、まず低リスク商品の積立投資から徐々にスタートするのがおすすめです。
また、資産運用する際には、NISAやiDeCoといった国の税制優遇制度もぜひ積極的に活用しましょう。ぜひ今回紹介した内容を参考に、効率的な資産形成に取り組んでみてください。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収・資産から3分で診断
参考資料
マネイロ編集部