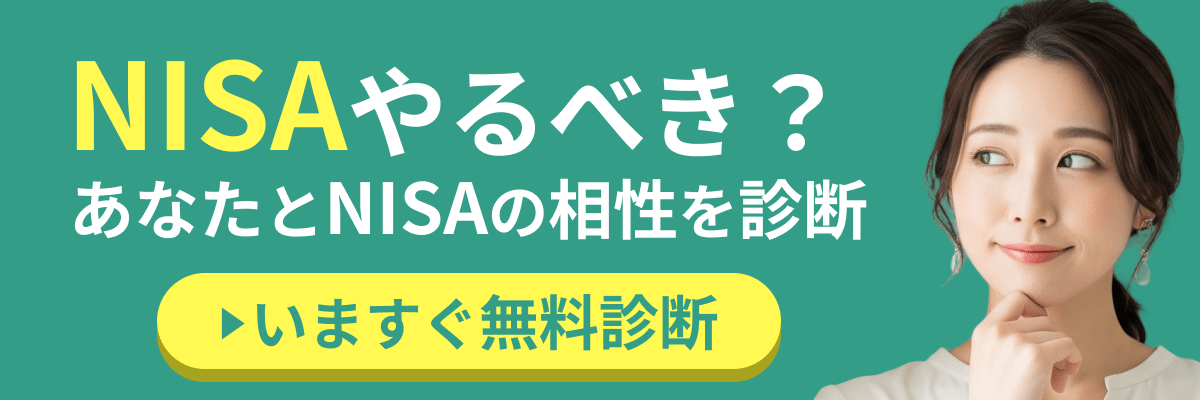2024年から制度が刷新されたNISAは、投資上限額の拡充や非課税期間の無期限化など、非常に使いやすい制度になりました。
「積立設定をすればあとはほったらかしでOK」という声もあり、初心者にも始めやすいイメージがありますが、反面、ほったらかしでも大丈夫かと不安に思う方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、NISAでほったらかしにする際の注意点や失敗しないための運用の要点について解説します。
1. NISAの運用をほったらかしにする際の注意点
NISAが刷新されたことで投資機会はさらに広がりましたが、NISAを開設しただけで満足し、長期間放置することには注意が必要です。まずは、ほったらかしの注意点について確認しておきましょう。
1.1 日々価格が変動するため元本割れリスクは常にあり
株式や投資信託、ETFなど、NISAで扱う多くの商品には元本保証がありません。経済指標や企業業績次第で、短期間に大きく値が動くこともあります。
放置している間に大幅下落してしまうと、そのタイミングで売却を検討する際に想定外の損失を被る可能性が高まります。特に自分のリスク許容度を超えるような商品を選んでいる場合は、定期的なチェックは欠かせないといえます。
1.2 売却時期次第では想定以上に損をするおそれ
もし市況の悪化時に売却した場合は大きな損失になりかねません。NISA口座では非課税制度の恩恵があるものの、投資である以上、商品自体の価格変動は避けられないため、安値の時期に売却を余儀なくされるとリターンは大幅に減少します。
そのため、いざというときに備えて投資プランをアップデートしておくことが大切です。
1.3 商品選びが不適切だとリターンを伸ばせない
NISAで投資する商品の選定は、将来のパフォーマンスを大きく左右します。特にほったらかしにしたい場合は、長期目線での投資が非常に重要です。そのため、長期的に成長が見込める株式やインデックス型投資信託など、自分の目標に合致する運用先を吟味することが必要不可欠です。
2. NISAの運用でほったらかしでも問題ないケース
投資対象が将来的に成長を見込みやすい場合や、余剰資金を長期で運用するつもりであれば、多少の放置でも大きな弊害は生じにくいといえます。
特に国際分散投資や株式主体のインデックスファンドを持つ場合、むしろ短期の価格下落には一喜一憂せず、長期視点で保有し続けるほうが結果的に好リターンとなる例も少なくありません。
【無料】あなたに向いている資産運用は?年収や資産から3分で診断
3. NISAで自分に合う商品の選び方
NISAを最大限活用するには、自分のライフプランやリスク許容度に適した商品を選ぶことが重要です。投資目的が明確であれば、無理のない範囲でリターンを追求でき、精神的にも安定して運用を続けやすくなります。ここでは4つの観点から、商品を選ぶ際のポイントを解説します。
3.1 ①投資目的とリスク許容度を明確にする
例えば、運用のゴールが老後資金なのか、子どもの教育資金なのかによって、求めるリターンと許容できるリスクは異なります。収入や年齢、投資経験に応じて「どの程度の価格変動なら耐えられるか」を最初に把握しておきましょう。
リスクが高い商品ほど見返りが大きい半面、下落時の損失も大きくなるため、慎重な判断が欠かせません。
リスクを抑えたい場合
安全性を重視したいなら、値動きが激しい株式だけでなく、株式と債券などを複数組み合わせたバランス型ファンドがおすすめです。組入比率によってリスク・リターンの度合いが変わるため、自身のリスク許容度に合わせて選定しやすいのが特徴です。特に、先進国債券を多めに含む商品は、値動きの振れ幅が比較的小さい傾向にあります。
リスクを積極的に取りたい場合
リスクを取って高いリターンを狙うなら、株式に的を絞ったアクティブファンドやインデックスファンドを検討しましょう。ただし、景気が好調なときには大きく伸びる半面、金融ショックなどが起きると一時的に資産価値が急落する可能性もある点には要注意です。長期目線で保有し、回復を待てるほどの余裕資金で運用するのが理想的です。
3.2 ②将来の成長が期待できる資産を選ぶ
NISAの非課税メリットを活かすには、長期的に値上がりが見込める資産を選ぶことが重要です。特定の地域やセクターに集中投資するより、世界株式に幅広く投資するファンドなどでリスク分散を図るのも一案でしょう。幅広い国々に投資先を分散しておけば、一部の市場が低迷していても他地域の好調さでカバーできる可能性が高まります。
3.3 ③純資産残高の推移をチェック
投資信託を選ぶ際には、純資産残高の増減が投資家からの人気度や運用実績を反映する指標となります。右肩上がりに資金が流入しているファンドは、長期的に注目されている可能性が高いといえます。
一方で、残高が減少し続ける投資信託は早期償還リスクがあるため、検討時には安易に飛びつかず注意深く観察しましょう。
3.4 ④投資対象が同じなら手数料を比較
同じインデックスに連動する複数の投資信託が存在する場合、信託報酬の差が運用成果に響きます。手数料が高いほど、長いスパンで見たときにリターンが目減りしやすい点を理解しましょう。
NISA対象のインデックスファンドでは、商品性が似通っているケースもあります。そのような場合は運用コストを比較して投資先を検討するとよいでしょう。
4. NISAの運用でおさえておきたいポイント
NISAは便利ですが、積立か一括投資かに応じて最適な対策が異なります。特に積立投資では商品選びの精査や定期的な運用レビューが重要です。
一括投資なら、大きな資金を一度に投入するぶん、投資先選定や売却タイミングがシビアになります。自分のライフイベントを踏まえ、常に運用計画を更新しておくことが欠かせません。
4.1 積立投資の場合
毎月の積立は平均購入単価を平準化できるメリットがあります。ただし、投資対象が長期低迷している場合はリスクが高まるため、定期的にモニタリングやファンドの見直しを行いましょう。
4.2 一括投資の場合
一括投資は投資する時点の相場動向が大きく影響するため、購入・売却のタイミングがリターンを左右する傾向があります。一括投資でこのようなリスクを抑えたい場合は、米国債など、比較的堅実な商品を選ぶという手も有効でしょう。
5. NISAで期待できる利益をシミュレーション
仮に投資信託を年利3%で運用するとした場合、複利効果によって長期保有すればするほどリターンが増えることになります。下表は月1万円を5年・10年・20年・25年・30年の期間で運用した場合を比較した例です。非課税制度を活かせば課税分が差し引かれないため、結果的により多くの資産を形成しやすくなります。
5.1 月1万円を年利3%で運用した場合
画像参照:月1万円、年利3%で運用した場合
年利3%で運用する場合、月々1万円でも10年運用すると約139万円に、さらに運用期間を20年にすると約328万円、30年にすると約582万円にもなることが分かります。
5.2 NISAの運用はライフステージが変わった時に見直す
結婚や子どもの誕生、転職、退職など大きなライフイベントがあると、家計状況や必要となる資金が変化します。それに合わせて投資方針を見直すことで、無理のない資産形成を続けられます。必要に応じて商品変更や積立額の調整を行い、常に現在の生活スタイルに適した投資計画を維持しましょう。
6. あらためて知っておきたいNISAに関する基本知識
新しくなったNISAでは投資上限額や非課税期間が大幅に拡充され、これから資産形成を始める方に有利な仕組みになりました。非課税枠の恩恵を最大化するには、年間360万円の投資枠や生涯1800万円の保有限度額を上手く活用し、長期分散投資に徹することがカギとなります。
6.1 非課税の仕組みとは?
本来、株式や投資信託の売却益や配当金には20.315%の税金が課されますが、NISA口座を利用するとこの税金がゼロになります。旧NISAでは投資期間が数年または20年と限定されていましたが、新NISAでは保有期間の上限がなくなり、焦らずのびのび運用できる環境が整いました。
6.2 年間投資枠と非課税保有限度額
NISAには「つみたて投資枠(年120万円)」「成長投資枠(年240万円)」の2つの投資枠があり、合計360万円まで非課税投資が可能です。また、個人が投資できる生涯の非課税限度額は1800万円となっており、ほとんどの人にとって十分な投資枠が用意されているといえます。
6.3 つみたて投資枠と成長投資枠の投資対象
つみたて投資枠は、厳選された投資信託が中心で、長期分散投資に向いた商品が並びます。インデックスファンドが多く、手数料も低めが主流です。
一方の成長投資枠では、株式やETF、REITなど多様な商品を選択でき、まとまった資金で一括投資することも可能です。投資スタイルや好みに応じて両枠を使い分けましょう。
7. まとめ:NISAは長期目線で適切な商品を選択し、定期的な見直しを
NISAは、基本的に長期投資を前提にした制度で、初心者が「ほったらかし投資」をするのに向いている制度といえます。とはいえ、考えなしに商品を選び、ほったらかしにしていると、思わぬ落とし穴にはまることもある点は理解しておいたほうがよいでしょう。
もし長期的な目標とリスク許容度が明確なのであれば、最初に運用の基本方針をしっかり固めるだけでも安定的に資産形成を進められる可能性が高まります。NISAの強力な非課税効果を味方につけるためにも、定期的に商品や進捗を確認し、必要に応じて戦略を更新することも検討しましょう。
参考資料
マネイロ編集部